注目
「変容論的アプローチの適用」の段階論と現代資本主義論への適用-7:商業機構
商業機構
展開
商業資本が分化する前のいわば「 原初的な」 産業資本では、確定的な生産過程に投下される生産 資本と、不確定な流通過程に投下される流通資本の2つからなる。2つの性質の違いから内的な矛盾が生じる。商業資本が分化すれば産業資本と商業資本の間の外的な矛盾となる。商業資本の役割は不確定な流通過程を産業資本から代位することだが、商業資本は本来的に「変わり身のはやさ」を身上としており、取り扱う商品の種類と量を変更する。このため産業資本は流通過程をいったん商業資本に押し出したとしても、商業資本が買い取らなくなって産業資本は流通過程の「押し戻し」を受ける可能性がある
小幡『経済原論』では「商業資本」の項には開口部はないが、「市場に組織的な取引網が整理されれば」、「市場のもつ無規律性が、商業資本によってある程度解除できる」しかしこれは「理論的に演繹できる商業資本の一般的な性質というよりも、卸売・小売などの取引組織や商習慣など、さらに特殊な条件を追加することではじめていえる効果」としている(218)。つまりこの「効果」は原理論で演繹できない、現実に存在する仕組みを取り入れることであり、これらは原理論の対象外となろう。
変容
しかし商業資本による「組織化」は最近の原理論研究ではいろいろ論じられてきた。産業資本が流通過程の負担を解除できるには、商業資本が継続的な買い取りや大量買い取りなどの形で買い取りを保証する契約を結ぶ必要がある、とともに商業資本も契約解除のオプションを持つ、という説明だ。これが「組織化」とよばれる。しかしこれは外的な矛盾に対処するための折衷的な説明にとどまっている。理論的にはこの外的な矛盾への対処として、一方の軸と他方の軸を分析基準として切り出し、現実の商業資本が占める位置は二つの軸の間、という形に整理する必要がある。2つの軸を変容αとして示すと以下のようになる。
表 商業資本の変容α
|
変容 |
多数の産業資本の共同の流通資本の役割 |
多数の商業資本が入れ替わり買取 |
|
①組織的な関係 継続的・大量買取 |
②スポット的な関係 非継続的・非大量買取 |
|
|
展開 |
(原初産業資本→)流通資本の自立化(→その他のさまざまな市場機構) |
|
①は要するに実態としては原初的産業資本の流通資本と生産資本と同じ関係だが、形式的に別の資本、という意味である。
ここで組織的関係について、継続的買取と大量買取には互換性がある。【買取量合計 = 単位期間の買取量 × 買取継続期間数】なので、産業資本における流通過程の負担を商業資本が代位できるとすれば、商業資本による単位期間の買取量が、産業資本の単位期間の生産量の多くの部分を占める必要がある。産業資本が産業資本にある現在の在庫量を超えて大量に買い取る場合、引き渡しが複数の期にまたがるならば継続買取と同様の効果になる。逆に継続買取も複数の期間をまとめてみれば大量買取と同様の効果になる。組織的な関係が強くなれば、部分的な経営統合になる。
次に②スポット的な関係、非継続的・非大量買取では、商業資本は在庫商品を買い取らなければ事業活動ができないから、多数の商業資本が存在していれば、産業資本から買い取ろうという動きが多数発生することで産業資本には買取が保証され、流通過程の負担を解除できる場合がある。ただしこれが確実に成立するには、産業資本に対して多数の商業資本が1か所に接するという特殊な外的条件が必要になる。たとえば生鮮市場でのせり売買のように買い手が商品に群がっている状況である。
①と②は両極端であり、現実にはその間となる。①の場合でも未来永劫、買取続けることはなく、②のスポット買いでも単品で買うわけではなく、さらに将来の見込み次第で買取量は増える。
産業資本からすれば不確定な流通活動押し出そうとして①の関係を求めるだろう。商業資本からすれば、①で流通過程の負担を各自に確実に引き受けることで買い取り価格を下げるかもしれないが、しかし変わり身のはやさを維持するために②の関係になる傾向もある。
次に①の組織的な買取関係は原初産業資本の価値に近づくが、そこには矛盾がある。確定的な生産過程に合わせて両者の関係を作るか、あるいは不確定な流通過程に合わせて両者の関係を作るか、という違いである。これは①の組織的な買取関係を前提にしてさらに生じる変容βである。
表 組織的な関係における変容β
|
多態化 |
流通系列化など |
製版統合(さまざまな連携、PB、SPA…)… |
|
変容β |
③産業資本から編成 |
④商業資本からの再編成 |
|
流通過程の変動を流通資本が吸収 |
流通過程の変動の吸収を生産過程も担う |
|
|
生産過程の安定的継続 |
生産過程の不断の変更 |
|
|
変容α |
①組織的関係:継続的・大量買取の深化・拡大 |
|
|
展開 |
(原初産業資本→)産業資本と商業資本との分化(→その他の分化) |
|
原理的には産業資本も商業資本もどちらかが特別に有利な立場に立つとは言えないため、組織的な関係においてどちらかの側における支配・被支配の関係は存在しない。しかし生産過程における「固定資本の巨大化」や、「小売商業の大規模化」といった外的な条件が加われば、変容βに達する可能性がある。
多態化
「固定資産の巨大化」の場合には、巨大な産業資本による流通系列化の傾向が生じる。これは変容βの「③産業資本から編成」が具体的に取る形である。「固定資本の巨大化」とは宇野が帝国主義段階論で重視したもので、後発国で新しい重化学工業が導入される場合、従来の資本蓄積の規模とは非連続的に大きな固定資本が建造されることである。この流通系列化については森下二次也らの商業経済論の中で十分に論じられてきた。
「小売商業の大規模化」の概念には検討が必要である。商業資本の大規模は、これまで商業経済論が論じているように、個別店舗の大規模化と、多数の小売店舗チェーンの拡大による大規模化の2つの方向がある。ただしこれだけでは商業資本自身の規模の問題であり、産業資本との関係を示すものではない。産業資本を含めた組織化にとって商業資本の規模が問題になるのは、まず㋐産業資本との関係では、個別の産業資本の生産量に対して個別の商業資本の買取量が「大規模」ということである。次に、㋑小売商業資本間の競争において品揃えに差がつかなくなるほど「大規模」となり、生産過程に関与する必要が生じる場合である。
まず、㋐については、多数の産業資本から少量ずつ商品を仕入れて、合計量で販売が「大規模化」しても、個別の商品について産業資本との関係では「小規模」にとどまる。そのため「大規模」になるには、商品の単品レベルで「大規模」となる必要がある。そのため、POSシステムのように単品レベルで全店舗的に販売を管理し、チェーン店の本部で一括して大量に仕入れ、さらに物流システムを構築することで初めて「大規模」となる。こうした技術が「商業資本の大規模化」の外的条件の一つとなる。
次に、㋑については、店舗が大規模化し、品揃えが非常に多くなると、他の大規模店との差異が減少する。つまり小さな店舗であれば品揃えの違いを生み出すことができるが、極端に抽象的に1つの大規模店舗にすべての商品が販売棚に並ぶと、2つ以上の大規模店は全く同じ品揃えとなる。そうすると大規模商業資本間の競争は価格を引き下げるか、あるいは他の大規模店にはない独自の商品の種類を取り扱うことが必要になる。いずれにしても商業資本は生産過程への関与を深めざるを得ない。そのとき、商業資本は個々の産業資本に対して大規模な買取が前提になる。関与とは、商業資本における変わり身のはやさに合わせて、生産過程で生産される生産物の種類と量が商業資本の要求に応じて変更できることである。これは生産の効率を下げることになるが、それを可能にする生産技術が必要になる。
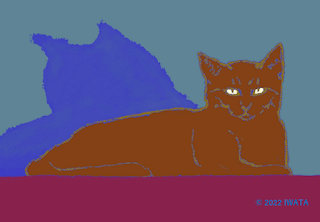

コメント
コメントを投稿