注目
価値形態論の研究ではandとorの関係が複数の異なる意味で用いられることがある。
価値形態論におけるandとor
以前、論文「商品集積体と債権化から信用貨幣を導出する新しい価値形態論:orの関係で結びついた商品集積体を基礎として」を投稿した際の査読で「andとorの関係がわからない」というコメントがあった。andは複数の商品セットが一体で取り扱われるのに対して、orは複数の商品セットの中のいずれか一つを選ぶということなので、さほどわかりにくくはないはずだ。しかし、価値形態論の研究の中ではandとorの関係が複数の異なる意味で用いられているので、わかりにくくなっているのかもしれない。
たとえば、山口重克『金融機構の理論の諸問題』や、小幡道昭『経済原論』では異なる意味で使われている。以下、その説明をする。ただし、表現の仕方は原著とは異なり、上記の私の論文の表現方法に依る。
山口『金融機構の理論の諸問題』283頁での使い方
同書で山口は、岡部説(岡部洋實[1996]「貨幣『制度』生成の論理」)への批判の中でandとorという言い方をしている。その内容を上記の私の論文の表現方法で説明すると、まず、展開された価値形態において商品Wiの所有者Piが等価形態に置く複数の商品、{W-1i, ,j}; j =1, 2, 3, … となる。
山口も依拠している宇野学派の価値形態の通説では、商品所有者iにとって集合{W-1i,1, W-1i,2, W-1i,3, W-1i,4, W-1i,5, W-1i,6, …}の各項(各商品)はいずれも等位に欲求の対象である。
次に複数の商品所有者を考えるために集合{W-1i, ,j}を{W-1i}と表記する。n人の商品所有者の集合をNと表記して、それぞれの商品所有者が欲する商品集合の共通集合を次のように示す。
BN=
BNはN人の商品所有者から共通して等価形態に置かれる商品であり、一般的等価物になる。これが時間をまたいで固定化すれば貨幣形態になる。
ここで集合{W-1i, j}; j =1, 2, 3, … 内のそれぞれ商品は、商品所有者Piがすべてを等しく欲するという意味でandの関係となる。つまり
Wi = W-1i,1
and
Wi = W-1i,2
and
Wi = W-1i,3
and
…………
ところが岡部説では、宇野学派の通説とは異なり、簡単な価値形態で等価形態に置いた一つの商品を交換で入手できない場合に、次善の策として第2、それもできなければ第3に、というように欲する商品を順番に等価形態に並べることで、展開された価値形態になる。つまり、{W-1i, j}の集合内で、{W-1i,1 , or W-1i,2, or W-1i,3, or W-1i,4,
or W-1i,5, or W-1i,6, …}(orは「そうでなければ」の意味)と添え字の数字の小さい順で欲するので、どれか一つが入手できればそこで交換のための価値表現は止まる。ここで集合{W-1i, j}; j =1, 2, 3, … 内のそれぞれ商品は、どれか一つが入手できればよいという意味でorの関係になる。この場合、直接的な欲求の度合いの低い商品でも一般的等価物、そして貨幣になる可能性がある。
宇野や山口の場合は、貨幣に選び出される商品、つまり貨幣商品は、欲求の対象とならなければならない、という点で貨幣商品の種類に制限が強くなるが、岡部の方法であれば、直接的な欲求の対象としては強くは求められない商品が貨幣になりうるので、貨幣商品の種類に制限が少なく、金本位制の離脱も含めて現実の貨幣の説明が容易になる可能性がある。とはいえ、直接的な欲求の度合いの低い商品が優先的に一般的等価物になりやすい、ということにはならない。この方法の是非はここでは問わない。山口の同書や海大汎[2019]「価値形態論の再考:価値形態の移行過程を中心に」になどに考察がある。
小幡道昭『経済原論』問題18(39頁、解説は282-283頁)での使い方
小幡『原論』では、展開された価値形態は、もともと欲していた商品を交換するための間接交換の方法である。つまり、商品所有者Piが所有する商品をW(Pi)とし、商品所有者iがもともと欲する商品W-1(Pi)と表記すると、量の関係を捨象して表現すれば、簡単な価値形態は、
W(Pi)= W-1(Pi)
となり、展開された価値形態は以下のようになる。
W(Pi)= {W-1i, j}; j =1, 2, 3, …
これは間接交換の第1段階であり、間接交換のルートを商品所有者Piから進む形で第2段階を表現すれば、{W-1i, j}=W-1(Pi)である。第1段階と第2段階を連結すれば、
W(Pi)⇒{W-1i, j}⇒ W-1(Pi)
となる。
この式で分かるように、商品所有者iにとって、{W-1i, j}に並んだ商品はあくまでも間接交換の手段なので、{W-1i, j}の中のいずれか一つでよい。つまり、{W-1i,1 , or W-1i,2, or W-1i,3, or W-1i,4,
or W-1i,5, or W-1i,6, …}(orは「または」の意味)として、{W-1i, j}内の各商品はorの関係になる。
ところが、ややこしいことに、小幡『原論』283頁の解説では、岡部の方法をandとよんでいる。つまり、岡部の方法では展開された価値形態の等価形態に並んだ商品は、欲求の程度の差はあるが、いずれも欲せられている商品なのでandとなるが、他方で小幡『原論』では展開された価値形態の等価形態に並んだ商品は交換の手段として一つ入手できれば十分なので、その中のいずれか一つという意味でorの関係になる。ここでも、andとorという表現を不用意に使うと混乱を招くことがわかる。
念のため、展開された価値形態における宇野(山口)、岡部、小幡の方法をまとめると、宇野(山口)では等位に欲求される多数の商品が並び、岡部では欲求の優先度で多数の商品が並び、小幡では間接交換の手段の手段として多数の商品が並ぶことになる。
最初に挙げた岩田[2022]での使い方
andの関係はさくら原論研究会『これからの経済原論』の方法で、
W(Pi)={W-1i,1, and
W-1i,2, and W-1i,3, and W-1i,4, and W-1i,5,
and W-1i,6, …}
となる。
orの関係は岩田[2022]の主張で、
W(Pi)={W-1i,1, or
W-1i,2, or W-1i,3, or W-1i,4, or W-1i,5,
or W-1i,6, …}
となる。
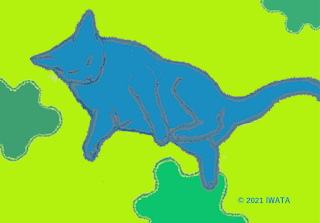

コメント
コメントを投稿