注目
【新しい地代論2】本質的に不均質な生産条件(本源的自然力タイプ1)における差額地代と絶対地代の新たな方法(3月11日修正)
変容論的アプローチによる地代論の前提
再生産されない生産条件である本質的自然力には2つのタイプがある。土地のように特定の有体物とは不可分で、かつ本質的に不均質なタイプ1と、知識と生産技術のように無体の要素が多数の有体物に均質に広がり、異なる知識の間には非連続的な差異を考えることができるタイプ2である。以前の記事で書いたように、タイプ2の方が従来の原理論の地代論の適用が容易である。逆に従来の地代論が対象としてたタイプ1の方は従来の原理論では扱いづらい。そこで今回はタイプ1を検討する。
今回の前提は「本源的自然力である生産条件は無限に不均質だ」ということである。現実には複数の異なる生産性の土地が同じ等級に分けられ、等級間には非連続的な差異がつけられるかもしれない。しかしここでは原理論で取りうる変容として2つのタイプを抽象的に取り出し、現実はその中間という方法をとる。
日高説を中心とする先行研究の前提
差額地代における調整的な生産条件
しかし、この①【同じランクの土地が多数ある】と②【異なるランクの土地とは非連続的に差がある】という前提は、土地のように本質的に不均質な生産条件では成立が難しい。「同じランクの土地」とは、第1次資本投下における同一性だけでなく、あらゆる追加の資本投下で同一になる必要もある。そのようにすべての追加の資本投下まで完全に同一でなければ、差額地代第2形態(以下DR2)において、多数存在する土地の中の或る一つのランクの土地の第n次資本投下が最劣等として調整的な生産性になる、という言い方はできない。
なお、この記事では「土地のような生産場面そのものの生産性」と、「その生産場面における追加の資本投下分についての生産性」の区別が紛らわしいので、土地のような生産場面そのものを「生産条件」といい、その生産条件における追加の資本投下の進展による生産量の変化は「生産性」と名前を区別する。ただし以下の文章では後者も「生産条件」とよんでいる場合もある。
以上のように考えれば、DR2として調整的な生産性になる場合は、様々な土地で、様々な次数の資本投下で同じ生産力水準になる資本投下が多数あり、それらが調整的な生産条件になり、その同じ生産条件の中には資本投下される部分と資本投下されない部分がある、と考える必要がある。
この問題を図解する。まず次のように古典的な地代表を作る。
表1
|
生産条件 |
A |
B |
C |
|
1次資本投下 |
4 |
4 |
6 |
|
2次資本投下 |
6 |
8 |
8 |
|
3次資本投下 |
8 |
13 |
11 |
以下では1次、2次…の数字を「次数」とよぶ。
この表の数字は、各資本投下で、超過利潤がなく、投下資本額の回収と平均利潤が得られる価格の水準である(以下のこの価格を「平均利潤が得られる価格」とよぶ)。別の言い方をすれば、その生産条件でのその次数の資本投下が最劣等の資本投下として調整的な生産性として市場価値になる場合の価格である。
上の表をグラフにすると次のようになる。
図1
Aのn次の追加の資本投下が調整的な生産性となる場合の価格水準をAnのように示すと、1次資本投下ではA1=B1 だが、2次資本投下ではA2<B2 としてある。これは上述の資本の追加投下の不均質性を示すためである。同様に不均質性ゆえに、資本投下の追加の過程で生産性が逆転することもあるだろう。これはB1<C1 だが、B3>C3 として示している。
この図では、価格8で3つの生産性で、平均利潤が得られる価格が同じとなるようにしてある。つまりA3 = B2 = C2である。これは偶然ではなく、資本投下の追加を連続的にすれば、A3 = B2 = C2のようになることは多数ありうる。連続的な曲線にする前段階として資本投下の追加単位を小さくしてみると(追加の資本投下の単位を1/10単位で補間すると)次の図になる。
図2
図3
ただし実は、連続的にせず、離散的に段階的な形でも、多数の生産条件と多数の追加の資本投下を考えれば、同じ生産性の資本投下は多数、生じる。そのため、連続的にする必要もないし、微分可能にする必要もない。
なお図3はBasu[2022] の方法をヒントにしている。ただし、この記事の方法はBasuそのものとは異なる。Basuの方法はそのうち説明する。
ここで念のために、あらためて横軸と縦軸を確認する。横軸は「それぞれの土地区画における累積投下資本量」、縦軸は「それぞれの土地区画においてその累積投下資本量での資本の追加投下分で平均利潤が得られる価格」である。
市場価値が価格8のとき、それぞれのグラフの赤い水平線上にあるのが調整的な生産性となる。従来の地代論の数値例では市場価値が価格8のときにAが3次資本投下まで、BとCが二次資本投下まで追加されるとは必ずしも想定されていなかった。そのため、一つの生産条件の一つの追加資本投下だけが調整的な生産条件のようになっていた。しかしA3 = B2 = C2とすれば複数の異なる生産条件をまたいで調整的な生産性が現れることがわかる。資本投下の追加単位を微小にすれば、このような調整的な生産性は、資本の追加投下分として、多くの異なる生産条件(土地)にまたがって多数、存在することがわかる。
しかしこの説明は、ミクロ経済学の、すべての生産主体での限界費用が市場価格と等しくなる、ということを適用しているだけに見えるかもしれない。ミクロ経済学の場合はすべての生産主体がそれぞれ今まで通りの生産部門で一斉に微小に生産量を変動させる。しかしマルクス経済学原理論では、とくに行動論的アプローチで考えれば、個別資本は最大限の利潤を追求し、かつ部門間移動ができることを前提に、超過利潤が得られるうちは同じ生産部門で資本の追加投下を続けるが、平均利潤しか得られない調整的な生産性の直前にまで至ると、同じ部門で資本投下を追加するとは限らない。その条件で生産可能な資本のうち或る部分は追加の資本投下で生産を増やし、残りの部分は追加の資本投下をしない。そこで追加投下をしない理由は、追加分を他の部門に資本移動することもあるかもしれないし、そもそも資本が足りないかもしれない。ここで追加の資本の額が非連続的だと考えれば理解は容易だが、この非連続性には異論があるかもしれない。
差額地代第2形態(DR2)の説明
ここで話を戻して、これまで3つだった生産条件を多数に増やしてみると次のようになる。
図4
これは個別の土地区画での資本の追加投下の累積による生産性の変化を示している。右下の方の曲線では生産性が高く、左上の方の曲線では生産性が低い。この線が無数にあると曲線の間が塗りつぶされて次のようになる。
図5
ここでたとえば市場価値20だとすると
図6
これはDR2になる。最劣等の生産条件(図6では生産条件H )は価格20であれば1次資本投下で平均利潤がちょうど得られる左上の端点で、これが調整的と考えればDR1である。しかし弾力的に伸縮可能という日高の主張を活かせば、調整しているのは生産条件Hではなく、優等な生産条件で価格20に並んだ無数の資本の追加投下の条件である。その意味ではこれらはすべてDR2である。
つまりDR1は、㋐優等な生産条件ではすべての資本が、最劣等の生産条件の1次資本投下よりも優等な条件でしか追加の資本投下はしない、という特別な制約と、かつ㋑1次資本投下で最劣等となる同一の生産性が多数ある、という条件があって初めて成立する。これらの㋐と㋑はこれまで述べてきたように、㋐は平均利潤を得られる追加的な資本投下の可能性は否定できない、㋑は土地のように本質的に不均質な生産条件では成立しがたい。そう考えると、本質的に不均質な本源的自然力タイプ1の考察においては、DR1の意義は、地代を論理的に考える場合に思考上の最初のステップとして、まずはどの生産条件にも同じ量だけの資本が投下される、として差額地代をわかりやすく示す、ということになるだろう。
絶対地代(AR)の説明
ARの成立に必要な条件の一つである、生産条件における非連続的な格差は、ミクロ経済学の滑らかな供給曲線の発想に基づいて否定されることが多い(飯島[2016]、新沢嘉芽統・華山謙(1976)「地代の一般理論」(『地価と土地政策 第二版』所収など))。他方で、ミクロ経済学を補完する新制度学派的な発想から借地農業者の取引コストの必要から、最劣等の生産条件の所有者はDRとは異なる最低限の地代としてARを要求できるという主張もある(Evans[1991]、[1999b]、馬渡[1995]など。この最低限の価格は reservation price、留保価格ともよばれる)。その方向性もあるかもしれないが、ここでは最近の原理論の「在庫に満ちた市場」「内在的価値」から考えてみる。そうすると、すぐに売れない商品が在庫として市場にとどまるのが常態であるのと同様に、最劣等の生産条件も借り手がいない状態がある程度、続いてもかまわない。賃貸借を一定期間の利用権という商品の売買の市場だと考えれば、通常の商品市場と同じである。そのため、最劣等の生産条件の所有者は借り手が見つかるまで地代を下げ続ける必要はなく、何らかの地代が得られるまではその生産条件を貸さない、と考えるだけでも、とりあえずARの存在は説明できる。
次にARをこれまでの図に重ねて図解してみる。
図7
下の図でオレンジ部分をDR2と書いたが、この領域がすべてDR2というわけではなく、図4のような個別の生産条件の曲線の左上の領域がDR2である。
左上の端点は生産条件Hの1次の資本投下だが、現在の原理論の説明では、ここでタダでは生産条件(土地)を貸さない、となると、その生産条件を使わなければ生産できない商品の市場価値が上昇してARが発生する、と言ってきた。しかしこれまでARを否定する批判者が何度も言っているように、資本投下の追加額や生産性が連続的に変化するのであれば、左上の端点の土地所有者が少しでもARを要求すると、同じ水平線上にある優等な生産条件で資本が追加で投下されるので、最劣等の生産条件は利用されず、その所有者もARを得ることはできない。
しかしHよりもやや生産性の高い(つまりHよりもやや下の)生産条件Eでは、その所有者がARを要求したうえで貸し出されることができる。たとえば、生産条件Eで超過利潤が図7のようであれば、この生産条件を借りた資本ではその生産条件の曲線よりも左上の部分が超過利潤となり、地代として払うことができる。この超過利潤は優等な生産条件の追加の資本投下が調整的な生産条件になっているので本来はDR2である。しかし、そのDR2が、生産条件Eの所有者が要求する地代(AR)の額に達しなければ利用できないという意味でARといえる。つまり、市場価格が15から20の間だと、生産条件Eでは超過利潤が生じるが、所有者の要求するARの額には足りないので、土地は賃貸借されず、利用されない。この「利用を排除する」という論理がARの核心である。要求されるARが実際に支払われる場合の内実としてはDR2だが、排除の論理としてはARとなる。
ところで、ARの額が同じで、市場価値も同じでも、AR = DR2(超過利潤)となる生産条件は複数ある。
図8
それぞれの生産条件の曲線と価格20とy軸で囲まれた部分がいずれも同じ面積になるように作図した。生産条件の保有者すべてが外生的に要求するARをこの面積だとすると、それぞれの生産条件は価格20のとき、曲線線の右(右上)端まで資本投下を追加すれば、要求されたARに等しい超過利潤を得ることができ、ARを支払うことができる。市場価値がこれよりも下がれば、要求されたARを支払うことができないため、その生産条件は利用されない。生産条件の所有者がARを要求することで生産条件に利用できないものが現れるという意味でこれはARである。市場価値が20よりも高くなれば、生産条件E~GではAR以上の超過利潤を得ることになり、契約更改で地代に吸収される。この地代は、優等地での資本の追加投下が調整的な生産条件になっているという意味でDR2である。この時点でARはすべてDR2に変わる。
ここで市場価値が20から25に上がると、生産条件E~GではAR以上の超過利潤としてDR2が発生する。
図9
ARはあくまでも、超過利潤がその水準以上にならなければその生産条件は利用されない、という排除の条件なので、AR=超過利潤となる生産条件のみで問題となるからである。これは日高の論理、ARは最劣地の生産条件の所有者がその土地を利用させないことで、同ランクの他の土地所有者によるARの取得が可能になる、という考えと整合的である。
生産価格体系との関係(本源的自然力タイプ1)
多数の生産条件が本質的に不均質ということが、投入要素のベクトルの構成比がすべて異なり、しかも同じ生産条件でも資本の追加投下量の違いによっても構成比が異なるのであれば、生産価格の方程式は不可能だ。社会的な需給を一致させる最後の追加資本投下の生産性が価格を規定することになり、同じ生産性での伸縮という調整的な生産条件の概念がなくなる。
しかしここで、土地が純粋に豊度の違いだけをもたらすと考え、投入ベクトルは同じで生産量だけが異なる、という想定をすると理解は容易になる。投入要素A1, A2, A3 … An から地代を必要とする生産物Anを生産する。各投入要素の単位当たりの価格がPA1, PA", PA3 … PAn、生産物Anを生産するための各投入要素の係数がa1n, a2n, a3n, …ann だとすると、まず図6の調整的な生産性での資本投下は次の式になる。
(a1nPA1 +
a2nPA2 + a3nPA3 + … + annPAn )
(1 + R ) =
優等な生産の資本投下では生産量が多いので、q倍の生産量になるとする、DR2の額をDR2と表記すると、優等な生産性の資本投下は次の式になる。
(a1nPA1 + a2nPA2 + a3nPA3 + … + annPAn ) (1 + R ) + DR2 = qPAn ……(2)
生産価格体系との関係では式(1)だけが計算に含まれるのでDRは関係ない。DR2は、(1)を含めた生産価格方程式体系で算出された価格ベクトルと、優等な生産性の資本投下で生産されたqからDR2は差額として産出される。
ARについては、本源的自然力タイプ1では、最劣等の調整的な生産条件は優等地の追加資本投下なので、ARとも関係がない。ARの額は劣等でまだ賃貸しされていない生産条件の所有者たちが外生的に欲求するものなので、価格方程式の体系で内生的に導出されるものではない。
他方、タイプ2ではARで市場価格が持ち上がるのでARを考慮する必要が生じる。後の記事で示す。
Heinz D. Kurz [1978] Rent Theory in a Multisectoral Model も参照。
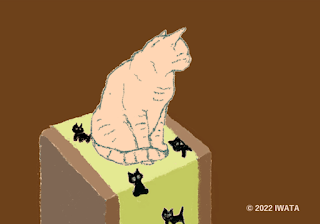










コメント
コメントを投稿