注目
板谷氏の修士論文「学説史にみる信用貨幣:戦後日本のマルクス信用論に関する一考察」
修士論文「学説史にみる信用貨幣:戦後日本のマルクス信用論に関する一考察」
論文要旨はこちら。
論文本文はこちら
PDFは、印刷可、コピー不可になっています。
コメント
1.論文の構成
本論文の根本的なテーマは金本位制停止後の貨幣の本質と流通の根拠の解明である。ただし、これは経済学の中でも困難なテーマであり、多くの議論がされてきた問題である。そのため本論文では第二次世界大戦後の日本のマルクス経済学での信用貨幣を巡る諸説の文献研究によって、問題の解明を試みている。
第1章 分析の方法
論文の構成としてはまず第1章で分析の方法を説明している。この分析の方法が本論文の特徴であり、様々な議論を一貫して分析するための導きの糸となる。
その方法とは信用貨幣を分析するためのA、B、Cの「三つの軸」の設定である。
まずAの軸は、信用貨幣の「信用」の意味をめぐるもので、①信用貨幣とは「発行者の銀行が本来の貨幣を支払う債務を信用貨幣の保有者が信用する」という理解と、もう一つ、②「銀行が与信の際に受信者の債務支払いを信用する」という意味がある。①が通説だが、学説史では②の方が信用貨幣の理解を深めるのに重要な役割を果たしてきた。
次にBの軸は、信用貨幣の説明に含まれる「債務」とは何を履行するのか、ということで、㋐上記のA①と同様の立場から「発行者である銀行が本来の貨幣を支払うという債務」という理解と、もう一つ㋑「信用貨幣の保有者が、発行者の銀行に対する債務を信用貨幣の引渡しで弁済できる」という理解である。㋐が通説だが、学説史では㋑の方が信用貨幣とその還流についての理解に重要な役割を果たしてきた。
最後にCの軸として信用貨幣の発行態様、あるいは発行の根拠の問題である。ⓐ「商業手形のような単名の債務でもそれが流通すれば信用貨幣といえる」という理解と、ⓑ「他者への債権を裏付けとした銀行の債務が信用貨幣となる」という理解がある。形式的にはⓐもありえそうだが、学説史ではⓑの方が信用関係の社会的連鎖としての信用貨幣の意義を明確にするのに役立ってきた。
第2章「不換銀行券論争」(1956~1960年代)
金本位制停止が日本国内では不可逆的に定着したばかりの時代に、不換銀行券の本質を巡る論争が起きた。多くの論者が、不換銀行券は政府の強制通用力にのみ依拠する国家紙幣、とみなす中で、岡橋保は不換銀行券も信用貨幣だ、と論じて論争になった。本論文では主要な論説を適切に要約し、第1章の3つの観点からの総括をしている。
第3章 山口信用論と内生的貨幣供給理論(1960年代~2000年代)
金本位制が完全に過去のものとなった時代の議論である。期間は1960年代~2000年代と長くなっているが、主要には1980年代前後の研究を対象にしている。
本章では、まず山口重克が原理論のレベルで、信用貨幣を「将来の貨幣還流の先取り」として明確化したことの意義を論じている。次に銀行業の実務家による内生的貨幣供給理論、すなわち、与信によって発行されるものが信用貨幣という議論を説明している。
本章では最後に、第1章の三つの軸による整理と分析がされている。
内生的貨幣供給理論は、貨幣の発行・流通・消滅のプロセスを的確に説明するものだが、貨幣がそもそも何か、という点には説明には至らない。この点は、実務家は問題にしないが、理論家には大きな問題として残り、理論家の山口と、実務家の内生的貨幣供給論者の吉田との間の論争がその問題を浮き彫りにした。第3章の時代の原理論の論者では金本位制停止後の貨幣の根拠については強制通用力に依拠するものが多かった。しかし、第4章が対象とするその後の時代では金本位制停止後の信用貨幣も、金貨幣と同様に商品価値に基礎を置くことを論じるようになった。本論文はこの問題を第3章の帰結であり第4章の出発点として説明している。
第4章 信用貨幣に関する近年の研究(2000年代後半~現在)
本章は、小幡道昭による商品貨幣論の説明から始まる。“商品価値に基礎を置く貨幣には物品貨幣と信用貨幣がある、信用貨幣は商品価値が債権の形で自立化したものである”、というのが小幡の規定である。金と兌換されない不換の信用貨幣がいかにして商品価値に根拠を持つのか、という点で、その後の新しい研究が発展していくことになる。本章は2023年に至るまでの研究を調査して、議論の焦点や発展の方向性を的確に論じている。
2.論文の意義
学説史というと、個々の学者の説の紹介だったり、様々な説の列挙になったりしやすいが、本論文は、諸説の分析のために信用貨幣の定義から「3つの軸」を析出し、それを諸説の分析基準とすることで、一貫した論述が可能になっている。
また、3つの時代区分として、2章で金本位制がまだ意識されて貨幣の本質論が問題だった時代、3章で金本位制廃止が常態化され、貨幣の供給と運動論が焦点だった時代、4章で再び貨幣の根拠が焦点となり、商品価値と信用貨幣とを結ぶ機構の問題、とすることで、学説史を一望することを可能にした。
こうした方法や時代区分は信用貨幣の研究に一定の貢献を果たすといえるだろう。
ただし、本論文には限界もある。一つには「3つの軸」を中心に据えたことにより、各論者の独自の論理が捨象されてしまう面があることである。もう一つは、学説史を中心に据えていることで、筆者の独自の貨幣論が分かりにくくなっていることである。ただし、これらの点はかなり難しい問題なので、修士論文としては完全に応えることは求められないであろう。したがって修士論文としては適切である。
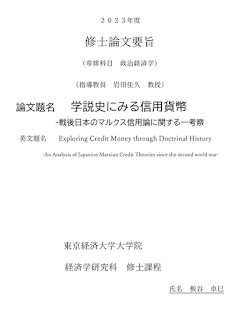

コメント
コメントを投稿