注目
FRB(アメリカ連邦準備制度)の赤字
以前の記事では中央銀行は銀行業資本の仕組みで貨幣を創出するので、適切な利潤は得ている、と論じた。次のグラフはGDPトレンド(HPフィルター、λ=100)に対する、FRB、商業銀行全体に対する利益とその差である。
FRBは比較的安定的に利益を維持し、不況でのある年には利益が増える傾向もある(ただし、年次なので不況のある年には好況末期も含む場合がある)
しかし2008-2009年のリーマンショックの危機とコロナ危機を経て、資本主義経済と中央銀行は大きく変わりつつある
かつての政策金利の誘導は、以前のようなインターバンクの短期の貨幣市場(つまり中央銀行の当座預金の貸借)だった。
しかし二つの危機と不況対策を経て、中央銀行は資産サイドで主に長期証券を大量に購入し、その見返りとして負債サイドに大量の当座預金を負うようになった。中央銀行の当座預金に大量の超過準備が堆積すると、政策金利の誘導は中央銀行の当座預金の預金利子率の変更によることが多くなる。そのため中央銀行は政策金利を引き上げると、中央銀行の準備預金への金利支払いが増える。
そこでFRBの四半期の決算をもとに2011年からの利子収入、利子費用、利潤などをまとめると以下のグラフになる。
四半期の決算は Federal Reserve Banks Combined Quarterly Financial Reports (Unaudited)
ただしこれには第4四半期がないので、年次の決算Annual Report of the Board of Governors of the Federal Reserve Systemから第4四半期を計算した。
中銀が大規模に資産購入する際には、安全な資産を対象にしたり、別会計にしたりして損失を避けるようにされていた。大量の資産購入の裏側で、大量の当座預金が生じてきた。
大量の超過準備は大規模な金融緩和で生じたものであり、低金利とセットになっていれば問題は少ない。大量に超過準備があれば、銀行間金利は常にゼロ金利になるので金利を引き上げるには準備預金への付利の金利を引き上げなければならない。そうすると中銀の赤字が増える。
中央銀行の大幅な赤字については、たとえば、①政府や国民の負担の増加するので問題だ、という考えや、②黒字なら政府に送金され、赤字なら政府から補填を受けるだけなので関係ない、という考えなどを聞くことがある。
しかし、ここでは資本主義経済の原理の観点から、非伝統的金融政策の帰結は、中央銀行が銀行業の仕組みでは維持できなくなるということとして考えることにしたい。
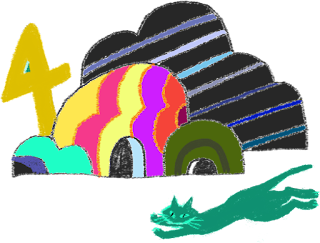



コメント
コメントを投稿