注目
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
非市場の市場化:新自由主義
非市場の市場化:新自由主義
新自由主義の一般的な特徴づけとして、とりあえず「非市場の市場化」と言える…と。以前、研究会で報告したら、「『非市場の市場化』は資本主義の発生以来の特徴だ」と指摘されたことがある。資本主義の一般的傾向としてはたしかにそうだが、しかし段階論の観点からは、19世紀末、とくに1930年代からの政府や各種団体による市場の組織化があり、非市場的な領域が大きく存在していた。これが、1980年ころからの新自由主義で組織が解体されたり、組織の内部に市場的な規律が持ち込まれたりした。この特徴が「非市場の市場化」だ。
ただし、次のような点をおさえておく必要がある
①「市場」の概念が最近の原理論(経済原論)では厳密に論じられるようになった。小幡『経済原論』の「在庫に満ちた市場」の概念は、多数の売り手が分散的な場で商品の内在的な価値を実現しようと商品を売りに出し、その価値で売れるのを待つ商品が在庫に満ちている、というものである。いつどの売り手からどれだけの商品が売れるか分からない。商品在庫の量は不断に変動する。在庫に満ちた市場はマルクスの『資本論』冒頭の「商品の巨大な集り」であり、売れるのが分からないのは「流通過程の不確定性」と言われてきたものである。或る商品に対する需要と供給が一堂に会して価格が変動するという市場とは根本的に異なる。「在庫に満ちた市場」の概念は価値論や労働市場、商業などの理論領域に広く影響する。
②「非○○」というのは「○○ではない」というものでしかなく、雑多な概念である。「非学生」とは何だろうか? 「非○○」が実際に使われている例もある。会計の「無形資産」だ。これはIntangible assetsで、「非有形資産」である。実際、「無形資産」の中身は、知的所有権や非金銭債権など雑多な寄せ集めになっている。「非市場」は具体的には、互酬、再分配、組織内の指揮命令系統、共同体内に限定された共有などを列挙するしかない。これらの内部構造に市場的な規律が取り込まれる。その例としてはアウトソーシングや準市場(介護保険など)、ふるさと納税、さらに身近なところでは、フリマアプリや民泊、ライドシェアなどがある。ここでは列挙にとどめる。
③「市場化」は政府の後退ではない。簡単に、経済における政府の大きさを示すと、次のグラフになる。
一般政府の経費支出の推移(対GDP比。%) 出所は樋口[2016]83頁参照
1980年ころから拡大傾向は止まるが、高止まりになっている。量ではなく中身の問題だ。加藤栄一の新自由主義段階の特徴づけからいえば、組織化の時代に公共部門があまりにも大きくなりすぎて、政治的な統制だけでは十分に制御できなくなったため,一定の政治的制御を残しながらも公共部門を市場化して市場の制御の下にも置くこと、となる。これは「段階論の方法における歴史と現在」229-230頁で紹介した。この例の一つが準市場である。
理論は体系であり、相互に前提し合っているため、一部だけを完結して論じるのは難しい。とりあえず今回はここまで。
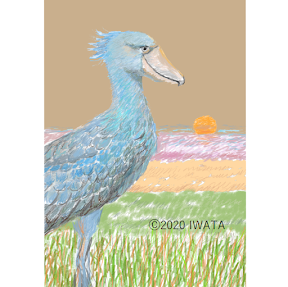


コメント
コメントを投稿