注目
信用創造と信用貨幣
信用創造と信用貨幣
原理論(経済原論)の授業の中で、学生にとって、理解が困難で、最も印象的となるのは信用創造と信用貨幣である。
最近の原理論では山口重克が定式化した説明「信用創造とは将来の貨幣還流を先取りして現在の購買力を創出すること」が使われる。最も単純な商業信用を例にとると次の図になる。
緑の部分が現在における購買力の創出で、赤い部分が将来の貨幣還流の先取りとなる。
つまりAが将来、自分の商品WAを売って貨幣を得ることを先取り(期待)して、BはAの支払い約束と引き換えに商品WBを渡す。Aは商品を買うという購買力を手に入れる。
2者間で商業信用が利用できない場合は、信用される第三者が与信と受信を媒介し、この第三者の支払い約束が転々流通すれば信用貨幣となる。これが下の図である。なお、この図ではAの商品の将来における販売を省略している。
内生的貨幣供給論の立場をとる吉田暁は「貨幣がまずあって、それが貸借されるのではなく、逆に貸借関係から貨幣が生まれてくる」と説く。
吉田説を単純化すると、次の図になる。
与信によって、銀行の負債として信用貨幣が創出される。これが信用創造における内生説である。信用貨幣の価値の裏付け、つまり現在の購買力の根拠は、将来の貨幣還流、つまり銀行の債務者が商品を販売して収益を得ることである。
原理論は内生説として信用創造を解くが、それ以外の場では信用創造は外生説で説かれる場合が多い。
外生説では、銀行の債務とは異なる「貨幣」なるものが自立的に存在し、その「貨幣」が銀行に持ち込まれて預金となる。銀行はその「貨幣」を貸し付けで借り手に引き渡す。その貨幣が銀行に戻ってくる。さらに貨幣が銀行から貸し出される、と説明する。つまり貨幣の又貸しである。
しかし、吉田暁の内生説からいえば、現在では銀行の負債としての信用貨幣の以外の貨幣は存在しない。かつては金(キン)が、それ自体自立して存在する貨幣だったが、現在は、金は貨幣ではない。では、銀行券はどうかと言えば、銀行券は中央銀行が発行する信用貨幣である。この構造についての説明は中央銀行のバランスシートを用いることが多いので多い。以下は日銀のバランスシートである(億円。2019年度9月末)
まず、中央銀行が与信することで、受信者の当座預金の数字が増える。または中央銀行が債権を買えば売り手の口座の当座預金の数字が増える。この当座預金の保有者が必要に応じて預金を銀行券に転換するという関係である。銀行券も預金も発行者の負債であることには変わりはない。
ところで、日銀の資産勘定にある「現金」は日銀の金庫にある硬貨のことである。硬貨は信用貨幣ではなく、政府が発行し、それ自体に価値のあるfiat moneyである。fiat moneyは「政府紙幣」と訳されることが多い。しかし紙でできている必要はない。fiatは「命令、法令」という意味なので、「命令貨幣」「法令貨幣」の訳語が適切である。外生説がイメージしている貨幣は、たいてい、このfiat moneyである。しかし現在のfiat moneyは少額の限定された存在でしかない。念のためだが、fiat moneyは、「法貨」とは意味が異なる。銀行券は発行者の負債であり、その裏付けに資産があるが、fiat moneyは発行者の負債ではなく、裏付けとなる資産も存在しない。「法貨」とは、流通する貨幣の中で、法的に支払い手段と規定された貨幣である。つまり、何をもって払った場合に、後で当事者がもめても、払ったことになるか、ということを法律で定めた貨幣である。(たとえば、銀行振り込みで払っても銀行が倒産したら払ったことになるのか、といった問題への対処)法律で規定されなくとも流通する貨幣はあるし、逆に法律で規定されても流通しない貨幣もある。
外生説と内生説とは貨幣をめぐって鋭い対立がある。…というよりも、たいていの場合、外生説は貨幣について考察する意思がないので対立という意識すらないが、内生説は貨幣について原理的な考察をして、外生説を批判する、という関係である。対立関係の現状については、一般には素朴な外生説の立場が多い。他方、たとえばWikipediaの「信用創造」は、内生説の立場である。吉田暁も勤めていた全国銀行協会の企画部金融調査室による『図説
わが国の銀行』では、昔々の版は外生説による説明だったが、現在の版では内生説の説明を基本としたうえで、通説的な理解として外生説も追加して説明する、折衷的な形だ。
原理論で内生説に基づいて信用貨幣を授業で説明すると、何の効果があるかと言えば、現実の貨幣が内生説による信用貨幣だから、という当然のことがある。しかし、それ以外に、貨幣による支払いの多くは結局、預金の振替になる、ということの理解が容易になる。そして電子マネー、キャッシュレス、スマホ決済といってもそのほとんどは預金の振替指示だということがわかる。この点は吉田[2002]の該当箇所を読めばわかる。また、市中の民間銀行の信用拡張と収縮による景気循環や、中央銀行の「最後の貸し手」機能も理解が容易になる。さらに根本的には、信用貨幣の価値の根拠は、信用貨幣の発行者である銀行の借り手の持つ資産や商品販売能力にあることがわかる。つまり、信用貨幣は政府の命令で価値を持つのではなく、商品価値に裏付けをもっている。図解すると次のようになる。経済主体1は銀行への債務者の集合、経済主体2は銀行の信用貨幣の保有者の集合である。
ここまでは原理論の授業の範囲だ。しかし本来の理論研究はここから始まる。原理論研究からいえば、上記の山口による説明と吉田による説明の違いである。山口では本来の貨幣を想定して、そこから信用創造や信用貨幣を説くが、吉田では本来の貨幣なるものは存在せず、与信による発行以外にない。そのため山口では、信用貨幣の「信用」とは本来の貨幣を引き渡すという発行者の約束を信用する、と意味だが、吉田の場合、信用貨幣の「信用」とは、貸借という信用関係、つまり後で払ってくれるという信用によって発行される貨幣となる。実際の両者には論争がある。吉田[2008]注3
原理論の観点からいえば、吉田の理論は「貨幣論なき信用貨幣論」となる。
振り返ってみれば、マルクスは金こそが貨幣という立場であり、その後のマルクス経済学では、金兌換停止後の貨幣は内在的な価値の根拠を失い、政府紙幣になり、インフレが必然化する、と説く傾向が強かった。しかし古くは岡橋保や川合一郎のように「兌換停止となっても銀行券は信用貨幣」と説く論者もいた。その後、山口や吉田の説明のような、信用論の発達があり、「貨幣論」を不要とする信用貨幣論が発展してきた。「貨幣論なき信用貨幣論」は信用論の発展の副産物ともいえる。
しかし原理論では「貨幣論なき信用貨幣論」で安住することはできない。最近では、貨幣論レベルで信用貨幣論を説く試みがある。その始まりはおそらく小幡『経済原論』で、そこでは「商品価値が債権のかたちで自立化した貨幣を信用貨幣とよぶ」と説かれる。
また価値形態論で単一の商品が貨幣となる、と説くのではなく、複数の商品セット貨幣として説く試みもある。江原[2018] さくら原論研究会『これからの経済原論』
この価値形態論は最近の原理論研究のホットなテーマである。
続きは後ほど。
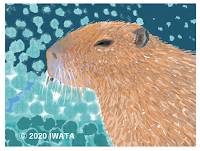






コメント
コメントを投稿