注目
価値形態論を記号で表現する
価値形態論では価値表現の等式を並べて表現するのが普通だ。
たとえば、
価値表現は、左側の相対的価値形態に置かれた商品の価値の大きさを、右側の等価形態に置かれた商品の価値を表現するので、20ヤールや4kgといった数量の表現は不可欠である。しかし間接交換のように交換の順序だけを表現した場合には 矢印で済むこともある。
リンネル所有者:リンネル → 茶 → 上衣 (小幡『原論』38頁)
記号の定義
ここで記号表現として、リンネルの所有者を
P(リンネル)
と表記する、と定義する。Pはpossessor、あるいはpersonをイメージするとよい。そしてリンネル所有者が欲する商品を
W-1(P(リンネル))
と表現すると定義する。W はWareをイメージするとよい。W-1の「-1」は、所有の反対の意味、とする。ただし、非所有一般ではなく、所有を意識した非所有、つまり主体が所有しようと欲する商品、ということである。英語のwantは「欲する」と「欠けている」の両方の意味があることを思えば納得しやすい。逆にW(P)は、主体Pが所有する商品を表現すると定義する。つまり、
W(P(リンネル))=リンネル
である。ただしこの式はトートロジーに近い。「近い」と言って、トートロジーだとは断定しないのは、Wは単数とは限らない、と定義することも可能だからだ。つまり、リンネル所有者はリンネル以外の商品も所有していることは否定されない。同様に、P(リンネル)も複数の主体がいと、定義することもできる。価値形態論の最初の出発点、相対的価値形態の商品所有者は一人だが、等価形態に置かれる商品の所有者は複数いてもかまわない。
間接交換を目的から出発点に向かう方向で記号表現する
小幡『原論』に即して、リンネル所有者が、茶を間接交換の手段として上衣を入手しようとしている場合、以下のように表現できる。
W-1(P(W-1(P(W-1(P(リンネル))))))=リンネル
この式を順番にかみ砕いていく。通常の数式と同様にカッコの内側から解いていく。
P(リンネル) :リンネル所有者
W-1(P(リンネル)) :リンネルの所有者が欲する商品〔上衣〕:
P(W-1(P(リンネル))) :リンネルの所有者が欲する商品の所有者〔上衣の所有者〕
W-1(P(W-1(P(リンネル)))) :リンネルの所有者が欲する商品の所有者が欲する商品〔茶〕
P(W -1(P(W-1(P(リンネル))))) :リンネルの所有者が欲する商品の所有者が欲する商品の所有者〔茶の所有者〕:
W-1(P(W-1(P(W-1(P(リンネル)))))) :リンネルの所有者が欲する商品の所有者が欲する商品の所有者が欲する商品〔リンネル〕
ここで
W-1(P(W-1(P(W-1(P(リンネル)))))) = リンネル
となれば間接交換が可能となる。
この表現に利点があるとすれば、間接交換の手段となる茶の表現
W-1(P(W-1(P(リンネル))))
が、リンネルや上衣、そしてリンネル所有者の欲求と、上衣所有者の欲求を含むことを示していることだ。つまり、茶は単独に置かれた商品としての茶ではなく、他の商品や商品所有者との連関に置かれた商品である、と示すことができる。
もう一つ、利点があるとすれば、W-1やPは単数である必要なく、集合として考えることができるので、表現が一般化されることだ。
難点としては、数量を示すことはできない。しかし、このことは最初に述べた。
上で説明した方法は、小幡『原論』の間接交換の例
リンネル所有者:リンネル → 茶 → 上衣
を表す、としたが、少し違っている。「リンネル → 茶 → 上衣」は、交換によってリンネル所有者の手元の商品が入れ替わっていくことを示しているが、上の記号表現の例は、複数の商品所有者における欲求の方向を順番に追っていることを示す。つまり欲求の方向に順じた順序で、「リンネル、上衣、茶、リンネル」となる。欲求の方向は以下の通り。
間接交換を自分の商品から目的へ向けて記号表現する
次に「リンネル → 茶 → 上衣」の方向でたどってみる。この場合、「-1」の記号を、W-1ではなく、P-1にする必要がある。
P-1(リンネル)
は、リンネルを欲する主体を表現すると定義する。ここでの「-1」はW-1のときと同様、非所有者一般ではなく、所有を意識した非所有、つまり所有しようと欲する主体、ということである。今度はリンネルから出発して上衣に達するもので、欲求の方向としては逆抜きに辿る。先の場合と同じように式を書けば、
P-1(リンネル) :リンネルを欲する人〔 〕
W(P-1(リンネル)) :リンネルを欲する人が所有する商品〔茶〕
P-1(W(P-1(リンネル))) :リンネルを欲する人が所有する商品を欲する人〔 〕
W(P-1(W(P-1(リンネル)))) :リンネルを欲する人が所有する商品を欲する人が所有する商品〔上衣〕
このように逆抜きにたどると、方向がはっきりしない〔 〕が現れる。つまり、ある商品を欲する人がどういう商品を所有する人かわからない。市場では誰もが商品所有者としてしか存在しえないので、何を所有しているかわからない主体は存在そのものが未規定で、曖昧である。
記号表現を他に応用する
記号表現をさらに進めると以下のような宇野の一般的等価物の導出も(これは過去の記事のもの)
と集合表現して、
となるAのうち、kが大きいAが一般的等価物になる、といえる。
また、間接交換の手段となりうる商品を表現する以下の図についても(これも先に挙げた、同じ記事のもの)
Xは、W(P-1(リンネル))
と表現され、Yは、
W-1(P(W-1(P(リンネル))))
と表現されるので、間接交換の手段となる商品集合は、
W(P-1(リンネル))⋂ W-1(P(W-1(P(リンネル))))
と表現できる。
以上は、これまでの価値形態論の説明の内容を変えるものではなく、表現の一般化である。ただし、数量を表現しないなど、表現を犠牲にした部分もある。こうした犠牲は一般に、記号表現には避けられない。それでもメリットがあるのは、簡潔に示されることと、間接交換の手段に用いられる商品は、他の商品や商品所有者との連鎖の中に置かれていることがわかることである。
他の使い道や、数量の表現方法などは今後、考えてみたい。
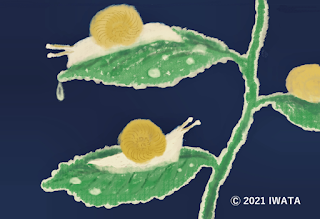






コメント
コメントを投稿