注目
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
「商品貨幣論の再構成」ガイド:発展編
基礎編を前提に、報告資料を読んでわかりづらそうなところを解説した。私の解説が誤っている可能性もあるで、自分で報告資料をしっかり読んでほしい。
スライド5~7:
この「現代資本主義の特徴」は通説なのか、報告者の積極的な主張なのかがわかりづらい。事前研究会では通説であって報告者の積極的な主張ではないと言われていたと思うが、このスライド7ではそのことはわからない。
不純化には二本の矢印があり帝国主義とグローバリズムに別々に入っていく。不純化には二つの形態があるのか?「帝国主義」も「グローバリズム」もともに不純化しているが、金本位制停止は「グローバリズム」だけである。
とりあえず、細かく見るよりも、現在資本主義は「不純化」しており、その重要な特徴は金本位制停止(金貨幣の廃止)と考えておこう。
スライド7:
この図も通説なのか報告者の積極的な主張なのかがわかりづらい。
スライド8:
「マルクス貨幣論」とはマルクスが実際に書いている「貨幣論」であって、その後、宇野弘蔵をはじめマルクス経済学が発展させていったものを指すのではない。
スライド10:
「貨幣認識」とは貨幣に物神性なども含めて理解する人もありうるので意味が広すぎる。ここはマルクスの「価値形態論」あるいは「貨幣生成論」、あるいは貨幣生成から貨幣の本質を説く、とかいうような意味で理解する。
スライド12:
強調されているが「どの商品にでも」と、金は「価値表現の材料」という2つの異質な規定があることに着目する。「どの商品にでも」は小幡『経済原論』44頁の「貨幣性」を思い出す。
スライド13:
意味が分からない暗号のようなスライド。
スライド14:
スライド12の二つの着目点の延長として考える。
スライド15:
商品と財との区別に着目する。
スライド16:
「受容される」のは誰に?と思うが、原理論研究者は貨幣論を独自に研究することなく「貨幣=金」という考えを引き継ぎ、信用論研究者は「貨幣=金」という理解を受容せず疑問を持った、ということのようだ。
スライド20:
「兌換停止の制度化・無期化」は重大な問題だが、詳しい説明がない。もしそうだとすると、物品貨幣と、兌換のない信用貨幣を連続的に取らえることになり、貨幣の「変容論的アプローチ」と矛盾をきたす。
「国家独占資本主義以降の体制の歴史的役割」これは通説なのか? 報告者の主張なのか? 現代の宇野理論の延長線で見れば、通説となるが、スライドだけでは不明である。
スライド21:
ここで引用される山口説は、信用貨幣は銀行の債務だが、その債務の支払い能力は金のような兌換準備金ではなく、銀行が保有する債権の円滑な返済、だという説。ここは重要なので押さえてく。
それはいいが、下の解説部分の「信⽤貨幣の研究が進み、【★】不換制度が⻑期に安定するようになると」【★】の前後の関係が不明。解説の中の「商品貨幣」の定義が、山口の理解か、小幡のような現代の宇野理論の理解か、報告者の独自のものかわからないし、報告者による定義もまだない。
スライド22:
基礎編参照
スライド23:
報告者の意図とは違うかもしれないが、金本位制と管理通貨制度の違いを挙げておく。信用貨幣の基礎はあくまでの債権であって金は補足的にしか存在していない。兌換制において兌換の義務が自然消滅するわけではない。
スライド24:
スライド22の銀行券と紙幣との違いに注意。
「国家紙幣論に理論的な根拠を与える。」とは、金貨幣を基礎に考えることが、不換銀行券=不換紙幣という説の理論的な根拠を与える、ということを言っているようだ。
スライド25:
ここで言う「信用貨幣論」は一般的な意味での、「信用貨幣についての論」ではなく、特定の貨幣観に基づいた基づいた一つの特定の学説を指す。この報告では吉田暁の説を指しているが、一般にはシュムペーターの分類に基づいて貨幣の信用理論「貨幣の信用理論credittheoryofmoney」と呼ばれる説のことである。その説明は授業資料 「現代資本主義論II第7回信用貨幣の基本」にある
スライド26:
「金債務」というタイトルは紛らわしいが、吉田[2008]は「貨幣とは兌換銀行券のような金債務だ」と言っているのではなく、全く逆で、吉田は「貨幣は金債務」という説を強く批判している。
念のため、「信用貨幣=金債務」という主張を報告者がしているわけではない。
スライド28:
「資本主義の異質化」のタイトルも紛らわしい。吉田が「資本主義の異質化」を主張しているのではなく、逆である。吉田は“金本位制を前提に理論を作り、金本位制がなくなるという「資本主義の異質化」として管理通貨制を説く”という「資本主義の異質化」論を強く批判している。そして、金本位制と管理通貨制を区別するのではなく、金に依拠することなく、銀行による信用貨幣システムから理論を作るべき、と論じている。
念のため、「資本主義の異質化」という方法論を報告者が主張しているわけではない。
スライド29:
このスライドも意味が分かりにくい。吉田の主張は“信用貨幣が貨幣の請求権だとすると、信用貨幣とは別に「ほんらいの貨幣」が存在することになるが、「ほんらいの貨幣」は存在しない”という主張をしている。スライド27の第3文もそう書いてある。論点は信用貨幣の他に「ほんらいの貨幣」が存在するか否かである。報告者が同じように論点を立てるなら、山口の主張は不要であろう。
スライド30~31:
二つのスライドが同じタイトルになっているので、31は30の続きであろう。
ところで、吉田の説は金本位停止の時代にのみ通用する特殊な貨幣理論を提唱しているのではなく、金本位制が停止されていても通用しうる信用貨幣論を提唱している。たとえば吉田[2002]『決済システムと銀行・中央銀行』には次のような節がある。
「兌換銀行券の流通根拠は兌換にあったのであろうか。流通根拠が兌換であったという点を強調すれば、不換銀行のそれは、法貨制にしか求められないことになる。しかし法貨であると強制しても激しいインフレに悩まさられれば、現実には流通し得なくなったり、ドラリゼーションでさえ起こりうる。不換化しても運営よろしきを得れば支障なく流通するということから逆に考えれば、兌換銀行券の時代でも、兌換は銀行券の信認を高めるために必要だったことは確かだが、真の流通根拠は銀行券の発行の態様にあった … つまり、経済取引のなかの信用関係がまずあって、銀行券にしろ預金通貨にしろ、その信用関係を代位するという形で信用貨幣が発行される。いい方を変えれば、再生産過程に根差した貨幣の発行還流こそが、真の流通根拠」(吉田[2002]78)
スライド32:
基礎編参照
スライド34:
このスライドの「商品価値ベースの信用貨幣」説と「返済還流ベースの信用貨幣」説との違いは何だろうか。
「債権債務関係の中で信用貨幣が創造される」は「返済還流ベースの信用貨幣」説と同じだが、次に「返済還流、商品販売の確実性」とあるので、信用貨幣の発行の資産に、金融資産に限らず、商品も含めたより広い資産構成になっていることが違いのようだ。
「不換銀行券制度」は「返済還流ベースの信用貨幣」説でもありうる。というよりもそもそも、スライド19の「返済還流ベースの信用貨幣」説の資産に「金」がある必然性がない。
※この後のスライドは基礎編と同じなので、触れない。
吉田説、不換銀行券と不換紙幣との違いについて岡橋説などは以下の記事も参照。
銀行の貸借対照表に現れる信用貨幣:外生的貨幣説、内生的貨幣説、商品貨幣説
Theories of credit money in Japanese Marxian economics: 2 Okahashi in Banknote controversy
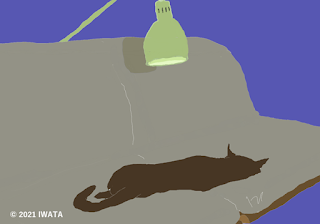



コメント
コメントを投稿