注目
新・orの関係の商品集積体から信用貨幣を導出する新しい価値形態論(その1)
はじめに
マルクスの『資本論』や,宇野弘蔵の『経済原論』は金貨幣の存在を前提にしていた。しかし,金本位制が停止された現在,貨幣をどのように捉えるのかは重要な問題である。現代の貨幣には価値はなく,政府の命令だけで流通する政府紙幣(fiat money:命令貨幣)になった,あるいはそもそも資本主義ではなくなったといった議論もある。
他方,信用論の世界では,現代の貨幣は銀行の与信によって発行される預金通貨の形をとった信用貨幣論である,という考えが有力である。また,経済学原理論でも最近,現代の貨幣も商品の価値に基づくという意味で商品貨幣としたうえで,金貨幣を経ることなく,価値形態論で信用貨幣を導出する方法が議論されている。これらの議論からは,マルクスや宇野とは異なる前提や論理展開が必要なことがわかる。本稿ではこうした先端的な議論を引き継いで,商品集積体の価値に基づく信用貨幣を価値形態論で導出するための新たな方法を提起する。
まず,全体像が見通せるように商品価値に基づく信用貨幣を例解しておく。地方の生産者が大きな商品市場のある都市の商人に商品を送り,その代金となるべき価値を商人が負う債務の形で保有する。その後,生産者が商人を通じてその都市の市場から商品を買う場合,その債権で支払うことができる。このとき商人に対する債権が商品価値に基づく信用貨幣になる。その条件はまず生産者の商品が他者に欲求され販売できるかどうかを,商人が調査し適切に判断することであり,さらに多数の商人によって構成される豊富で発達した商品市場と,債権・債務の振替を行う決済システムの存在である。
(略)
A.信用論における信用貨幣論の発展とその限界
A.1 信用論における信用貨幣論の発展
(略)
A.2 貸借対照表に現れる信用貨幣
信用貨幣が貸借関係で発生するものならば,それは図1のように貸借対照表に現れる。
図表1 貸借対照表に現れる信用貨幣
図1の読み方には外生的貨幣説,内生的貨幣説,商品貨幣説の3通りがありうる。
第1に外生的貨幣説では,もともと金貨幣のような,銀行とは別個に外生的に発生した「本来の貨幣」があって,その貨幣を保有する経済主体2がその貨幣を銀行に預け,銀行がその貨幣を経済主体1に貸し出して引き渡し,経済主体1が商品の購入でその貨幣を支払う。その結果,その貨幣はどこかに出ていき,図1の状態になる。図1は右側から読み,外生的な貨幣が持ち手を転換しながら債権と債務の連鎖をつくる。しかしこの説では「本来の貨幣」の発生を説明できない。
第2に吉田のような内生的貨幣説では,まず真ん中の銀行で与信債権と預金通貨(銀行にとっては預金債務)が同時にできるとみる。外生的貨幣や商品価値を前提にしないという点で「無からex nihiloの信用創造」となる。また,経済主体1からの受信需要に基づき,銀行システムの内部で自立的に貨幣が発生するという点で内生的となる。与信しただけの段階では預金通貨は受信者である経済主体1の資産にある。その後,経済主体1が経済主体2から商品を買って預金通貨で支払えば図1の状態になる。図1は真ん中の銀行から読む。この見方は実際の銀行による信用貨幣の創造を説明するが,銀行の債務がなぜ貨幣となるのかは説明できない。ここが「貨幣論なき信用貨幣論」になる。
3番目の見方は商品貨幣説で,資産の商品価値が銀行を通じて貨幣に転換される,とみる。外生的貨幣説と内生的貨幣説とは異なり,商品貨幣説では実際の取引を想定せず静態的に,貨幣の論理的な発生論としてみる必要がある。ここでは,左からみる場合と右からみる場合がある。
まず右から読む場合,信用貨幣の価値の根拠を商品の価値にまでさかのぼる。つまり,預金通貨の形である貨幣の価値の根拠は預金通貨を発行する銀行の債権の健全性であり,その債権の健全性は最終的に債務者である経済主体1の資産の商品価値に基づく将来の貨幣獲得の可能性にある。その考え方は山口の説明と整合的だが,説明自体が最初に貨幣の存在を前提としていることを否定できない。
左から読むと商品価値の貨幣への転換がわかる。まず,経済主体1の下にあるさまざまな商品は特定の使用価値によって価値実現が制約されており,すぐに交換されるわけではない。そこで,銀行はその商品の販売可能性を調査したうえで,その商品の価値を基に,使用価値の特殊性に制約されない貨幣を預金通貨として創出する。商品の価値を根拠に貨幣が発生するという点では,価値形態論と同じ構図になる。
以上,外生的貨幣説,内生的貨幣説は,実際の取引を想定して理解することが容易だ。しかし,外生的貨幣説では「本来の貨幣」の発生が説明できない。内生的貨幣説も,なぜ銀行の預金通貨が貨幣としての価値や購買力を持つのか説明できない。他方,商品貨幣説では右から読む場合は説明の最初から貨幣が存在する。貨幣を導出できるのは左から読む商品貨幣説だが,これは現実の取引から説明できるものではなく,原理論における抽象的な価値形態論で説く必要がある。ここに困難がある。この商品貨幣論を説こうとする小幡『原論』やさくら『原論』での試みを以下,検討する。
B.価値形態論で信用貨幣を説く説の検討
B.1 債権化の方向と商品集積体の方向
これらの試みには,第1に,貨幣になるのは商品の現物ではなく債権という債権化の方向と,第2に,単一種ではなく複数種の商品の価値に基づくという商品集積体の方向がある。以下,これらの論考を検討して信用貨幣を導出する価値形態論を探る。
B.1.1 債権化としての信用貨幣
債権化の方向として小幡『原論』は,信用貨幣を「商品価値は金銭債権の形で外化し,自立化することもある。商品価値が債権の形で自立化した貨幣を信用貨幣と呼ぶ」(小幡『原論』:47頁)と定義する。この信用貨幣も,商品の交換可能性としての価値を基礎に持つ点で,商品貨幣の一種だとする。つまり商品の価値に基づく商品貨幣には,現物そのものが貨幣になる物品貨幣と,債権の形になった信用貨幣がある(同48頁の図)。
ただ,現物ではなく債権,というのでは,しょせん信用貨幣は物品貨幣の兌換の約束でしかない,という批判を免れない。貨幣のない世界での債権・債務は,特定の商品の給付に対する債権・債務である。しかし,債権に記された給付対象が単一種の商品ではなく,多数の商品種の集積体であれば,債権が価値の自立化に近づく。
B.1.2 商品集積体に対する信用貨幣
小幡[2006]では第2の方向がある。つまり,多数の種類の商品が集積され,その価値が合成されることである(小幡[2006]:30 頁)。その例解として,信用貨幣が債務証書であることを前提に,商品券とその引換対象の商品集積体との関係,あるいは商人の債務と商人が在庫として保有する商品集積体との関係を挙げる。具体的には,たとえば10ポンドの茶といった単一種商品の引き渡しという簡単な債務から,引渡対象が複数の商品種となる債務へと展開して{10ポンドの茶,または20エレのリンネル,または1着の上衣…}といった合成的な債務証書になると,信用貨幣の価値に安定性がもたらされ,商品流通における信用貨幣の流通が可能になる,と論じる。「または」とあるように,債務証書に記された諸商品はいずれか1つというorの関係である。
小幡によれば,商品の合成によって債務証書の価値が安定になり,「さらに銀行券のような本格的な信用貨幣への発展は,直接的な諸商品の集合から,多数の債権を基礎にした債務に間接化し,その背後に種々の商品の価値を取りこむことで,複合性をさらに高次化させる」(同頁)。商品集積体を裏付けに持つ商品券型信用貨幣の発行者は図1でいえば,経済主体1と銀行(信用貨幣の発行者)を未分化に包括した存在になる。原理論体系の展開によって,商人のような商品集積体と銀行が分化すれば,本格的な信用貨幣へ発展する。
しかし,ここでの目的は、信用貨幣の価値が,特定の商品への兌換なしでも安定化しうることを示すことなので,価値形態論との関係は説かれておらず,債務証書を形成する動機も述べられていない。
そこで,この「商品券」のような信用貨幣を価値形態として表現してみる。まず,債権発行者(つまり債務者)が次のように債権を定義である。
債務証書1単位 := {次の商品からいずれかを受け取る。|10ポンドの茶,1着の上衣,砂糖3kg...} ……①
次に商品◆◆の所有者がこの債務証書で価値表現すると次の式になる。
商品◆◆の△△単位 = 債務証書○○単位 ……②
商品◆◆の所有者が価値表現をする動機は,債務証書内の商品を欲することだろう。そのうえで,債務証書の所有者にとって,価値の下落した商品との交換を回避できるという点では,単一種の商品の交換の約束よりも価値が安定する可能性もあろう。
B.2 さくら『原論』の価値形態論について
さくら『原論』の価値形態論の特徴は,第1に複数種の商品セットが現れること,第2に「交換を求める形態」と「評価を求める形態」が交替して進み,その中で価値表現式の左右が逆転するように見えることである。
以下,商品のセットが現れる部分だけ取り出してその論理を追う(さくら『原論』21-29頁)。なお,B’やAは主体の表記として同書に書かれている記号である。
まず,2頭の豚を欲する商品所有者B’が,自分の複数種の商品をセットにして「交換を求める形態」の価値表現を次のように行う。「→」は交換を求める意味である。
B’:(鉄0.5kg, 砂糖15kg) → 2頭の豚 ………③
ここでB’が複数種の商品セットをつくる積極的な理由はなく,単種でなければならない理由はないというだけである(同27頁)。なお,この手法の基になったと思われる江原[2018]は,B’の手元にある商品は単種では量が不足するので,複数種の商品を集めて価値表現する,と説く(:59頁)。
次に,B’はこの(鉄0.5kg, 砂糖15kg)というセットの商品の価値量を引き渡す約束の証券を発行し,これをεと名付ける。商品セット全体の価値量を安定的に維持するために,B’は商品セットの構成を組み替えることができる。
証券1ε := (鉄0.5kg, 砂糖15kg)の価値量 ………④
これは価値表現ではなくB’が設定する定義式である。
B’は,今度は式③の価値表現をこの証券を用いて次のように行う。
B’:証券1ε → 2頭の豚 ………⑤
他の主体Aは自分の商品の価値の「評価を求める形態」として,価値量の安定する証券εを用いて価値表現を行うことができる。小麦90㎏を保有するAがその価値の大きさをεで表現するとたとえば次の式になる。
A:小麦90kg = 証券8ε ………⑥
さくら『原論』によれば,さらに多くの主体がこの証券で価値表現を行えば,この証券が一般的等価物となり,一般的等価物として固定すれば貨幣となる。そして商品セットは現物ではなく,証券εという形で価値を自立化させて流通させることができる。こうしたεのような証券は,より発達した市場組織の下では銀行業資本が発行する(さくら『原論』:28頁)。同書には信用貨幣という語はないが,これが信用貨幣の基礎になる。
以下,この方法の特徴について考察する。
第1の特徴は,式③と式⑤の「→」で表記される「交換を求める形態」と,式⑥の「=」で表記される「評価を求める形態」を区別し,両者が入れ替わって進むことである。従来は,たとえば宇野の方法では「交換を求める形態」だけであり,等価形態に置かれる商品は,相対的価値形態の商品の所有者の直接的な欲求の対象でなければならなかった。そのため,価値形態論の中で信用貨幣を説くことが困難だった。しかし,さくら『原論』では「評価を求める形態」を挿入することで,直接的な欲求の対象とはならない証券εを等価形態に置くことが可能になっている。
第2の特徴は,式⑤と式⑥では,証券εについて,左右両辺が逆転しているようにみえることである。もちろん,価値表現が左右逆転できないことは現代の原理論の基本である。ただし,ここでよくみると,式⑤はB’が価値表現し,式⑥はAが価値表現している。価値表現を行う主体が入れ替われば,同じ商品も相対的価値形態と等価形態との位置が「逆転」することは当然ありうる。
第3の特徴は,「価値量」として何を引き渡すかが不明なことである。引き渡すものを商品の現物ではなく「価値量」とすることで,発行者がセット内の商品の種類と量の変更の調整が可能になり,そうすることで,価値量の安定化を図ることができる。
そうなると,B’はεの価値量の安定化のために,自分が所有していない商品種も商品セットに入れることもできる。また,多数の種類の商品がこのεのセットに入ればε自体の価値の大きさは計算できなくなる。そのためεが価値表現の素材として用いられ,貨幣として信認されていれば,商品セットの中身は伏せられ,「1εは1ε」とのみ認識される。しかし,εや発行者のB’への信認が揺らげば,B’の保有する資産が問題とされるだろう。
これら3つの特徴から2つの方向を考えることができる。
第1の方向は,εの履行を保証するために,B’の下に商品の現物,あるいは商品価値を体現する何らかのものが大量に集積していると考えることである。しかしさくら『原論』ではそうはなっていない。B’が商品セットを作る動機がB’自身の保有商品の不足だったら,履行の保証は困難だろう。さくら『原論』では「主体が欲するのが商品の使用価値ではなく価値である場合,商品としてのモノそのものを流通させる必要はないのである。したがって商品に内在する価値を商品体とともに流通させることも,商品に自立化したかたちで流通させることもできる」(さくら『原論』:28頁)として商品の現物の保有は必要ないとしているのだろう。しかし特定の使用価値の制約のない「価値量」そのものが現れていれば,それはすでに貨幣が成立しているので,貨幣を導出する価値形態論としては成立してない。いずれにしても,どういう形であれ,証券εが信用されるためにはB’の管理下に価値物が大量に存在していることは必要だろう。
第2の方向は,εはあくまで「評価を求める形態」で等価形態に置かれるだけであり,「交換を求める形態」では等価形態に置かれることはない,と考えることである。交換が求められなければε発行者は債務の履行を求められることもない。しかしそうするとB’自身には商品セットや証券εを形成したり価値を安定化させたりする動機がない。おそらく,さくら『原論』では銀行業資本まで説明を繰り延べているつもりだろう。
価値形態論の段階で,証券発行の動機と,発行者の下での何らかの形で商品の集積を論じる必要があるだろう。
次に,「交換を求める形態」と「評価を求める形態」の区別の意味を明確にするために,その区別の観点からマルクスの方法と,それに対する宇野による批判を確認する。
B.3 価値形態における「評価を求める形態」と「交換を求める形態」
B.3.1 マルクスの「評価を求める形態」
(略)
B.3.2 宇野の「交換を求める形態」
宇野はマルクスを批判して,相対的価値形態の商品の所有者による「交換を求める形態」一本で進んでいく方法をとった。つまり,欲求の対象となる商品種を複数挙げれば展開された価値形態になる。そして多くの商品所有者から共通して等価形態に置かれる商品種が一般的等価物となる。こうして,価値表現の左右を転換することなく一般的等価物を導き出す。
交換の量を決める順序では,先に,等価形態に置かれる上衣の1着という特定の量があり,それとの「交換を求める形態」としてリンネル所有者が所有しているリンネルの中からその一部の20ヤールという量を選んで価値表現する(宇野『原論』全書版:23頁注1)。この順序は,マルクスの方法や「評価を求める形態」とは逆である。ここでは,リンネル所有者の下には20ヤールのリンネルの他に,相対的価値形態に置かれていないリンネルが存在することが前提になっている。
ここで「交換を求める形態」に現れる商品と商品所有者を一般化して簡潔に記号で表現する。まずリンネルをW1とし,W1の所有者をP(W1)と表記する。Pはpossessorと思えばイメージしやすい。Pは単数としてもよいが,複数と考えれば一般的な表現になる。
次にW1所有者が欲して等価形態に置く商品をW-1∘P(W1)と表現する。「∘」は合成関数を意味する。W-1(P(W1))と表現してもよい。いずれにしても右から順に読んでいく。この表記方法は一見,奇異に見えるかもしれないが,見慣れると便利である。
WはWareと思えばイメージしやすい。W-1の「-1」は所有の反対の意味である。ただし,非所有一般ではなく,所有を意識した非所有,つまり主体が所有しようと欲する商品である。英語のwantは「欲する」と「欠けている」の両方の意味があることを思えばイメージしやすい。W-1∘P(W1)は複数であり,展開された価値形態になっている。
次に,商品にはW1,W2,W3,…Wn があるとし,それぞれの商品所有者が欲する商品の共通集合を次のように示す。
宇野の方法では,この商品集合Aのうち,空集合にならずにKの数が最も大きいAKに含まれる商品は,他の商品所有者から直接的な欲求の対象としてだけではなく,間接的な交換の手段としても欲求される。その中の1つが,他のあらゆる商品から価値表現の対象とされる一般的等価物になる。
しかし,この宇野の方法の難点は,一般的等価物になりうる商品は,他の多くの商品所有者から使用価値の面で欲求される必要があることである。そのため,基本的に物品貨幣しか導出できない。あるいは信用貨幣としてはせいぜい,物品貨幣を「本来の貨幣」としそれとの交換を義務付けられた兌換信用貨幣しか導出できず,信用貨幣の観点からは外生的貨幣説と同じになる。
B.3.3 小幡『原論』の価値形態論における「間接交換」
小幡『原論』は大きくは宇野の方法を引き継ぐが,展開された価値形態に違いがある。宇野の場合,欲求の対象として多くの商品が並べられて展開された価値形態になるが,小幡では間接交換の手段が多く並べられて展開された価値形態になる。
手順として,まずリンネル所有者が上衣を欲するが,上衣所有者がリンネルを欲しない場合,リンネル所有者はどの商品であれば上衣所有者に欲せられ交換されるかを調査し,その商品を交換で入手できれば,その商品を用いて続いて上衣を交換で入手できる。その商品はリンネル所有者にとって間接交換の手段となる。リンネル所有者にとって間接交換の手段となる商品の使用価値は何でもいいので,間接交換の手段が多数,並べられると,リンネルの価値量が展開された価値形態で表現される。
なお,そもそも商品は「他人のための使用価値」なので,商品所有者は自分の商品が交換を求められるかを調査する必要があるが,ここでリンネル所有者は,他者がリンネル以外のどの商品を欲求して交換に応じるか,という調査をしている。
一般化するため間接交換を記号表記する。まずリンネルをW1とした場合,W1を欲する主体をP-1(W1)と表記する。P-1の「-1」は所有の反対の意味である。ただし,非所有一般ではなく,所有を意識した非所有,つまりその商品を所有しようと欲する主体である。P-1(W1)が所有する商品をW∘P-1(W1)とする。このP-1やWは単数でも複数でもかまわない。
そして,W1の所有者が欲する商品の所有者はP∘W-1∘P(W1),その所有者が欲する商品はW-1∘P∘W-1∘P(W1)と表記される。
上記の記号表現は欲求の対象となる商品の種類を示すことができるが,量を示すことはできない。表記を工夫すれば量も表現できるが,今回の考察には意義が乏しいのでこれ以上の表記の複雑化は行わない。
間接交換の手段となりうるのは,以下の共通集合となる。
W∘P-1(W1)⋂ W-1∘P∘W-1∘P(W1)……⑨
記号で表現すると,間接交換の手段となるのは茶だけではなく,複数種の商品から成る集合であることを一般化できる。
また記号表現することで,間接交換の手段となる商品は,たとえば式⑨の右側W-1∘P∘W-1∘P(W1)のように,他の商品所有者が持つ商品への欲求を背景に持つことが明示できる。つまり,1つの商品は他者との関係が切断された単独の商品としてあるのではなく,複数の商品所有者による欲求の連鎖の中にあり,その欲求の連鎖こそが一般的等価物,さらには貨幣を導出することがわかる。
B.3.4 間接交換における2つの価値表現
小幡『原論』では明示されていないが,「間接交換」は2つの価値表現から成ることをこの項で明らかにする。
まず,間接交換の前に,以下の「簡単な価値形態」がある。
リンネル20ヤール = 1着の上衣 ……⑩
ここで上衣の所有者がリンネルを欲しない場合,間接交換における1つ目の価値表現は次の形になる。
リンネル20ヤール = 茶4kg ……⑪
リンネル所有者は茶の使用価値を欲するわけではないが,どの商品が上衣所有者に欲求されるかを調査し,交換の手段として茶を欲する。そのため式⑪の価値表現を行う。
次に,「リンネルの価値量に基づく茶4kg」と「1着の上衣」との等値の表現となるが,どちらの商品が相対的価値形態で,どちらが等価形態だろうか? 小幡『原論』にはこの先は書かれていないが,次のように考えるべきであろう。
茶がリンネル所有者に選ばれたのは,茶が上衣所有者の欲求の対象となっているからなので,上衣所有者の欲求の契機を捨象せずに残せば,2つ目の価値表現は上衣の所有者が茶を欲するという形で次の式になる。
上衣1着 = 茶4kg ……⑫
間接交換は,上記の式⑪と,この式⑫の2つの価値表現から成る。式⑪はリンネル所有者が自分で行う価値表現,式⑫は「上衣所有者が⑫の価値表現をするであろう」とリンネル所有者が見込んでいる価値表現である。両者はいずれもリンネルの所有者の主観で組み立てられた価値表現の体系である。ただし,ここで主観と言っても単なる願望ではなく,上衣所有者の欲する商品についてのリンネル所有者による調査に基づいており,客観的状況を一定程度,踏まえたものである。式⑫の量の関係もリンネル所有者の主観である。茶4kgはリンネル所有者が1着の上衣を欲するためにその量になっているので,上衣所有者の欲する茶の量が4kgとは限らない。
間接交換の2つ目の式⑫は一見,簡単な価値表現のように見えるが,リンネル所有者の観点から記号表現すると,W-1∘P(W1)=
W-1∘P∘W-1∘P(W1)となる。この右辺の項は,内部にW-1が2つあることで分かるように,リンネル所有者,上衣所有の欲求を二重に含む。
この2つの価値表現では,茶はいずれも等価形態に置かれる。しかし,簡単な価値形態の式⑩と,間接交換の価値形態の2つ目の式⑫を比べると,上衣の位置が左右逆転することがわかる。つまり,簡単な価値形態の式⑩では,上衣はリンネル所有者によって等価形態に置かれるが,間接交換の2番目の価値表現式⑫ではリンネル所有者の主観での「上衣所有者が茶に対して価値表現する」ことで上衣は相対的価値形態になる。
こうしてリンネル所有者の主観の世界では,もともと等価形態にあった上衣は等価形態から排除されて,相対的価値形態になり,他方,茶は等価形態の位置に残り続ける。こうした排除が他の商品にも続けて起きれば茶が一般的等価物になる。
ただし,小幡『原論』の「間接交換」の記述では間接交換の1つ目の式(⑪)で終わり,2つ目の式(⑫)がないので左右の逆転がわからない。しかし,小幡[2018]の信用貨幣の説明では2つ目の式だけがある。
B.3.5 小幡[2018]の信用貨幣論と「間接交換」
小幡[2018]の信用貨幣による価値表現の部分はいくつか補足すると次のようになる。17頁の図2の「信用貨幣型」では,まず第1の行為として,主体Aが,自分の所有する商品WAの商品体を引き渡す債務と引き換えに,主体Cから商品WCの商品体(WC・körperと表記)を受け取る債務を得る。このWCの債務の価値の大きさはWAの価値(WA・wertと表記)に相当する。こうしてWAの価値を持つWC商品体という「商品融合」(WA・wert+WC・körperと表記)が生じる。次に第2の行為として主体Bが,自分の所有する商品WBの価値の大きさをWCの債務の量で表現する。式で表せば次の形になる。
WB = WCの債務((WA・wert)+WC・körper) ……⑬
著者はこの説明の困難さを自認しており,「受信のための与信」を「補助線」にし,Cを媒介にしたAとBの間の信用取引で例解しようとする。しかし,その補助線は第3者の媒介を理解するのにはよいかもしれないが,価値形態論から離れる。必要なことは信用論と価値形態論との論理的な接続である。それは間接交換の手段に債務が用いられると考えれば容易に理解できる。
まず小幡『原論』の間接交換と対応させるとWAがリンネル,WBが上衣,WCが茶に相当する。B.3.4項で説明したように,間接交換では,まずはAはWBを欲するが直接交換ができないので,1つ目の価値表現としてWCの受取債権を等価形態に置く。次に2つ目の価値表現としてBがWCの受取債権を等価形態に置く。簡単な価値形態でも間接交換でもAが主体となってWBを得ようとする構造である。しかし,この論文(小幡[2018]17頁の図)では,B.3.4項の式⑫に相当する2つ目の価値表現だけが示されている。そこで,B.3.4項の2つの価値表現に沿って組み立て直す。
まず,最初の「簡単な価値形態」はAを主体に考えて次の式になる。
WA = WB ……⑭
次に,直接交換ができない場合に,間接交換のための1つ目の式(B.3.4の式⑪に相当)はWAとWCの「商品融合」の中に埋もれている。明示すると次の式になる。
WA = WCの債務 ……⑮
2つ目の式(B.3.4の⑫式に相当)は上記⑬式で,再掲すると,
WB = WCの債務((WA・wert)+WC・körper) ……⑬
これは間接交換(B.3.4)で論じた2つ目の価値表現の式⑫に相当する。なお,式⑫を式⑬のように表現すれば次の形になる。
上衣1着 = リンネル20ヤールの価値を化体した4kgの茶
つまり,最初の簡単な価値形態では⑭だったのが,間接交換では1つ目の価値表現が⑮,2つ目が式⑬になる。式⑭と式⑬を比べるとWBの位置の左右逆転がわかる。
つまり,もともとAはWBを欲して式⑮の価値表現を行うが,直接交換ができないので,式⑭と式⑬から成る間接交換を構想する。そこではまず式⑭のように「商品融合」を起こし,新しくWCの債務(WA・wert+WC・körper)をつくる。その目的は,Bが価値表現の主体となって式⑬のように価値表現するようにさせることだ。
こうしてWBは最初の「簡単な価値形態」のときに置かれていた等価形態の位置から排除され,相対的価値形態に移る。他方,WCはいずれの価値表現でも等価形態に置かれ,WC自身の価値の大きさは表現されない。
B.4 先行研究の検討の小括
マルクスの価値形態論は貨幣が存在しない状態で,或る特定の量の特定の商品の価値を表現するために無数の商品を列挙することになった(B.3.1)。他方,宇野は商品所有者の欲求を導入して「交換を求める形態」に純化し,1つの商品が貨幣となることを容易に説いた。しかしこれは基本的に物品貨幣しか導出されない(B.3.2)。
これに対して,小幡『原論』は間接交換の手段となる商品の登場とその債権化を示したが,間接交換の手段が単一種の商品になっており,それの引渡債権であればやはり兌換信用貨幣でしかないという困難が残る(B.1.1)。他方,小幡[2006]は多数の商品がorの形で並んだ商品券型の信用貨幣によって,その困難を回避する方向を示した。しかしそこでは価値の安定だけを論じており,価値形態の関係が不明である(B.1.2)。
他方,さくら『原論』は,従来は単一種の商品ごとにしか登場しなかった価値形態論にandの関係で結びついた複数種の商品セットを持ち込んで,信用貨幣と,単一種の特定の商品とのリンクを切断した。また,「交換を求める形態」とは区別された「評価を求める形態」を明示することで,直接的な使用価値の不要な商品が等価形態に置かれる論理を可能にした。しかしこの「評価を求める形態」への特化は,「交換を求める形態」を失い,貨幣として流通する論理を失ってしまう(B.2)。
最後に小幡[2018]は,整合的に理解されるなら,もともと簡単な価値形態で等価形態に置かれていた商品が等価形態から排除され,等価形態に一般的等価物が導出される論理があった(B.3.5)。しかし間接交換を構成するはずの2つの式のうち2つ目の式しかなく,全体像が示されていない。また,小幡『原論』と同じく,単一種の商品の債権という問題は残っていた。
以上の先行研究の検討を踏まえて,次回の記事で新しい価値形態論を説明する。
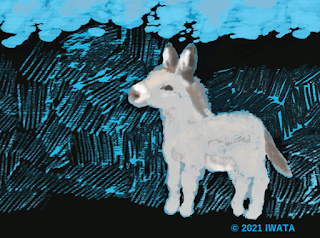



コメント
コメントを投稿