注目
利潤を追求する資本としての中央銀行
先日、研究会で中央銀行は利潤を追求する資本といえるかどうかが話題になった。そうでないとすれば中央銀行は公的な機関という説に論拠が増し、さらにエスカレートすると政府と統合勘定になってMMTへと話を繋げる人もいる。しかし中央銀行は与信や国債などの証券を買う場合に元利払いを前提として預金という信用貨幣を創出するので、中郷銀行は銀行の仕組みであることは間違いない。
与信を行うために自分の債務を流通させるのが銀行の業務
銀行が利潤を得るのは貸出利子によってである。しかし銀行の業務は貸出によって利潤を得ることだけでなく、その際に自分の債務を流通させることである。ここが単なる金貸しとは異なる。産業資本が自分の生産物の品質を確かなものにして自分の商品の流通を促進するのと同じように、銀行業資本は貨幣となる自分の債務の品質を維持して自分の債務の流通を促進する。自分の創出した信用貨幣の健全性とは銀行の資産サイドでは裏付け資産の健全性であり、さらに銀行の負債サイドでは預金の振替など貨幣取引が円滑に行われることである。銀行が資本ならば利潤率を最大化しようとする。
その時の研究会では銀行の利率は次のように示された。
利潤率=貸出利子率×貸出債権-流通費用- 貸倒引当金 ①
しかし正確には以下の式である。
利潤率=(貸出利子率×貸出債権-預金利子率×預金債務額)-流通費用- 貸倒引当金 ②
①または②の銀行の利潤率が産業資本の一般的利潤率をイコールになる。産業資本の一般的利潤率が与えられていれば利子率の水準が決まる、というのが小幡氏の主張だった(小幡『経済原論』238-239頁)。しかしこの式は利鞘しか示さない。利鞘しか分からないことを開き直れば①の式でよい。しかし銀行の業務が自分の債務を流通させることだとすれば、預金利子率は省略してはならない。ここで流通とは自分の債務を持ってもらうことだ。例えば最近の先進資本主義国の中央銀行の当座預金が膨大な量に増えたのは中銀当座預金におけるプラスの付利が契機となった。
中央銀行の利潤
中央銀行の業務は、資産サイドでは一つには再割引といわれるように与信業務を行う市中の銀行などの金融機関に対して与信を行うことである。これは最初の与信の銀行がしっかりと与信先を審査しているので、そのしっかりとした銀行に対してさらに審査をして与信する中央銀行の資産はさらに健全となる。もう一つは国債や外貨準備、金のような安全資産である。
中央銀行はこうした資産からの利子が低くても、その健全性ゆえに預金利子率を低くしたまま自分の債務の流通を増やすことができる。
また、金融危機に際して、最後の貸し手を行うことでも利潤を得る。最後の貸し手の理解はいろいろあるかもしれないが、基本的には、流動性危機が収まれば健全になるはずの銀行に、罰則的な高利率で与信をする。危機が収まれば与信が元利払いされて高い利潤が得られる。利潤率の最大化には利潤率計算上の期間の長短の問題があり、この長さは一意には決まらない。利潤率計算上の期間として景気循環の周期を超える長さを採用すれば、平時には低い利潤であっても、信用貨幣の流通の広さを確保していれば、危機に際して高い利潤を得る。
中央銀行は競争するかどうか
資本であれば他の資本と競争するだろう。ここで競争は二種類に分けて考えることができる。一つは異業種間の競争である。これは例えば産業資本と商業資本の間で買取価格の高低をめぐって競争がある。同様に中央銀行と市中銀行の間では中銀からの与信の利子率や中銀の当座預金の利子率の高低を巡って競争がありうる。この競争は容易に理解できる。
ここで研究会では、「中央銀行が国債を大量に購入して長期金利を大幅に押し下げると市中銀行の貸出金利が下落して市中銀行の利潤率が大幅に下がる、という競争があるのではないのか」という意見が出た。しかしこれは競争というよりも利害対立ではないか。
中央銀行が有利な与信先や債券を市中銀行と奪い合っていればたしかに競争になる。実際、19世紀のイングランド銀行やフランス銀行は、現代的な中央銀行になりきっておらず、市中銀行とこの種の競争をしている、と非難されたこともあった。しかし、現在、長期金利の引き下げで起きていることは、中央銀行が市中銀行から大量に国債を買って、市中銀行は中央銀行に大量の準備預金を持つ、という関係である。このように中央銀行が「銀行の銀行」であるというのは市中銀行が準備預金を中央銀行に持つ、ということである。この意味では有利な与信先や債券をめぐる競争というよりも、準備預金というシステムの在り方における利害対立のようにみえる。
しかしもっと理解しがたいのは、中央銀行における同種の資本の間での競争だ。つまり商業資本同士の競争の競争や銀行業資本同士の競争のように、中央銀行間での競争があるかどうかだ。この点では、異なる通貨単位を発行する中央銀行同士が貨幣価値の安定をめぐって競争することを仮想するハイエクの「貨幣の脱国家化」denationalization of money が有名だ。しかし同一単位の貨幣だけで考えると、階層的な銀行間組織で上位の銀行が単一の中央銀行か、競争的な複数の銀行か、ということになる。
19世紀前半のフリーバンキングの議論は、イングランド銀行やフランス銀行という政府と癒着して特権的に首都(決済中心地)で階層的な銀行システムの単一の上位銀行となった銀行に対し、同列に上位に位置する競争的な銀行を首都に作るべきかどうか、という論争だった。中央銀行単一論は、階層的銀行システムの最上位では競争がないことで信用貨幣システムが安定化できると論じる。逆に複数の競争的銀行論は、競争があることで最上位の複数の銀行は、与信業務などで銀行として健全性といった規律が保たれる、と論じる。ここで上位の銀行同士の競争とは直接には、互いに相手に対してもつ預金債権の支払請求をして、互いの準備預金をぎりぎりまで減少させるということだ。こうして過剰な与信を抑制できる、という主張だった。
原理論における銀行間組織の変容
現在の宇野派の原理論では、一般の銀行が準備を置く上位の銀行は一つに絞られるか複数になるかわからない、というのが通説である。原理論の高いレベルの抽象度では、ここは理論的にどちらの可能性もあって歴史的な要因がそこに入り込んで特定のかたちをとる開口部、あるいは二つの可能性があるという意味で変容のポイントとなる。しかし今のところ、宇野派の原理論の研究者は、原理論では一つに決まらない、とは言っても、暗に中央銀行を前提として。階層の上位に複数の銀行が競争的に存在する銀行間組織の複数のタイプを論じようとしている人はいない。
価値形態論における信用貨幣論の発展と、貨幣内生論者との論争点
他方で、現在の宇野派では、兌換のない信用貨幣論を価値形態論で説く研究が高度に発展している。しかしここではややこしいのは、流通論という場所に制約されて、銀行間組織を捨象して銀行が単一であるかのように説くことで、理論的な発展を図っていることだ。そして、信用貨幣の価値の根拠は、信用貨幣の発行元の銀行の裏付け資産の商品価値にある、と主張する。もちろんここでは中央銀行のような階層的な銀行システムは捨象されている。
他方、現実の信用貨幣制度を見る貨幣内生論者は、最後は支払請求のない中央銀行券の法貨としての性質が貨幣流通の最深の根拠だ、という。そして裏付け資産の確実性というのは、それが確実であるかどうかの確証のない「ぼんやりしたもの」に見える。逆に宇野派は中央銀行券の価値の根拠は中央銀行の保有資産だ、と反論する。
宇野派の原理論としては、具体的な銀行機構を流通論で論じるわけにはいかない、と言って批判をかわすが、では、機構論の銀行信用のところで、複数の上位銀行の可能性まで含めて銀行間組織を論じているかといえば今のところそうではない。
ただ両者のすり合わせの一致点の可能性はある。宇野派の原理論では価値形態論の物品貨幣の導出で、商品所有者間の行為だけで 一般的等価物が一つに決まるわけではなく、何らかの外部の力が必要になる(小幡『経済原論』40、47頁など)というのが一般的な理解である。健全な債権を根拠に信用貨幣として自分の債務を流通させる銀行はたくさんあるが、「この銀行の債務は最終的な支払いであって、それ以上の支払い請求ができない」ということが外部の力によって決められる論理を受け入れることはさほど困難ではないだろう。
参考 岩田佳久「商品集積体と債権化から信用貨幣を導出する新しい価値形態論:orの関係で結びついた商品集積体を基礎として」
岩田佳久『世界資本主義の景気循環 : クレマン・ジュグラーの景気循環論とクズネツ循環 』第1章 または「クレマン・ジュグラーと19世紀英仏マネタリーオーソドキシー」
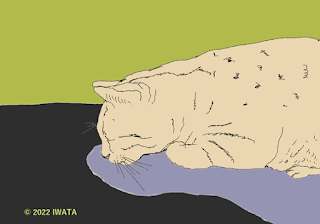

コメント
コメントを投稿