注目
バランスシートで貨幣をつくろう-2
「バランスシートで貨幣をつくろう-1」の記事の改定版
貨幣は商品価値をもとに、貨幣がない状態から、銀行による与信と預金設定によって創出される。これが内生的貨幣供給理論の核となる。内生論では 銀行(信用貨幣の発行者)の債権と債務が建てで拡大する。そのため内生論ではバランスシートで示すことが多い。 ここでバランスシートで実習してみよう。
銀行の預金通貨を用いた決済システムは 次の図のような階層的なシステムとなる。
図1 階層的な銀行預金通貨システム
ここで信用貨幣の前提として、前回の記事と同様に以下の条件を付ける。
1)非銀行経済主体が商品をもつということだけから開始。
2)貨幣は与信によって預金の形で発行される。
3)政府は中銀にだけ口座を持つ。国債は中銀が政府から直接に買ってはいけない。
以下の記号を使う
D 非銀行経済主体の預金
政府D 政府預金
CBD 中銀への当座預金
claim 債権(市中銀行と非銀行民間主体との関係、中銀と市中銀行の関係の2つがある)
Lib 債務(市中銀行と非銀行民間主体との関係、中銀と市中銀行の関係の2つがある)
B 国債
W 商品
設問ⓐ:図1の形を作る。ただし、図1では市中銀行は2つあるが、簡単にするために1つにしておく。
そうすると次のようになる。
図2
そうすると次のようになる。
図3
4行目の納税で非銀行経済主体の純資産がなくなってしまうのはかなりの重税のように見えるがこれは、利潤の捨象と、枠の大きさの固定のために誇張されているからである。
設問ⓒ:納税ではなく、まず政府が国債を発行し、それを非銀行経済主体が買う。政府はその収入でモノを買う。最終的にモノが消費されてなくなる。
これは課題にしておく。
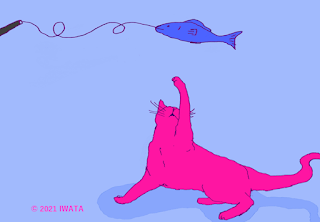




コメント
コメントを投稿