注目
貨幣内生説と「インフレ」
原理論では「景気循環」でのテーマである(たとえば小幡『経済原論』「投機活動と累積的価格上昇」266-267頁)。
まず貨幣については、貨幣の集計量の絶対額ではなく、購買をしようとしている経済主体の購買力で考える必要がある。内生論では、信用創造による信用貨幣の創出で購買力を増やすことができる。とくに好況が続くと受信資本の返済可能性が高い状態が続くので、購買力の創出の拡大が続く。その状態が過度に大きくなると、再生産不可能な生産条件に依拠した生産物では生産拡大が困難になる局面が現れる。ここでは好況は好況末期に至る。地代論で説明したように、そうした生産物では劣等な生産条件に依拠することになり、その商品の生産価格が上がる。そうするとさらなる価格上昇を見込んで、その商品を買い占める投機活動が起き、価格上昇が累積的に加速される。「価格が高くなると予算制約で買える量が減る」とはならない。ここでも信用創造によって購買力が創出され、さらに高値で買われていく。投機の対象となる商品の価格が上昇していけば、受信資本の返済は容易と判断され信用創造がさらに拡張する。ここの理解が貨幣内生論の強みとなる。
累積的に価格が上昇する商品を原材料に用いた他の商品へと価格の上昇は広がる。ここで注意しておくべきことはすべての商品価格が同程度に一斉に上がる「インフレ」はない。
市中銀行の信用創造は、他行への支払いや預金準備率の確保のために、信用創造の後で準備預金を必要とする。準備預金は市中銀行間の取引で調整されるが、総額を増やす必要がある場合は中央銀行が信用創造で創出する。その時の条件(主に金利水準)で市中銀行の信用創造をコントロールできる。中央銀行の資本としての業務は、自身の債務である信用貨幣を流通させて、与信債権からの利子で利潤を得ることだが、価格が上昇する商品が増えると、貨幣の価値が下落することになり、中央銀行は自身の債務である信用貨幣の流通が困難になる。そうなると、中央銀行の資本としての活動が大きく阻害される。実際、多くの中央銀行は最大の政策目標として「物価の安定」を挙げている。これは、自身の債務としての信用貨幣の価値を維持するということである。産業資本が自らの生産物の品質を維持しようとするのと同じように、中央銀行は自身の発行する信用貨幣の価値と流通性を維持しようとする。
信用貨幣は中央銀行の発行だけではなく、市中銀行も信用貨幣を発行し購買力を創出する。中央銀行は市中銀行の信用創造をコントロールするために、ホールセール(銀行間取引)のレベルで市中銀行の準備預金の獲得条件を厳しくする。現在では主に政策金利(準備預金を入手するための金利。中央銀行による与信や債券の購入の際の利率、銀行間の貸借の利率)の引き上げによる。それは景気を反転させ、政治的に打撃になるので中央銀行には独立性が必要になる。最近では大統領時代のトランプとFRBパウエル議長の対立が目立った。資本主義の歴史的変化の観点では、1970年代のインフレに対して、1979年秋からのボルカー議長の下でのFRBが急激な金利を引き上げて、新自由主義の時代への画期をなした。ここでは中央銀行の独立性が強調された。
物価変動の種類
物価変動についてはいくつかの種類に分ける議論がある。
①額面の変化。デノミの逆。その結果一斉に価格が上がる。
②貨幣価値自身の変化。金本位制の場合は金の価値下落。金本位停止後は、為替レートの下落による物価上昇効果。輸入品と国産品の競争の影響もあるが、同じ通貨圏から輸入品には同じ変動の効果がある。
③特定の商品の生産条件の劣等化からくる。上で述べた通り。
④命令貨幣(表券貨幣、fiat money)の信用が失われる。生産条件に基づかず、多数の商品の全面的な投機的価格上昇が起きる。
参考
カンティロン効果:貨幣残高の集計量ではなく、どの経済主体が貨幣を入手したかによって経済的な効果が異なること。集計概念に反対するハイエクなどオーストリア学派がよく用いる概念。
「準備は後から求められる」:貨幣外生論では準備預金があってそれをもとに市中銀行が貨幣貸出を行うと考えるが、内生論では逆で、市中銀行がまず信用創造によって預金通貨を創出しする。その後で、その預金に対して一定の比率の準備預金が必要となる。
吉田暁「内生的貨幣供給論と信用創造」
吉田暁「インフレ目標論について」
19世紀の通貨論争に関連しては、岩田『世界資本主義の景気循環 : クレマン・ジュグラーの景気循環論とクズネツ循環』19-20頁のトゥックの項と、55-57頁参照。
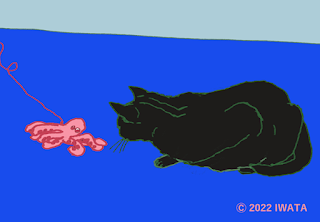



コメント
コメントを投稿