注目
変容論的アプローチの適用によって地代論を知識へ拡張する試みと、それに伴う地代論の再構成について
近年,原理論の地代論を知識の領域に拡張する試みが広がっている。しかし土地を対象につくられてきた地代論をそのまま知識に応用することはできない。地代論そのものの再構成が必要になる。この問題を本稿では以下の3点を中心に検討する。
第1に土地を本源的自然力として高度に抽象化するとともに,本源的自然力がより具体的な形に変容する2つのタイプとして考察する。つまり土地のように特定の有体物と不可分で本質的に不均質なタイプと,知識のように特定の有体物から分離可能で多数の有体物に遍在(ubiquitous)しうるタイプである。これは小幡[2009]の変容論的アプローチに基づく。小幡[2009]が地代論で変容のポイントとした絶対地代と,恒久的土地改良の主体の2点を本稿では,本源的自然力のタイプ分けと,産業資本からの本源的自然力所有者階級への分立の有無の2点として発展させる。
第2に,知識に拡張できるように宇野学派の地代論を発展させる。現在の宇野学派の地代論は大内力と日高普の説が基礎になっている。これらの説は土地を対象としているが,土地だけでなく知識も含めた本源的自然力についての基準になりうる。ただし,これらの説はもともと対象としていた土地のような本源的自然力のタイプよりも,知識などのタイプに適合的,という逆説的な関係になっている。
第3に地代論の直前にある市場価値論の特別利潤との関係を検討する。特別利潤では超過利潤の源泉である知識と産業資本が一体だが,地代論では超過利潤の源泉である土地と産業資本とは階級的に分立している。そのため,地代論の対象を知識に拡張すると,特別利潤と地代論との関係に不整合が生じる。
以下,本稿では,A節で地代論を知識に拡張しようとする先行研究を簡単に概観するとともに原理論の地代論で扱う「知識」の範囲を限定する。次にB節では知識の領域への拡張で地代に生じる変化を考察する。そのさい,これまでの宇野学派の功績と新たな難点,小幡[2009]における本源的自然力とその変容の意味を示す。続くC節では,原理論における特別利潤から地代論への論理展開において,産業資本から知識の所有者階級の分立の可能性について論じる。最後にD節でまとめとさらなる発展の展望を述べる。
Ⅰ.前提
Ⅰ.1 先行研究の概観
宇野弘蔵の方法論では,19世紀末から固定資本の巨大化で資本主義は不純化し,巨大な産業資本と銀行業資本が一体化した金融資本の下で独占利潤の発生を説く。しかし1980年代頃を画期に,ITなどの知識によって超過利得を得る企業が多くなってきた。原理論はもともと利潤率の均等化を基礎にしながら,特別利潤や地代論において超過利潤を論じる枠組みがある。こうした超過利潤を単に資本主義の不純化とするのではなく,原理論でとらえるために,地代論からの拡張がいくつか試みられている。ここで先行研究を便宜的に3つの潮流に分けて概観する。
第1に,知的所有権によって1つの商品を1つの経済主体が独占する,つまり独占地代としてとらえる諸研究である。よく参照されるZeller [2007] は,製薬産業における知識による独占地代を論じている。この方法は個別の事例を挙げるのは容易であろう。しかし,原理論の地代論は同一商品生産における複数の生産条件を基礎に地代を論じるが,独占地代はその基礎から離れて支払い能力のある需要によって地代と価格が決まる,とする。そのため,独占地代に依拠する研究潮流は地代論を正当に継承しているとは言えない。またZellerの研究は金融的の発展形態として土地を金融資産,地代を利子とみなして取り込む,とする。たとえばrent-extracting
financial capitalという表現がある(Zeller [2007]:111)。あらゆる収入が金融的に処理される「金融化」の時代の特徴を示そうとしているのだろうが,生産過程における地代の役割を軽視する点に問題がある。
第2に,マルクスの地代論として価値論を基礎に,差額地代第1形態(以下DR1と略記),差額地代第2形態(以下DR2と略記),絶対地代(以下ARと略記),独占地代という枠で知識も説明しようとする諸研究がある(Rotta and Teixeira [2019]とくにp.388)。代表的にはRottaとTeixeiraによる一連の研究がある。Teixeira and Rotta [2012]は,Zellerのような金融化の考えを批判して,金融における利子と,生産過程で知識がもたらすレント(地代)の役割をそれぞれに区別することで,地代論の知識への拡張を緻密にできる構造になっている。彼らの主張では知識は,土地と同様に,いったん得られるとコスト不要で利用できるため,再生産においては労働生産物ではなく価値物ではない。そのため,知識の所有者は知識の販売ではなく,知識を賃貸しし,知識を利用する産業資本の超過利潤から地代を得る。そして,土地と知識の違いについては,知識の所有者は能動的に知識を創出し,独占することでレントを増やそうとすることだとする(Teixeira and Rotta [2012]:464)。彼らはこうした経済主体を資本としてModern rent-bearing capitalとよぶ。しかし地代をレントとみなすなら,「地代を生む資本」という概念には矛盾がある。
Rigi [2014]も地代の種類にそくした分析をしているが,地代論を生産過程だけではなく,著作権や営業上の秘密,ブランド(商標)などの知的所有権にも拡張している。著作権などはZellerなど第1の潮流と同じく独占地代として扱っている(Rigi [2014]:923など)。しかし生産過程を基礎に作られた地代論を流通過程に適用するには第1の潮流と同様の問題がある。ARの根拠について,農業での資本構成の低さによって説明する『資本論』の方法を準拠しようとする。しかしそうすると知識が重要になる産業では資本構成が低いとは思われないので,ARは存在しないとしている(Rigi [2014]:927-928)。
この研究の潮流が示すのは,土地と農業を対象につくられた地代論をそのまま知識に適用することの困難である。
第3には,「資産化assetization」の研究である。土地の概念を知識だけでなく地代論の対象を大きく広げて,利用が制限されてその保有によって超過利潤を得ることができる様々なモノを「資産asset」として理解する。これは商品を販売するのではなく,また,金融資産の保有による利益でもなく,実体経済において作用する資産を保有し,そこからレントを得ることを目的にしてレントを生む「資産」を作り出すという意味で「資産化」となる。Birch and Muniesa[2020]では特許,データベース,バイオ医療,インフラとしての鉄道,太陽光や風,教育,小麦の種子,行動を改善できるホームレスなど,さまざまな分野における資産化を検討している。超過利潤を生む新しい技術と,将来にわたって得られる超過利潤を計算する評価valuation技術によって資産が作れられる。これは経済学だけでなく社会学や社会政策にかかわる広範囲な対象について,レントを追求する経済主体の行動でとらえる点で研究分野としては大きな可能性がある。しかし,レントを生む資産の概念を拡張しすぎて,資本の平均利潤や超過利潤の概念がない。その結果,資産それ自体が収益を生む物神性に陥っている面も多い。
第2と第3の潮流は利子とレントを混同する傾向のある金融化論や「レント資本主義」論に対して,金融的ではなく,実体経済,とくに生産過程における資産の役割から持続的にレントを取得し続ける要素を強調するところに特徴がある。
これらの3つの研究潮流の中では,第2の潮流が原理論の地代を知識の領域に拡張できる可能性が高い。
他方,宇野学派は,地代論においても『資本論』の論理的な再構成を進めてきた。詳細は後述のⅡ.1とⅢ.2.2で述べるが,たとえばARの根拠は資本構成の問題ではなく,最劣等地の所有者たちによる競争による価格引き上げとした。また原理論全体としても,流通過程の不確定性を重視し,生産過程と流通過程の区別を明確するので,地代論は生産過程に限定される。
宇野学派の中では最近,小幡[2009]が,土地を「本源的自然力」として抽象化し,その中に知識や生産技術を含める方法をとった。ただしまだ,その論述は知識も土地の範疇に加えることが中心になっており,しかも具体的な展開では主に従来の通り,土地と農業にとどまる。そのため,地代論において知識と土地との違いは積極的には論じていない。しかし一部に,土地とは異なる知識の特殊性を指摘する個所もある。それは,落流の場合に得られる地代はDRで,特許の場合に得られるのはARという区別である(小幡[2009]:205,問題132とその解説)。この観点を発展させることも可能である(後述Ⅱ.3)。
以下,本稿では,知識への地代論の適用の試みを宇野学派の地代論研究の成果に踏まえて論じる。
Ⅰ.2 対象となる知識の種類の限定
もともと地代論は第1表のように「機構論」(『資本論』第3巻に相当)の前半である「価格機構論」の最後にある。
第1表 機構論の体系
|
機構論 |
価格機構 |
費用価格と利潤 |
|
生産価格 |
||
|
市場価格(特別利潤) |
||
|
地代 |
||
|
市場機構 |
商業資本,銀行信用,株式資本 |
|
|
景気循環 |
「生産価格」では,同一商品の生産に単一の生産条件を前提とするが,「市場価値」では同一商品の生産に複数の生産条件がある場合を考察する。特に優等な生産条件を利用して超過利潤を得ればそれは特別利潤となる。ここで特別利潤とは,「生産論」(『資本論』第1巻第3篇以降に相当)の特別剰余価値が機構論で現れるものを意味する(「特別利潤」という言い方は富塚[1976]:327-328参照)。これに続いて「地代」では生産条件の優劣の格差が固定化された場合の超過利潤を扱う。
このように,地代論の対象は同一商品の複数の生産条件における優劣の格差に限定される。そして地代の種類はDRとARが中心となる。地代のもう一つの種類である独占地代は同一商品の生産に一つの生産条件しかないので,ここでの地代論の対象からは基本的に外れる。また,流通過程への作用はここでの地代論の対象にはならない。さらに,土地には住居用など最終消費向けの用途もあるが,ここでの地代論の対象は生産過程で用いられるものに限る。
従来の原理論の地代論の対象は「制限された自然力」なので,これを知識の領域に拡張すれば,制限される知識が対象となる。制限される知識として知的所有権の分類には,たとえば日本では第2表のような種類がある。
第2表 日本の知的所有権の分類
|
知的創造物についての権利 |
特許権 |
|
実用新案権 |
|
|
意匠権 |
|
|
著作権 |
|
|
回路配線利用権 |
|
|
営業秘密 |
|
|
育成者権 |
|
|
営業上の標識についての権利 |
商標権 |
|
商号 |
|
|
商品等表示 |
|
|
地理的表示 |
原理論の地代論ではこれらがすべて対象になるわけではなく,生産過程で原価のレベルで認識可能なものに限られる。上の第2表でいえば主に特許権である。他にあるとすれば回路配線利用権,営業秘密,育成者権にありうる。第2表の残りの多くは販売の促進として流通過程に作用するものなので「商業地代」の対象になる。商業地代は『資本論』第3巻第18章「商人資本の回転,価格」の最後に出てくるが,これまでは議論が進んでいない。原理論体系で論じるとすれば市場機構の商業資本になるので,本稿では取り扱わない。
Ⅱ.知識の領域への拡張による地代の変化
Ⅱ.1 日高説の功績と難点
知識の領域へ地代論を拡張するために,この項では宇野学派におけるDRとARの研究の意義をまとめる。宇野学派の地代論の代表的なものには大内[1958],日高[1962],大内[1982],日高[1983]などがあるが,ほぼ方向性は共通している。そこで本稿では最も網羅的に地代論を探求した日高[1962]を中心にして「日高説」と総称する。
Ⅱ.1.1 日高説の功績
日高説は土地を主たる生産手段とする農業を対象に論じているが,知識にも通じる考察がある。その限りにおいて日高による理論的成果を確認する。
第1に,DRの「一般allgemeinen」と「特殊」の区別である。『資本論』第38章の題はDie Differentialrente: Allgemeinesで,通常「差額地代:総論」と訳されるが,日高はこれを「一般」と解釈している(日高[1983]目次の第3篇第2章第1節1参照)。実際,『資本論』の38章第2段落の冒頭では「地代のこの形態の一般的なallgemeinen性格を明らかにするために」(Marx [1964]: 653)として落流の動力を用いた工場の例の説明を始め,38章最終段落では「こうしてわれわれは差額地代の一般的allgemeinen概念を確定したので,次に本来の農業における差額地代の考察に移る」としている(ibid.: 661)ので,日高の解釈に無理があるわけではない。
日高の解釈によればDRの「一般」とは,その商品の複数の生産条件において「制限された自然力」が不可欠な場合と,それが不可欠ではない場合をともに含むという意味で一般ということである。一般に対するものを「特殊」とよぶとすれば,特殊は「制限された自然力」が常に不可欠となる場合で,この特殊の場合が39章以降で論じられる,と日高は解釈する(日高[1962]:6)。具体的には「一般」で例示されるのが,数が制限される落流と制限されない蒸気機関が用いられる場合で,「特殊」は制限された自然力としての土地の利用が不可欠な農業の場合である(日高[1962]:6,[1983]:190)。こうして,地代論は土地を不可欠に利用する農業に限定されず,工業の領域でも、制限された自然力を含む視角を確保できる。
第2に調整的な生産条件の概念である。「調整的」とはregulierendで,『資本論』訳書では多くの場合「規制的」と訳されるが,日高[1962]が参照する青木文庫長谷部訳は「調整的」の語を当てている。ここで日高が強調しているのは,同じ生産性,つまり同じランクの土地にも多数の区画があり,それらの中には,利用されている部分と,利用されていない部分がある,ことである(日高[1962]:87,282-283)。優等なランクの生産条件は優先して利用され,その量が限られる。他方,最劣等の生産条件の中には利用されるものと利用されないものがある。需要の変動に応じた生産量の変動の必要に対しては,この最劣等の生産条件の利用度の伸縮で調整される。これが「調整的」の意味である。その前提は,優等地の利用の制限と,さしあたり最劣等地で利用制限がない,の2つである。
他方,マルクス『資本論』では個々の生産性の異なる土地区画が一つ一つ生産に利用されていくと想定され,最も劣等な区画が市場価格を規制する生産条件(土地)となっている。これに対して日高は強調して批判している(日高[1962]:421)。日高説の前提では,調整的となっている最劣等の生産条件には未利用の部分があり,さしあたりは利用制限がないという意味で,DR一般と共通する性質がある。
この日高の説明には,①同じ生産性の土地が多数ある。②異なる生産性の土地の間には非連続的な格差がある,の2点が前提になる。ここからARが説明される。
第3にARの説明である。ARは,DRの論理では地代を得られない最劣等地の所有者がタダでは土地を貸さないとして要求する地代である。マルクスの想定のようにそれぞれの区画のランクがすべて異なり1種類の区画に1人の所有者しかいなければARを要求するのは容易だ。しかし日高のように同一の生産性の土地が多数の区画に分かれて,地代を求めて多数の土地所有者が賃貸しを求めて地代の引き下げ競争をする場合にはARの獲得は困難である(日高[1962]:400)。つまり,最劣等地の所有者の一人Aが,何らかの額のARを要求しても,同ランクの最劣等地の別の所有者Bがより低いARで土地を賃貸しすれば,Aは地代を得ることができない。ここでもし最劣等地の複数の土地所有者の間に競争介入能力(同:396)があればARを得ることができる。そしてARの上限は,次に劣等な土地の生産性との差,あるいは優等地における次に劣等な追加投資の生産性との差による。しかし,この差がわずかならばARは実質的には存在できないので,ARの存在には上記の日高の想定②が必要になる。ただし日高自身は,賃貸しされていない最劣等地の土地所有者にとっては,タダよりましなので,地代引き下げ競争の結果,ARの額は極めて小さいと想定している(同:209)。
生産増加のための追加の資本投下が最劣等地ではなく,最劣等地よりも劣等な生産性で優等地に資本が追加投下され,それが新たな調整的な生産条件になれば,それまでARを要求していた最劣等地Cでは超過利潤が発生しDR2を得る。これはマルクスが明らかにした「最劣等耕地にも生じるDR」である。優等地の追加投資が始まる前には,最劣等地Cの所有者たちに競争介入能力があればARを得るが,優等地での劣等な生産性の追加投資が調整的な生産条件になれば,従来の最劣等地Cの所有者たちが得るのはDR2になる。そこでARとDR2の背反と相互転換が生じる
第4に,DR1(+AR)とのDR2の背反と相互転換である。最劣等となる調整的な生産性の投資先には2つの可能性がある。一つは最劣等地に投下される場合で,これはDR1になる。この場合,最劣等地の所有者たちの行動によってはARも生じうる。もう一つは優等地で最劣等の生産性の追加投資の場合であり,この場合は優等地にも最劣等地にもDR2が生じる。この場合,DR1はなく,最劣等地のARもない。その代わりに最劣等地も含めてすべての土地にDR2が生じている(日高[1962]: 402)。
この相互転換は次の2つの図で示される。
それぞれの場合の調整的な生産条件で生産増加の余地がなくなり,もっと劣等な生産性の投資が必要になったときに,最劣等の土地に投資が拡大するか,あるいは優等地での劣等な追加投資になるかによって,DR1(+AR)とDR2は相互に転換しうる。
Ⅱ.1.2 日高説が新たに残した難点
日高説は功績と同時に難点を残した。それは①同じランクの土地の多数性と,②異なるランクの土地の間での非連続的な格差,という,日高の功績の前提そのものである。土地が再生産されずに本質的に不均質であれば,なぜ同じ生産性の土地が多数,存在するのか? しかもこの「同じ」は1次投資だけでなく,高次の追加投資にわたって「同じ」となる必要もある。このように①は成立し難い。さらに,無限に不均質であれば,異なる生産性の格差も微小となる。そのため②も成立しない。ARについての日高の説明への反論の多くはこの②についてである(たとえば飯島[2016]:56-59,新沢・華山[2016]:395-396)。
日高もマルクスも,ともに②の想定をしたのはおそらく,本質的に不均質なはずの外的自然としての土地を,簡単な例解として地代表にするために非連続の少数の種類に絞り込んだことが原因だろう。
しかし,知識の場合は日高説の①と②が2つとも成立する。ここで知識とは先に「課題の限定」で述べたように,生産過程において原価レベルで生産性を高める特許のような知識に限る。
つまり①については同じ知識が多数の有体物に均質に遍在可能であり,同じ生産性として調整的な生産条件になりうる。②では異なる知識の間では非連続な格差がある。というのは,知識が地代に相当する使用料を得るには知的所有権による利用制限が必要であり,知的所有権が認められるのは,既存の知識との明確な格差が必要だからだ。そうすると,日高説は土地よりも知識の方が適切になる。
従来の地代表を知識の領域に拡張するために必要なことは,土地と知識を混和するのではなく,論理展開として土地について抽象度を高くして本源的自然力として論じた後,より具体的には土地のようなものと,知識のようなものへと変容する,という論理構造で説くことである。これが「変容論的アプローチ」になる。
Ⅱ.2 本源的自然力の変容
Ⅱ.2.1 小幡[2009]における本源的自然力の定義
小幡[2009]は本源的自然力を「生産に用いられるが,再生産されない生産条件」(小幡[2009]:201)と定義し,「原理的に再生産を通じて均質化することはない」「本源的自然力の不均質性」(同)と特徴づける。土地から知識への拡張については,「本源的自然力の概念は,このような(耕地や鉱山-引用者注)外的自然力に限定されない。パテント化された生産技術など,原理的には同様に考えるべき対象は,制度と権力を背景に,無形の知的領域においてもつくりだされている」(同:202)とする。さらに本源的自然力の「ポイント」として「(1)本源的自然力は,何回用いられても劣化することがない」「(2)再生産されるのではなく,発見される対象」とする。ここで「生産」と「発見」との違いは,生産には社会的再生産の関係に基づいて必要なコストが確定的にわかるが,発見の場合には再現性がなく,要したコストに客観的な根拠がない,ということである。
ここで念のために本源的自然力の概念を従来のマルクス経済学に関連付けておく。自然力に知識を含める観点はすでにマルクス『資本論』にもある。1巻第13章「機械と大工業」第2節「機械から生産物への価値移転」において,自然力自体では費用は不要だが,それを利用するための生産手段には費用が必要である,ことを指摘し,それは自然力も科学も同じ,という(Marx [1962]:407。この部分はドイツ語4版で追加)。ここで自然力は蒸気などが想定されているが,土地も自然力であり,知識も同じように扱えるだろう。「本源的」については,リカードによる「地代は,土地の生産物のうち,土地の本源的な不滅な諸力の使用の代価として地主に支払われる部分である」という規定に対してマルクスは,土地は不滅ではなく,また,自然史的な過程の所産でもあるので本源的ではない,と批判した(Marx [1967]:244)ことはよく知られている(竹永[2019](2):9注(6))。しかし,現在の原理論では土地に対する働きかけのうち,経済学的に意味のある期間では劣化しない不滅の部分を恒久的土地改良として,その期間については本源的とみなすことはできる。この点は新たな発明などの知識についても同様である。
Ⅱ.2.2 本源的自然力の変容
「変容論的アプローチ」とは小幡[2009]をはじめとした一連の研究で提唱されているものである。この説によれば,原理論には論理展開だけでは一つに決まらず,外的条件と結びついて異なる形をとりうる箇所がある。この箇所が「開口部」であり,異なる形が変容である。この開口部は具体的には小幡[2009]では,貨幣,資本など10か所が挙げられている。なお「変容」は「歴史的な変化」の意味ではなく,抽象度を下げることで生じる複数のタイプの存在の可能性である。ただし,変容論的アプローチについては原理論や方法論でも,現状分析でも,まだ十分には考察されていないので,本稿での説明は,筆者の理解(詳しくは岩田[2022])であり,他の説とは異なることもある。
小幡[2009]の地代論で開口部は,絶対地代と恒久的土地改良の2つにある。絶対地代での変容は,本源的自然力の所有者が結託し絶対地代が発生する場合と,結託がなく絶対地代が生じない場合である(小幡[2009]:204)。恒久的土地改良については本源的自然力を改良する主体の行動の内容が原理論では説明できないとする。後者では変容の形については明確ではない(小幡[2009]:211)。
この2つの開口部から知識への拡張を試みる。まず,土地は本質的に不均質なので結託は難しいが,知識の場合は同じ知識には一人の所有者がいるので結託によるARの取得が可能だとわかる。変容のポイントは結託の有無というよりも,結託の可能性の根拠となる本源的自然力の性質にある。次にもう一つの恒久的土地改良の主体については本稿では,本源的自然力の所有者の階級的分立の有無として解釈する。つまり,分立が有る場合は産業資本と本源的自然力所有が分かれており,後者から前者が本源的自然力を借りる。他方,分立が無い場合は産業資本が本源的自然力を専有(高林 [2017]:116)する。これらに踏まえて本節のⅡ.3でARの変容を説き,階級的分立の問題は次節(C節)で説く。
上記のARの変容の観点を発展させれば第3表のようになるだろう。ただし,「土地」や「知識」といった具体的なイメージを強く持つ用語は,原理論に必要な抽象化を妨げることがあるので,ここでは土地などは「タイプ1」,知識などは「タイプ2」とよんでおく。
第3表 本源的自然力の変容
|
多態化 |
土地など |
知識など |
|
変容 |
タイプ1 |
タイプ2 |
|
特定の有体物と不可分に結合 |
特定の有体物と分離可能で,多数の有体物に遍在しうる。 |
|
|
本質的に不均質 |
他のモノとは非連続的な格差。 |
|
|
有体物を通じて利用制限可能 |
法的にのみ利用制限可能,あるいは知識の秘匿で制限可能 |
|
|
展開 |
資本移動の自由→生産条件の格差→競争制限による格差の固定化〔地代〕
→流通過程における競争 |
|
この表で最も抽象度が高く,基底にあるのは原理論の論理的な「展開」である。その順序は,まず,生産価格論では資本の自由な移動と優等な生産条件の模倣によって生産条件は一つと想定される。次に特別利潤では複数の生産条件が想定され,優等な生産条件で一時的な超過利潤が発生し,その後,優等な条件が普及して超過利潤は消滅する。続いて地代論では優等な生産条件が消滅せずに持続的に固定される,という論理展開になる。確定的な生産過程に基づく価格機構は地代が最後で,その後は不確定な流通過程における競争となる。
次に「変容」の複数のタイプは現実の存在としては2つの中間にあたる場合もありうるが,概念としては互いに両極端に対になる概念として抽出される。
タイプ1の特徴は土地をそのままイメージすれば容易に理解可能だ。土地のような特定の有体物と不可分に結合し,再生産不可能なので,個々の土地は本質的に不均質である。有体物の支配を通じて利用制限される。
他方,タイプ2は主に知識であり,無体の要素として特定の有体物と分離可能で,同じモノが多数の有体物に遍在しうる。知的所有権の対象であれば,他のモノとは非連続的な格差がある。利用の制限は法的保護,あるいは知識の秘匿で可能となる。
ここでタイプ2の概念を明確にするために補足すると,すべての有体物は,無体の要素としての知識を含んでいる。例えば椅子であれば有体物であるとともに,デザインや製法など無体の要素としての知識のその内に含む。その無体の要素としての知識は知的所有権で制限されていることもあれば制限されていないこともある。無体の要素の部分が利用制限される場合には,,有体物の所有権が否定される場合もある(Drahos[1996]:ch.7など)。
最後に「多態化」はより具体的な形で,タイプ1には様々な制限された自然力があり,タイプ2には慣行なども含めた広い意味で様々な知識がある。
Ⅱ.3 本源的自然力タイプ2における地代の変化
前項のように変容の内容を特徴づけると,本源的自然力タイプ2での地代の性質を検討できる。ただし,産業資本と本源的自然力所有者の階級的分立の有無によって地代の種類が異なる。先に結論を示すと表6の形になる。
第4表 本源的自然力タイプ2の所有と階級的分立
|
超過利潤の取得 |
|||
|
一時的 |
持続的 |
||
|
階級的分立 |
無 |
ⓐ通常の特別利潤(DR) |
ⓑDR |
|
有 |
ⓒAR |
ⓓAR |
|
まずⓐは通常の特別利潤である。一部の産業資本が優等な条件を専有して超過利潤を得る。調整的な生産条件は従来の生産方法であり,日高のいうDR一般でDR1と同じ形になる。
次にⓑとⓓについては,これに近い例を小幡[2009]:205問題132が取り上げている。そこではDR一般の例になる落流の利用による超過利潤はDR(同:202-203),知的所有権の利用による超過利潤はARと説明している(同:341)。
これを第4表のⓑとⓓに応用すると,まず階級的に分立しているケースⓓは,本源的自然力タイプ2の知識が多数の有体物,つまり多数の産業資本の生産資本に遍在しうるので,調整的生産条件はこの知識を利用した生産条件になる。知識の所有者はその知識の利用を希望するすべての産業資本に利用させ,代価として地代(レント,利用料)を取る。これよりも劣等な生産条件は利用されない。調整的生産条件が地代を要求して価格を引き上げるのでこれはARになる。このARの上限は,まだ利用されていない生産条件のうちで次に優等な生産条件との差になる。図で示すと次のようになる。
ここで重要なことは,タイプ2では,タイプ1とは異なり,この差が非連続的な格差であるためARが可能だということだ。というのは,知的所有権が認められるのは通常,他の方法よりも非連続的に効果がある場合だからだ。DR2については,本源的自然力タイプ2の場合は,この知識を用いた生産条件は同じ生産性で増やせるため,収穫逓減を前提としたDR2は存在しない。
ところで,もし,知識の所有者が一部の産業資本のみに利用を許可し,その他の産業資本が劣等な生産条件を用いる場合は,一部の産業資本と知識所有者が事実上,一体化しているので階級的分立がないⓑのケースの一つになる。
次にⓑでは階級的分立がなく,優等な生産条件の利用は特定の産業資本の生産資本に限定される。その意味で本源的自然力タイプ1と同じに形なる。それよりも劣等で利用制限されていない生産条件が調整的となる。この場合は日高のいうDR一般でDR1と同じ形になる。
ⓒは,ⓓと基本的に同じで,知識への所有権が維持できる限りでARを得ることができる。
こうして,本源的自然力タイプ2では日高説の前提,①同じランクの生産条件の多数性と,②異なるランク間の生産条件の非連続的な格差,の2つの条件を満たすので,DRとARについての日高の説明が適用できる。つまり階級的分立があればAR,なければDRになる。
Ⅱ.4 小括
おそらくは日高らの原理論の研究者は,地代を簡潔に考察するために例解に用いたマルクスの地代表に制約され,日高の2つの前提に基づいていた。しかし,本源的自然力を2つのタイプの変容として明確に区分することで,日高の2つの前提は本源的自然力タイプ2に適合的なことがわかる。また小幡[2009]のARに関する開口部での変容も,本源的自然力タイプ1とタイプ2への変容に吸収される。このB節では,階級的分立の有無による地代の性質の違いを論じた。次のC節では,原理論の展開における階級的分立の発生の可能性について論じる。これは,小幡『経済原論』の地代でのもう一つの開口部である本源的自然力所有者の行動の内容に相当する。
Ⅲ.本源的自然力所有者階級の分立
Ⅲ.1 特別利潤と地代論との関係
これまでの原理論の想定では,特別利潤は一時的で,地代は持続的という区別とともに,超過利潤の源泉は,特別利潤では特別な知識の利用,地代では本質的に不均質な外的自然の利用という区別があった。この関係は表5の形になる。
表5 特別利潤と地代,知識と土地の組み合わせ
|
一時的な特別利潤 |
持続的な地代 |
|
|
知識 |
㋐ |
㋑ |
|
外的自然 |
㋒ |
㋓ |
従来は,特別利潤が㋐,地代が㋓になり,互いに共通項がなく,別々に取り扱うことが可能だった。しかし地代論を知識の領域に拡張すると㋐から㋑への拡張になる。単純に考えれば,高い生産性をもたらす知識が,時間の経過で社会全体に普及していくのであれば特別利潤で,知的所有権で持続的に利用制限されれば地代,というだけのことのようだが,そうはいかない。特別利潤では暗黙の裡に,一部の産業資本が特別利潤を生む知識を自身で専有する,つまり特定の産業資本と知識との一体化を想定している。しかし通常の原理論の地代論では,本源的自然力の所有者と産業資本との階級的分立を前提し,競争によって賃貸借の相手は変わることを想定している。
ている。そのため,本源的自然力タイプ2について階級的分立の発生の有無を考察する必要がある。もし分立がなければ地代論に至っても産業資本が本源的自然力を所有し続け,産業資本とはいえなくなる。現代のIT企業や巨大自動車会社などは本源的自然力タイプ2を産業資本の中に組み込んでおり,あらかじめ,本源的自然力タイプ2も産業資本の外側で所有されている,と言って済ますわけにはいかない。ここに本源的自然力タイプ1とは異なる困難がある。
なお,この表の対称性から㋒の領域も問題にできるが,本稿は知識と地代論との関係を扱うので,㋒は取り扱わない。
Ⅲ.2 本源的自然力所有者階級の分立について先行研究の検討
先行研究はほとんど土地についてのものなので,土地所有から検討を始める。
Ⅲ.2.1 土地所有を前提にする説
産業資本と本源的自然力所有者との関係について,マルクス『資本論』は,第38章「差額地代:総論」の落流の例では,一部の産業資本が落流を所有して超過利潤を得るという想定から始める。その後「いま,落流が,それの属する土地とともに,地球のこの部分の所有者すなわち土地所有者とみなされる主体の点にあるのと考えてみれば」(ibid.:658-659)と階級的分立関係がいきなり持ち込まれる。そうすると落流を所有している産業資本家は超過利潤を資本家としてではなく落流所有者として取得する(ibid.:659)という。階級的な分立は形式的に扱われている。
次に宇野は,土地所有の必然性について,第1に本源的蓄積として労働者を土地から切り離すために,労働者のみならず資本とも分立した土地所有者が必要であり,第2に土地は生産物ではなく資本ではないので,資本家階級からも分立した独自の階級として必要だと述べた(宇野[1964]:177)。つまり,土地所有との階級的分立は資本主義成立の前提だということと,土地は再生産過程に基づく価値物でないということである。第1については大内による批判がある。第2は正当な内容で後述Ⅲ.3.3の内容に関連する。
Ⅲ.2.2 資本による土地所有の押し出し説
大内は,原始的蓄積によって資本主義の出発点で土地所有があったとしても,労働力との分離を維持する機構が資本主義になければ,やがて労働者と土地が結合する,と批判した(大内[1982]:602-603)。原理的には土地所有を歴史的に与えられたものとするのではなく,土地所有のないところから出発し,地代論が展開され,土地所有の必然性が論証されなければならない,とした。(大内[1958]:223-224)。原理論の展開における土地所有の発生については,資本は競争にって利潤率を均等化せざるを得ないが,超過利潤を不断に生み出す農業では超過利潤を第三者に引き渡す機構が存在せざるを得ない。それが土地所有と土地所有者階級である,とする(大内[1958]:221-222,[1982]:604-605)。しかしこの説き方には問題がある。個別資本は自分の利潤を最大化するために行動しているのであり,利潤率を均等化させるために行動しているわけではないからだ。利潤率均等化が土地所有を要請する,という「行く先論アプローチ」になっている。しかし,現代の原理論では,個別資本の利潤追求行動が結果として土地所有を生み出す「行動論的アプローチ」で説く必要がある。「行動論的アプローチ」は宇野以来,積極的に用いられており,大内も補足的に用いている。それは,資本が土地を所有すると,その土地の価格からは利子率しか得られないが,土地を売って機能資本にすれば利子率よりも高い利潤率を得ることができるので,資本は土地を外在化させる(大内[1982]:533-534)というものである。
しかし,資本は利潤を得ることができるから利子しか得られない活動はしない,という論理は宇野が原理論から株式資本を排除した論理と同じである。これについては山口重克以降の原理論では,固定資本の償却資金など長期的に遊休する資金を,利子しか得られない株式や債券の購入にあてる契機を明らかにしている(山口[1985]:236-237)。その論理でいえば産業資本が長期的な遊休資金で土地を買うことは当然,想定される。現代でも本社ビルと土地を売却してそれをそのまま賃借りしたり,逆に賃借りしていたものを購入したりという行為をみれば容易に理解できる。
次項からは,本源的自然力が,資本とは別の本源的自然力として認識され,分化する論理を検討する。
Ⅲ.3 本源的自然力所有者階級発生の論理
Ⅲ.3.1 資本内部における本源的自然力の認識と測定の発生
資本の利潤追求運動が土地所有を外部に措定する例はマルクス『資本論』にも少しある。それは土地所有者の自己経営が排除される論理の説明である。つまり,産業資本が土地を所有する自己経営であっても,生産物への需要が増えて所有地よりも広い土地が必要になれば,土地の賃借りが必要になる。こうして所有と経営の分離が生じる,というものだ(Marx [1964]:759-760)。逆に言えば,生産物への需要が減って所有地の一部が不要になれば,土地の賃貸しが必要になる。
この論理は資本移動で考えれば一般化される。資本が本源的自然力を保有していても,その超過利潤は将来にわたって常に保証されるものではなく,将来も含めて多数の資本の間には相異なる思惑がある。そのため,その本源的自然力を資本が賃貸しまたは売りに出すこともある。その際,価格がついて地代の源泉である本源的自然力が明確に分離して現れる。その際の本源的自然力の価格は従来の原理論と同じで,将来に渡って本源的自然力に起因する超過利潤を現在価値に換算した価額となる。
本源的自然力階級の分立を積極的に説明していなければ,本源的自然力を買い取る主体は,さしあたりは資本家階級としなければならない。ただし,買い取った産業資本の内部で産業資本の本体とは区別され,本源的自然力それ自体の自立化が現れる。
この自立化は知識が重要になった現代では顕著になる。M&Aに際して新自由主義の現代で標準となったパーチェス法では,「無形資産」が認識され測定される傾向が強まっている。重要な無形資産の測定には主に「超過収益法」が用いられる。超過収益法では,評価対象となる「無形資産」が関係する事業活動の収益から,その「無形資産」以外の資産,言い換えるとその「無形資産」の収益獲得に貢献する「貢献資産」のコストと期待利益を差し引くと,その残余がその「無形資産」による超過利益となる。その利益の将来にわたるフローを現在価値に還元してその「無形資産」の現在価値を算出する(たとえば山本・金子[2021]:56-57, 118)。
この超過収益法による「無形資産」の測定は,従来の地代論で説明されてきたものと同じである。つまり地代論では,新たな地代契約や契約更新に際して,収益から投下資本の回収額と平均利潤を差し引いた残りである超過利潤が評価され,この超過利潤を土地所有者が地代として得る(統制小作料としての地代計算の例は島本[2001]:53)。
知識のような「無形資産」は,有形資産としての固定資本とは異なり,減価償却されない。耐用期間が不明であり,減価しないことによる。資産獲得のために支出された費用の回収は償却amortization(笠井2005,240)されるか,再評価モデルの場合には必要に応じて再評価をして以前の評価額との差額を損失とすることによる。
こうして産業資本の中に埋もれていた特別利潤の源泉は,資本移動やM&Aを通じて,超過利潤の源泉である本源的自然力として認識され,平均利潤をもとに超過利潤の額に基づいて測定される。こうして,特別利潤から地代へと原理論の展開が可能になる。
Ⅲ.3.2 本源的自然力の新たな創出と恒久的改良を担う経済主体の発生
土地所有者を,地代を受け取る受動的な存在ととらえるだけでは,かつて宇野が株式資本は原理論では説けないという説が批判され克服されたのと同様の道をたどる。つまり長期的な遊休資金の運用先として土地所有を説くことが可能になるからだ。しかし土地の,一般化すれば本源的自然力の,新たな創出や恒久的改良を担う主体とすれば本源的自然力所有者階級は積極的に原理論に位置づけられる。
土地改良は土地所有者が担うとする議論については歴史的な研究では椎名[1973](とくに第3章)など多数ある。土地所有者が直接に改良事業を担う場合もあれば,借地資本家が支出した改良費用を契約更改時に土地所有者がtenant-right(椎名[1973]:66)や有益費(島本[2001]第4章)として補償する形で間接的に担う場合もある。
ただし,これを原理論で考えるにはまず,土地への働きかけを概念として,効果が損耗し減価償却する土地合体資本と,損耗しない恒久的土地改良に区分する必要がある。こうして恒久的土地改良について,土地所有者の行為と存在を積極的に示すことが可能になる。小幡[2009]は,この恒久的土地改良は本質的に不均質な外的自然を対象とし,それぞれ一度限りの行為であり,利潤の均等化のような安定的な関係がなく,産業資本の生産過程に収まるものではない。そのため資本家と労働者以外の第3の主体が必要になる(小幡[2009]:211)と説く。この議論を知識の領域に拡張すれば,新たな知識の発見には客観的に必要なコストが存在しないこと,発見された知識は恒久的に効果を持ち続けることといった点に土地との共通性がある。なお,知識はより新しい知識によって無効化,あるいは陳腐化することもあるが,その知識自身が有体物のように損耗することはない。この無効化(陳腐化)は土地にも起きる。優等な土地はそれ自身の生産性が変わらなくとも,調整的となる最劣等の生産性の水準が上昇すれば,地代が減少したり,地代がゼロになったりすることもありうる。両者とも発見や改良に支出した費用には原理的に減価償却の概念は適用されず,償却あるいは再評価となる。
この項では,土地所有など本源的自然力所有者は,大内が言うような資本の運動から押し出されるだけの受動的な存在ではなく,地代の増加を求めて積極的に活動する主体とみなした。次に,本源的自然力所有者の産業資本からの分化を説明する。
Ⅲ.3.3 本源的自然力所有者の分化発生
もともと原理論では産業資本は,特別利潤(あるいは特別剰余価値)とよばれる超過利潤を得ようとする,と想定している。それゆえ産業資本の内部には新たな知識を生み出す要素があると想定されている。
産業資本の内部にある異質な要素から,個別資本が利潤を最大化しようと競争して行動する結果,異なる種類の資本へと分化すると説く方法は,宇野学派では分化発生論とよばれてきた。流通過程や信用業務は,商業資本や銀行業資本という形で異なる種の資本として分化する。知識を発見する要素も,産業資本の本体の運動とは異なり,超過利潤を追求する主体として分化発生すると説くことができるだろう。
従来の分化発生論は主に,分化前の産業資本が対処すべき不確定な流通過程を外部に押し出す作用を中心に論じてきた。第1表の「市場機構」の箇所である。本源的自然力の創出は第1表では「市場機構」の前になるが,客観的に根拠のない支出を必要とすることでは流通過程と似た性質があり,流通過程と同様に外部に押し出される作用もある。実際の例としては個人発明家,IT起業家,ベンチャービジネス,大学などの公的研究機関,大企業の中央研究所(最後の例についてはRosenbloom, ed. [1996]訳書:146, 8-9)の形である。問題は押し出された要素が「資本」になるか,ということである。資本であれば本源的自然力所有者階級は分立せず,「本源的自然力創出資本」,または「地代生み資本」(Teixeira and Rotta
[2012]: 463-465)になる。検討するための基準としては,資本とは「自己増殖する価値の運動体」であり,価値物として貨幣と商品の姿態変換運動をして価値を増やすものである。これに踏まえて分化発生する他の資本と比較する。
まず商業資本は,売買する商品は価値物であり,G-W-G’の姿態変換をするので資本である。ただし,流通費用の部分は,G-W…(消滅)という形をとるので姿態変換はしない。商業資本としては姿態変換する部分としない部分を合わせて資本となる(山口[1985]:60-61)。
次に銀行業資本では,自己資本の部分は,信用調査費など流通費用への支出や貸倒準備に充てられるので姿態変換しない。しかし現代の原理論は銀行業資本を商業信用から銀行信用へという論理展開で論じるので,銀行業資本の活動は与信先の受信資本における商品販売可能性の調査が基礎になる。そのため銀行業資本の自己資本部分は姿態変換をしないが,自身の利潤は与信先の資本の姿態変換運動から生まれる。この点で,銀行業資本は与信先の資本の姿態変換運動の一部を構成する資本といえる。
では,本源的自然力の創出は「本源的自然力創出資本」あるいは「地代生み資本」となるだろうか?以下の理由で資本ではなく,別個の階級となる。第1に,新たな本源的自然力の創出には労力や資材が必要で,それを購入すればG-Wになるが,新たな本源的自然力それ自身は価値物ではないのでG-W…(消滅)という形になり,姿態変換しない。第2に,本源的自然力は産業資本の生産過程で機能するが,生産過程それ自体は,貨幣や商品の姿態変換運動にとっては外部にあたる。そのため,本源的自然力が産業資本と一体で姿態変換するとは言えない。第3に,本源的自然力の保有では常に本源的自然力を貸し続ける,つまり一定期間の利用権を売り続けているが,同じものを継続して繰り返し売っているだけ姿態変換ではない。賃金労働者が自身の労働力を繰り返し販売し続けているを「資本」とはよばないと同様である。
Ⅲ.4 小括
C節では,まず大内に問題意識にそって土地所有を資本の外部に押し出す論理を検討した。現在の原理論の株式資本の議論に踏まえれば,利潤よりも低額の地代を受動的に受け取る本源的自然力所有を原理的に説明するのは困難だ。そうではなく,積極的に本源的自然力を創出あるいは改良する主体とすることで本源的自然力所有者を原理論で説明できる。本源的自然力を創出あるいは改良する要素はもともと産業資本にあるので,その要素が新たな主体として分化発生すると説くことができる。しかしその主体は資本とは言えず,独自の階級となる。
まとめと展望
現代の資本主義で重要性を増す知識を,知的所有権を基に地代論で論じるのは非常に展望のある方法である。しかし,土地を基礎にした従来の地代論でそのまま知識を論じるには,土地の概念に過重な負荷がかかる。土地をいったん本源的自然力へと高度に抽象化したうえで,本源的自然力がより具体的に変容する2つのタイプに分ける必要がある。タイプ1は,特定の有体物と不可分に結びき,本質的に不均質なもの,であり,タイプ2は,特定の有体物から分離可能で多数の有体物に均質に遍在できるものとなる。
これまで検討されてきたタイプ1の地代から,知識への拡張としてのタイプ2の地代の拡張は,これまでの地代をその基礎とすることができる。ただし,日高らの説はもともと想定していたタイプ1よりも,タイプ2の方により適合になる点で逆説的である。それは,これまでの地代論がタイプ1における本質的に不均質な性質の検討が不十分なまま,例解として簡単な数値例の地代表を用い続けたことによる。この問題は変容論的アプローチとして抽象的にとらえることで克服できる。
小幡[2009]が変容論的アプローチとして地代論で指摘した2つの開口部,つまり変容のポイントについて本稿では,まず一つ目のARについては本源的自然力のタイプ1とタイプ2として,2つ目の本源的自然力所有者の行動については産業資本と本源的自然力所有者の階級的分立の有無として整理し発展させた。こうすることでタイプ2でのARの発生と,階級的分立がなければDRになることを明らかにした。
本源的自然力所有者階級の意義を,本源的自然力の単なる所有ではなく,新たな本源的自然力の創出と恒久的改良においた。さらにその発生の論理的な根拠を,もともと産業資本にあった要素の分化発生論として説いた。これは,これまでの宇野学派における宇野への批判的克服と発展の方向に沿ったものである。この方向でさらに宇野学派の原理論は進めることができるだろう。
なお,本稿では知識を地代論として説くことが目的だったため,従来の地代論が取り扱ってきたタイプ1でのDRとARの説き方や,特別利潤から地代への展開も触れることはできなかった。これは日高説におけるDR2とARの交替を利用すれば説明可能だが,次稿に譲る。
今後の発展の方向性としては,タイプ1とタイプ2の相互転換可能性である。たとえば,知識は本来的にタイプ2だが,特定の人にのみ習得可能な知識はタイプ1になりうる。小幡『経済原論』でいえば,「名人芸のような『個人の熟練』」(136頁)に相当するだろう。複雑労働として習得可能な範囲であればタイプ2であり,その知識が知的所有権の対象となればタイプ2のままで利用制限される。この種の知識は現在の会計でも「競業避止協定」や場合によっては「雇用契約」の形で「無形資産」になっている。
本稿の対象は生産過程にとどめたが,商標権や商号権,地理的表示といった,流通過程に作用する私的所有権も「商業地代」としてさらに考察の対象にできる。著作権は最終消費の対象に関連すると思うのが自然だか,本という有体物や,アクセス権といった債権を売るためのラベルとして流通費用と考えると話が非常に簡単になる。いずれにしても現実には雑多に理解されていることを原理論で説明すること自体に展望があるといえるだろう。
参考文献
飯島充男[2016]「虚像としての絶対地代論」『商学論集』 84
(4)
岩田佳久[2022]「変容論的アプローチ」の適用:段階論と現代資本主義論のための原理論の「開口部」についての体系的な考察」『東京経大学会誌(経済学)』315
宇野弘蔵[1964]『経済原論』岩波書店
大内力[1958]『地代と土地所有』東京大学出版会
大内力[1982]『経済原論:下』東京大学出版会
小幡道昭[2009]『経済原論 : 基礎と演習』東京大学出版会
笠井昭次[2005]『現代会計論』慶応義塾大学出版会
椎名重明[1973]『近代的土地所有. その歴史と理論』東京大学出版会
島本富夫[2001]『現代農地賃貸借論』農林統計協会
竹永進[2018,2019]「1860年代前半のマルクスの地代論研究 :
61-63年草稿,『資本論』第三部主要原稿第6章(65年)および関連抜粋ノート(リービッヒの農業化学)を中心に (1)~(3)」『経済論集』110~112
新沢嘉芽統,華山謙[1976]「地代の一般理論」(『地価と土地政策 第二版』岩波書店,所収))
高林龍[2017]『標準特許法:第6版』有斐閣
富塚良三[1976]『経済原論:資本主義経済の構造と動態』有斐閣
日高普[1962]『地代論研究』時潮社
日高普[1983]『経済原論』有斐閣
山口重克[1985]『経済原論講義』東京大学出版会
山本智貴,金子竜平[2021]『PPAの評価』中央経済社
Birch, K.
and F. Muniesa [2020] Assetization: turning things
into assets in technoscientific capitalism, MIT Press
Drahos, P. [1995] A Philosophy of Intellectual Property, Dartmouth
Golka, P. [2021]”Assetization: A technoscientific or financial phenomenon? ,”
Finance and Society, 7(1)
Marx, K.[1962] Das Kapital, Buch I, in
Marx-Engels Werke, Bd. 23, Diets Verlag.
Marx, K.[1964] Das Kapital, Buch III, in
Marx-Engels Werke, Bd. 25, Diets Verlag.
Marx, K. [1967] Theorien über den Mehrwert, Zweiter
Teil Ⅱ, in Marx-Engels
Werke, Bd. 26, Diets Verlag.
Rigi, J. [2014]”Foundations
of a Marxist theory of the political economy of information: Trade secrets and
intellectual property, and the production of relative surplus value and the
extraction of rent-tribute,” tripleC : Communication,
Capitalism & Critique, 12(2)
Rosenbloom, R., ed. [1996] Engines of innovation:
U.S. Industrial Research at the End of an Era, Harvard Business School
Press(西村吉雄訳[1998]『中央研究所の時代の終焉:研究開発の未来』日経BP社)
Rotta, T.N. and R. Teixeira [2019]”The
commodification of knowledge and information, in Vidal,“ in M.et al.,
eds, The Oxford Handbook of Karl Marx, Oxford University Press
Teixeira R. and T. N. Rotta [2012]”Valueless
Knowledge-Commodities and Financialization: Productive and Financial Dimensions
of Capital Autonomization,” Review of Radical Political Economic, 44(4)
Zeller, C. [2007]”From the gene to the globe:
Extracting rents based on intellectual property monopolies,” Review
of International Political Economy, 15(1)
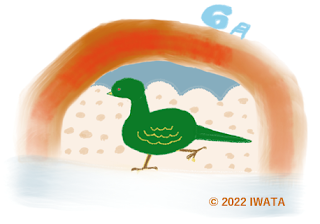





コメント
コメントを投稿