注目
マルクス『資本論』における「自然力」の概念について
「自然力」概観
土地に関する地代論を知識の領域に拡張するには、土地を自然力として概念化し、それを拡張する必要がある。そのための準備として、マルクスの『資本論』での「自然力Naturkräfte」の使用を確認する。自然力という語が『資本論』で集中的に使われる個所は2つある。
1つ目は、第1巻のS.407~411(
Werke版)第4篇「相対的剰余価値の生産」第13章「機械と大工業」第2節「機械から生産物への価値移転」。
2つ目は第3巻のS.656~661第6篇「超過利潤の地代への転化」第38章「差額地代。総論」である。
この2つは現代の宇野学派の原理論体系(たとえば小幡『経済原論』)でいえば、1番目が生産論の生産過程論、2番目が機構論の価格機構の地代論である。
マルクスの場合は、投下労働価値説(1巻)、あるいは生産価格論(3巻)が基礎なので、自然力についてはその無償性が強調される。その存在自身が無償である、という意味だが、生産過程で生じた廃棄物が自然力によって無償で処理される、ということも含めて考えることもできる。
先に見通しを書くと、生産過程論、あるいは「機械と大工業」では、自然力は無償だが、それを利用するには生産手段が必要で、生産手段は資本家階級が独占する。結果として、自然力は資本家階級が独占的に利用できる。他方、地代論では、自然力の中には、一部の資本によってのみ利用できる特別に生産性の高いものがあり、この自然力を利用することで超過利潤が生じる。この超過利潤は生産条件の所有者に地代として支払われる。ここまではマルクスもリカードもほぼ同じだが、最劣等地のように、所有はされているが、最劣等の自然力については両者は異なる。土地を例に言えば、最劣等地について、リカードでは量が無限で質が均一であれば、無地代の土地となる。しかしマルクスは土地所有を強調して、差額地代とは異なる絶対地代の存在を説く。これは資本の本源的蓄積として、プロレタリアートを土地から切り離すために土地所有者階級による土地の独占的所有が必要となるからである。
自然力の分類
生産過程論と地代論の両方で「自然力」が意味する範囲は、生産過程論で現れる順番で言うと、①主に分業と労働の効果である労働の社会的自然力、②土地と、蒸気や水力などの外的自然、③科学や知識、技術、④機械のうち価値移転されない部分の4つがある。図式化すると次のようになる。
|
|
生産過程論(機械と大工業) |
地代論 |
|
|
資本にとってその利用は |
無制限 |
制限される |
|
|
種類 |
①労働の社会的自然力(分業と協業) |
㋐ |
㋔ |
|
②外的自然 |
㋑ |
㋕ |
|
|
③知識 |
㋒ |
㋖ |
|
|
④機械のうち価値移転しない部分 |
㋓ |
㋗ |
|
ただし、『資本論』には存在しないセルもある。
以下、生産過程論と地代論についてそれぞれ説明する。
生産過程論における「自然力」
スミス、リカード、マルクス
まず前提として、スミスの自然力の概念をリカードが批判し、その批判をマルクスが承認している。
マルクスは『剰余価値学説史』(Ⅰ巻, S.31, Werke版)で、スミス『国富論』から重農学派のような次の記述を引用する「地代は、人間の所産とみなしうるすべてのものを控除または補填したあとになお残るところの、自然の所産である。それは、総生産物の4分の1以下であることはめったになく、しばしばその3分の1よりも多い。…製造業では、自然力はなにもせず、人間が一切のことをする」 続けてマルクスはリカードによる批判を引用する「自然は、製造業においては人間のために何もしないのか? われわれの機械を動かし、航海を助ける風や水の力は、なにものでもないのか? 金属を軟化し溶解する熱体の効果や、染色および発酵過程中の大気の分解効果については言わないまでも、最も巨大なエンジンの運転を可能にする気圧および蒸気の弾性は、自然のたまものではないのか? どんな製造業でも、自然が人間にその援助を、しかも寛大に、かつ無償で、与えていないようなものは一つもあげることができない」
これらの主張をふまえたうえでマルクスは『資本論』で《そうした自然力を利用するには大規模な生産手段が必要であり、その生産を所有するのは資本のみである。資本のみが自然力の利用を独占する》(『資本論』第1巻S.407)という趣旨のことを論じた(詳しくは後述)。資本と賃労働という資本主義的な階級関係の下では、資本はこうした自然力を無償で無制限に利用できる。こうして自然力は資本の生産力として現れる。
自然力の区分
①社会的労働の自然力
自然力の記述が集中的に現れる「機械から生産物への価値の移転」の冒頭は「協業や分業から生じる生産力は、資本にとっては一文の費用もかからない。それは社会的労働の自然力である」(S.407)という内容から始まる。自然力の記述が、蒸気や土地といった外的自然からではなく、労働の社会的生産力から始まるのは、この部分より前の2つの章が協業と分業を扱っているからである。
②蒸気などの自然力
同様の自然力は、蒸気力のような外的自然について当てはまる。「生産諸力に取り込まれる蒸気、水などのような自然諸力も、(協業や分業から生じる生産力と―引用者注)同じように何らの費用も費やさせない。しかし、呼吸のためには肺を必要とするのと同じく、人間が自然諸力を生産的に消費するためには「人間の手でつくられたもの」を必要とする。水の動力を利用するためには、水車が必要であり、蒸気の弾性を利用するためには蒸気機関が必要である。」S.407
③自然科学
さらに、科学についても同様の効果がある。「科学も自然力と同じことである。電流の作用範囲における磁針の偏倚にかんする法則や、周囲を電流が回っている鉄における磁気の発生にかんする法則は、ひとたび発見されれば、一文の費用も費やさせない。しかし、これらの諸法則を電信などに利用するためには、極めて高価で大仕掛けな装置が必要である」(S.407-408)
④機械の内で価値移転しない部分
最後に、機械の内で価値移転しない部分が同様の効果をもつ。「機械と道具とから、それらの毎日の平均費用を引き去れば、すなわちそれらが毎日の平均損耗と油や石炭などの補助材料の消費とによって生産物につけ加えられる価値成分を引き去れば、機械や道具は、人間の労働を加え加えられることなく存在する自然力とまったく同じに、無償で作用することになる。」 S.409
この点については、マルクスは注釈をつけてリカードを批判している。つまり、リカードも同様に自然力と機械の共通性を指摘しているが、リカードは「機械が生産物に引き渡すか価値成分を忘れてしまって、機械を自然力と全く混同してしまっている。」と、マルクスは批判した。なお、リカードによる記述は以下の通りである。「自然力と機械は、それらの仕事を無償でするのだから、それらが我々に当たる助力は交換価値には何も付け加えないのである。」(スラッファ編『経済学および課税の原理』英文p.286、訳書330頁)である。
これらの4つの自然力、あるいは自然力と同じモノを大規模に産業的に利用することは、固定資本を持つ資本のみが独占しており、他の階級は排除されている。(小規模であればだれでも利用していることは言うまでもない) これらの自然力は、資本と賃労働の階級関係の意味で言えば「制限された自然力」になる。とはいえ、普通、「制限された自然力」という場合は、地代論で説明される「資本にとって制限された自然力」のことである。
地代論における「自然力」
機構論では複数の資本の間での競争関係が焦点であり、その中で地代論は、利用できる資本と利用できない資本のある自然力が焦点になる。ここでは、資本にとって利用が制限されるという意味で「制限された自然力」となる。制限された自然力が生産条件となる生産活動では超過利潤が生まれことがあり、その生産条件の賃借りをめぐる産業資本間の競争で、その超過利潤は賃貸料としての地代に転化する。
生産過程論で挙げられる4つの自然力、あるいは自然力と同等の作用をするものは、地代論では以下のように現れる。順番に説明する。
⑥外的自然の制限
蒸気のような自然力の利用については、他の階級に対して資本家階級が独占するが、それはどの資本でも利用可能なので超過利潤は生じない。そのため、超過利潤の発生には「もっとほかの事情が加わってこなければならない」(S.656)とマルクスは説明している。落流については「落流のように、ただ土地の特殊な部分とその付属物とを自由に利用できる人々だけに利用できる、独占されうる自然力である」(S.658)と説明する。落流の例はこの章(38章)で詳しく説明されている。通常の地代論の研究は、38章の落流の例から39章以降の農地の例へと焦点が移るが、38章には落流以外にも「ほかの事情」への言及がある(S.657)。この中に、社会的労働の自然力と、知識が制限されて超過利潤を生む例の説明がある。
⑤⑦社会的労働の制限と知識の制限
『資本論』の記述のメインは落流から農地への流れだが、労働の社会的自然力と知識についても言及がある。
「一つは労働の生産力を高くする一般的な諸原因(協業や分業など)が、より大きな労働場面で作用することによって、より高い程度,より大きい強度で作用することができるという事情」もう一つは「より優れた労働方法や新たな発明や改良された機械や化学的な製造上の秘法等、要するに、新しい、改良された、平均水準を超えた生産手段や生産方法が充用されるという事情」(S.657)とある。前者が労働の社会的自然力で、後者が知識の例である。
これらの2つの方法による超過利潤は一時的なものである。「これらは資本が例外的に大量に一つの手の中に集積されているということ ― この事情は同じ大きさの諸資本量が平均的に充用されるようになれば解消してしまう ― から生じるか、または、一定の大きさの資本が特に生産的な仕方で機能するということ ― この事情はこの例外的な生産方法が普及するかまたはより発達した生産方法によって追い越されるかすればなくなってしまう ― から生じる」(S.657) こうした制限は、労働の社会的自然力の場合は固定資本の大型化、知識の場合は特許や営業秘密trade
secretに相当する。
ここで得られる超過利潤は、これらの方法の普及による超過利潤の消滅を前提としており、原理論で言えば特別利潤になる。他方、この制限が持続するならば、それは地代と同じになる。
しかし特許には普及と独占の二面性がある。特許権者に一定期間の独占権を認めるとともに、特許の内容の公開によってその特許の内容が陳腐化する可能性も生じる。この二面性は特許がその中間項としてわかりやすい。たとえば特許庁の『2022年度知的財産権制度入門テキスト』には以下の説明がある。「特許制度は、発明を世にオープン(開示)することを条件に、発明者に対して独占的実施権を付与するとともに、この発明の開示により、発明利用の途が提供されることになり、改良発明の誘発や新たな発明が生まれる機会が生ずることになる」(11頁「第2章 産業財産権の概要 第1節 特許制度の概要 [1]特許制度の目的」)
このように、特許の例は、原理論の展開において特別利潤と差額地代の中間項として論じるのに適切である。
⑧機械の内の価値移転しない部分
機械の内の価値移転しない部分については、地代論の部分には相当するものがないようである。
蒸気力的自然力と土地自然力の区別
外的自然については、蒸気力的自然力と土地自然力に区別できる(寺出[1981]「地代論における「自然力」概念について」)。
蒸気力的自然力は生産過程論では資本にとって無制限に利用可能で、土地自然力は地代論で資本にとって利用制限がある、として、蒸気力的自然力と土地自然力は別のもののようにも見える。しかし、蒸気力的自然力と土地自然力には連続性がある。つまり、リカードの地代論は「もしすべての土地が同じ性質で、量において無限で、質において均一ならば、土地の使用に地代は生じない」(リカード『原理』スラッファ編英文p.70) この場合、土地は蒸気力的自然力と同じになる。リカードの文脈ではこれはすべての土地についての仮定の話である。しかし、最劣等地が同質で、当面の社会的需要に対して相対的な十分に多ければ、無地代の最劣等地については蒸気力的自然力と同じになる。
リカードは無地代の土地の想定から始めて、下方序列での耕作拡大で差額地代の発生を論じる。この議論に対してマルクスは『剰余価値学説史』(Ⅱ巻S.307-314)で批判する。批判は一つには、豊度だけではなく位置の問題もある、ということである。しかしこれは販売市場に持ち込むコストで考えれば重要な批判ではない。もう一つは最劣等地でも絶対地代や差額地代(第Ⅱ形態)が存在するという批判である(S.312など)。しかし、自然力の理解のためには、ここでは絶対地代なしの状態で理論的展開をして、その後で絶対地代を導入した方がよいだろう。そうすることで、蒸気力的自然力と土地自然力は同じ自然力として理解可能になる。
以上の考察で、自然力を生産過程論と地代論を通して、土地自然力、蒸気力的自然力、知識にわたって分析可能になる。ただし、ここでは自然力を無償性の観点から論じている。地代論の知識への応用、あるいはマルクスの価値論、生産価格論、階級関係の議論には適切であるが、自然力のその他の面を論じることができるかどうかは別の問題である。
自然力についての参考文献
小幡道昭[2023]「環境と再生産:「本源的で不滅な土壌の力」批判」第554回 独占研究会 報告
寺出道雄[1981]「地代論における「自然力」概念について」『三田学会雑誌』74(3)
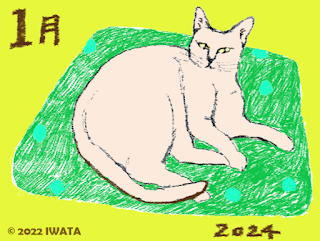

コメント
コメントを投稿