注目
ネオリベラルな現代
ネオリベラルな現代
新自由主義としての現代資本主義
5、6年前から「現代資本主義論」を担当するようになり、現代資本主義の特徴を理論的に考える必要に迫られた。そういえば宇野弘蔵は、経済原論と経済政策論を同時に担当する中で原理論と段階論という経済学の体系を構成したのだった。
宇野の方法を引き継ぐ論者は、第一次世界大戦以降を「現代資本主義」としてきた。しかし今から100年以上前から現代資本主義、というのは、文字通りの「現代」の学生にとってリアリティに欠ける。それよりも1980年代以降の大きな変化を、リアリティをもってとらえる枠組みが必要だ。このあたりの事情は、すでに論文に書いたのでこれ以上は詳論しない。(段階論における歴史と現在)
そこで、1980年代移行を新自由主義としての新たな段階とする現代資本主義論を講義し、学生とも直接、間接に議論をしてきた。
現代資本主義論という科目はよく考えると大変な科目で、現在の経済事情を全て網羅しなければならないし、また段階論の方法に踏まえれば、現代は歴史的な発展との結果としての現代なので、過去に遡ってまで現代の特徴を説く必要がある。実際、東京大学の「現代資本主義論」では英文タイトルがModern Capitalism from
the Historical Perspective となっている。
いろいろやり方はあるだろうが、この講義を良い機会だと考え、原理論をベースにした新たな段階の構成をこころみた。そのベースとなる方法は、山口重克氏の「ブラック・ボックス」論と小幡道昭氏の「開口部」論・変容論的アプローチである。しかし、原理論の専門家は現実を知らないのでそのままでは使えない。そこで段階論の区分には加藤栄一の方法を用い、原理論の中のテーマごとに段階的変化を当てはめて論じることにした。段階区分は、19世紀の古典的自由主義、19世紀末からの組織化の時代、1980年代からの新自由主義の時代、の三つである。
原理論の使い方や段階区分には方法論的な問題がいろいろあるが、ここで詳しく書くと話が進まない。すでに公刊済みの論文でも論じていた。
内容を簡単にいえば、新しい段階論と原理論がクリアに対応するのが、会計における利潤(利益)の認識と測定における「収益費用アプローチ」から「資産負債アプローチ」への変化である。商業機構は「流通系列化」から「製販統合」への変化である。これらは組織化の時代から新自由主義への変化と対応する。これはすでに論文で書いた。今後は、信用貨幣の段階的変化、知識を地代論で説いて段階的変化を説く…、と一連の論文にしようと思っていたのだが、まとまった論文が多数、必要になり、何年かかるか分からない。とても無理だ。実は、これがこの文章を書いている動機だ。
ただし、積極的に言えば、宇野の段階論よりもはるかに現代に精通し、既存の理論の枠にこだわらない学生との議論で、原理論と段階論をさらに進めることが求められる。VTuberへの投げ銭が市場的行為か、という点は延々と議論が続いた。
また、小幡氏の『経済原論』では、生産性を高める知識を本源的自然力として地代論として論じるようになった。そうすると、IT企業の中には資本としての性質だけでなく、本源的自然力を所有する「土地所有者」の性質を併せ持つことになる。また、個人資本家における家産と資本のあいまいさが論じられるようになったが、ベンチャービジネスは、家産を運用する非資本、資本、土地所有者としての性質が混在する。またさらに、知識の所有とは何か、つまりたとえば音楽CDを買った場合、それは音楽を買っているわけではなく、CDという道具を使って音楽の利用権を借りていることになる。では、ストリーミングのサブスクリプションではどうなるのか? 詳しいことは後の投稿で紹介する。
身近なことから資本主義の変化への疑問は多様に広がっていく。他方で、格差や貧困をもたらす資本主義の問題をもっと考えるべき、という意見もある。
いずれにしても、現代経済は資本主義であり、資本主義の原理としての経済学原理論から現代をみる切り口は数多くある。論文には収まりきらないものを別の形で記しておきたい。
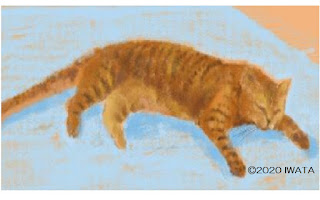

コメント
コメントを投稿