注目
泉正樹「価値形態と現代の不換銀行券制度」(『マルクス経済学―市場理論の構造と転回』第4章)についての研究会
この記事は研究会を通じて考えたことを書いています。表記の論文の内容を知りたい人は本を買って読んでください。
表記の本は今年(2021年)3月出版だが、執筆者の一人の話では、「この本は入稿が2年くらい前なので、現在の自分の考えとはずれているところもある。もちろん、執筆者によっていろいろ事情は異なるだろうが」とのことだ。
ということで、今回の研究会の議論について、泉氏自身の現在の考えは今後、氏の研究論文になるかもしれないのでここではふれない。そのため、この論文の本旨とは異なるが、研究会で議論になったことから私が考えたことを以下に書いておく。
論文の内容を簡単に
論文の構成は、まず1節「資本主義の転換期と通貨制度の変化」では、物価変動や貨幣制度の歴史を追って、貨幣が金から乖離してきたことを記述している。理論的にはあまり論じるところではなく、前提知識のようなものだ。
次に2節「不換銀行券論争を振り返る」として、兌換停止後の諸説を、岡橋保、麓健一、川合一郎、金井雄一、山口重克らの説を検討する。岡橋、川合、金井らは、兌換停止になっても、与信で貨幣が発行される信用貨幣ということでは不変、という説だ。兌換の時代にも実際には兌換を請求されることは少ないという、金井のような主張もあるが、兌換が少ないということと、兌換債務そのものを停止することとは別問題だ。《与信で作られるものが貨幣だ》という信用貨幣論に対する山口による反論《与信以前に貨幣の概念が必要になる。与信で作られるものが貨幣というだけでは循環論法だ》でこの節はまとめられる。
第3節「価値形態と現代の不換銀行制度」はこの論文のメインになる。マルクス『資本論』の論述によって、商品に内在する価値の問題を設定する。商品に内在する価値は外部に表現されなければならない。従来から説かれてきたように、多くの商品所有者から自身の商品の価値の表現の素材として特定の商品種が選ばれれば、価値表現としては一般的価値形態になり、その素材は一般的等価物となる。一般的等価形態が固定すれば貨幣形態となり、表現に用いられる素材は貨幣となる。
しかしこのように特定の素材が選ばれる従来の方式では、金貨幣と兌換銀行券しか発生せず、兌換を停止して不換銀行券になれば商品価値の根拠を喪失する。
それに対してこの論文の主張は、貨幣形態に至る一般的価値形態には二つの方式がある、というものだ。二つのうち一つは従来の形である。もう一つがこの論文の核心で、商品世界を構成するあらゆる商品を収蔵するルーレットの円盤とか一覧表(リスト)のようなものを想定し、諸商品に内在する「価値」の在り方がXを用いて示されることで、Xを等価形態に置く形で統一される、とする。この方式は従来の方式とは異なり、特定の商品種に帰着できなことが要点だ。次の図は報告に基づいて岩田が作成。
議論の内容
研究会の討論ではこのルーレットXについて議論が多くなされた。議論は結局、ルーレットXでは「○○量の商品A = △△量のX」という価値形態にならない、という問題に至る。
Xは論証されたものではなく、こういうものが存在してほしいという著者の願望のようにみえる。あるいは論理展開の代わりに比喩を用いて価値形態に置き換えるのかもしれない。しかし、いずれにしても先の述べたように、この論文は少し前のものなのでさらに論考が進んでいるだろう。そのためには、まずはこの論文を読んで、次の議論に備えるべきだろう。
その他のテーマ
本論文の主旨からは外れるものもあるが、他の議論のテーマとしては以下のようなものがあった。なお、この研究会は原理論の専門家だけでなく、現状分析や思想系、学部生なども含むので、議論も幅広い。それらのテーマについて私が今の時点で考えると次のようになる。
①著者の執筆者の一人である『これからの経済原論』の価値形態論とこの論文はかなり異なるが整合性はどうなのか?
とくに、商品集積体の概念が『これからの経済原論』では複数の商品がandの形でつながる商品セットだが、この論文では、個別の商品が単独でXによって価値表現するorの関係になっている。orの関係に基づく商品集積体は以前の記事で書いた。また、小幡[2013]『価値論批判』98頁の「商品券」はorの関係である。
②原理論が想定している主体概念がよくわからない。
古くは資本の人格化といわれていた。その後、とくに山口『経済原論講義』では出発点に市場経済的利得の最大化を求める主体、と設定された。
私はさらに進めて、例えば価値形態論では、「価値表現を行う主体(相対的価値形態の所有の所有者)が所有する商品が交換を求める商品と、すぐには交換に供されない商品から構成される」というように、前提を緻密にすることが必要だと思う。これは「行く先論アプローチ」で「本質論としての原理論」を説く方法に対して、「行動論的アプローチ」によって「分析基準としての原理論」を構成していく場合に必要になる。つまり、行動論的アプローチでは、論理において経済主体が行動するためには、主体における前提を決めておかなければ行動しようがない。あるいはなんでもできてしまう。
第2篇の労働や、第3篇の市場機構(市場組織)などでも、主体の行動を想定するための前提を緻密にしておく必要がある。従来の原理論では、常識的な市場観や、なんとなく19世紀のイギリスの現実を前提にしている可能性がある。
そもそも「不換紙幣」の定義は何か? という議論があった。
これは思考実験として貨幣のない世界でポイントが貨幣になるとしたら、と流れで出てきた疑問だ。たとえばビックカメラのポイントは、発行者の債務であり、ビックカメラが保有する複数の商品から選べる。このポイントがビックカメラへの債務履行請求ではなく、第3者への支払いに用いられれば貨幣になる。しかし、ビックカメラへの債務履行請求に用いることも可能である。
今から私が考えると、不換紙幣とは、「素材それ自体の価値は額面の価値よりも明らかに小さく、額面の価値のある商品への交換の債務を発行者が負っていないモノが貨幣として流通する」となる。しかしよく考えると素材は「紙」でなくてもいいので、問題は不換紙幣ではなく「不換通貨」となりそうだ。
ついでに一言、『資本論』に出てくる「マダム・クイックリ」の意味をはじめて知った。
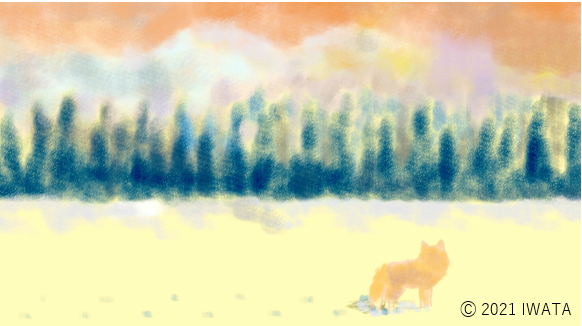


コメント
コメントを投稿