注目
続・orの関係の商品集合体と信用論を用いて信用貨幣の発生を説く新しい価値形態論
前回の記事で「F.この次に必要なこと」について、論旨にかかわる点について補足する。
ⅴ)相対的価値形態の商品所有者の主観からの再構成について。もともとリンネル所有者は以下の価値表現を行う。
リンネル20ヤール = 1着の上衣
しかし、欲求の正反対での一致がないので、間接交換として、他の商品で価値表現を行う。ここでは2つの価値表現が行われている。
㋓ リンネル20ヤール = 茶4kgの債権
㋔ 茶4kgの債権 = 1着の上衣 これはもう、貨幣による上衣の購入。
茶の債権が貨幣になれば、㋔の価値形態はもはや価値表現ではなく、貨幣による商品の購買になる。
宇野の方法では、上衣の位置にある商品が貨幣になる。
ここで話をもどして、新しい価値形態論の方法をリンネル所有者の主観で再構成すると、
㋓リンネル20ヤールの価値を、「Xが茶4kgを引き渡すという債権」で表現する。
㋔「Xが茶4kgを引き渡すという債権」の価値を上衣1着で表現する。
その際、「Xが茶4kgを引き渡すという債権」は、Xが保有する他の商品の請求債権と転換可能性を含む。次に、
ⅰ)「価値表現の媒介として多数の債権債務関係が同じ量の価値量で創出される」という特殊な想定の解除し、一般化する問題。
この問題は、リンネル所有者が、リンネルを多数の商品で価値表現することで解決する。たとえば、リンネル所有者が以下の価値表現を行えば、
Xの債務における商品の単位量当たりの価値量は以下のようになる。
上衣1着:茶1kg:鉄1トン:小麦1kg = 1:0.25:2
これはリンネル所有者の主観の世界に立ち返れば、「Xが茶4kgを引き渡すという債権」は、X
が鉄の受取債権を0.5kg以上保有していることを想定したうえで、価値量としては「Xが鉄0.5kgを引き渡すという債権」に転換可能ということを意味する。
そうすると、Xの債務の構成要素がすべて同じ価値量でなくても、リンネル所有者のように最初に相対的価値形態に置いた商品の所有者による展開された価値形態によって、債務の構成要素は量的関係を示すことができる。
|
資産 |
負債 |
|
αA1量の商品WA1の受取債権 |
αB1量の商品WB1の受取債権 |
|
αA2量の商品WA2の受取債権 |
αB2量の商品WB2の受取債権 |
|
αA3量の商品WA3の受取債権 |
αB3量の商品WB3の受取債権 |
|
… |
… |
|
αA4量の商品WAnの受取債権 |
αB4量の商品WBnの受取債権 |
たとえば、WA1を最初に相対的価値形態に置いたWA1の商品所有者の展開された価値形態で、商品WB1と商品WB2の価値量の比率がx : yであれば、
αB2量の商品WB2の受取債権の価値量は、WB1の1単位の価値量を用いて以下のように示される。
(y / x) ・αB2・WB1
こうすることで、Xの債権債務に並べられた諸商品の価値量の関係において、特殊な想定をせずに一般化できる。ただし、もちろんこれは、リンネルのように、最初に相対的価値形態に自分の商品を置いた商品所有者の主観的な比率にすぎない。価値量に客観性が与えられるのは、原理論体系では価値形態論の次の「貨幣」の項における、貨幣による商品の購買という価値尺度機能である。これは、これまでの価値形態論でも共通する前提である。
先ほど、Xにおける他の商品債務を、WB1を基準にして表現した。多数の商品の中で何が基準になるかは根拠がない。既存の価値形態論の論理を使って「多数の人々が基準としても用いる商品が基準となる」としてみよう。そうすると便利なことが起きる。それは、WB1が存在しなくとも、計算貨幣、あるいは楊枝嗣朗氏の「イマジナリーマネー」が現れることである。
Xに対する債権が貨幣となり、その単位がWB1という実在する商品で示されたとしても、実際の売買にはWB1の実在は不要である。ではXに対する債権としての貨幣には意味がないかといえばそうではなく、Xの保有する商品受取債権に価値の根拠がある。
こうしてXに対する債権は、商品価値の裏付けを持ち、特定の商品との交換を義務付けられない信用貨幣としての商品貨幣となる。さらにその計算単位は特定の商品の物量となるが、観念的な存在として貨幣として機能し、貨幣の計算単位、あるいはイマジナリーマネーとなる。
前回の記事の「F.この次に必要なこと」に挙げた他の項目は、派生的なものなので今回は取り上げない。ただし、もう一つ問題点を追加すると、
ⅵ)Xの実存性をどこまでとして設定するか。最初に相対的価値形態においた商品の所有者の主観として押し通すか、Xの実存性を想定するか。また、Xの実存性を想定するにしてもどのくらい抽象的な存在とするか、といった問題である。
信用貨幣は債権債務関係で成立し、発行者の負債だとすれば、Xの実存性を否定するのは困難で、問題はどこまで抽象的に説くか、ということになる。
(終わり)
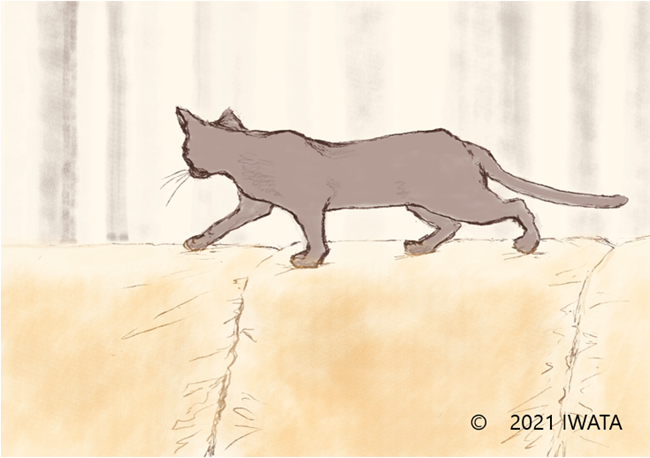




コメント
コメントを投稿