注目
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
「労働概念の拡張」を読むための若干の整理と前提
東京経済大学学術フォーラム「マルクス経済学の現代的スタンダードを語る 」報告内容の事前学習を大学院と学部のゼミで始めている。労働の報告で学生がひっかかる点がいくつかあったので、ここで整理や前提を書いておく。おそらく、報告者は「それは全然、違う」と言いそうだが、とりあえず気にしないでおく。
まず、マルクス経済学では、労働は人間の目的意識的な活動と定義する。
労働と言えば、賃金と引き換えに他者の指示に服する行為、と思ってしまう人もいるが、それは労働の中でも賃金労働の説明である。さらに言えば賃金労働であったとしても、一から十まですべて指示された通りに動くのではなく、労働者の目的意識的な活動として行われる。この点はマルクス『資本論』が、ミツバチの本能的行動に対する、人間労働の特徴を説明しているところが有名であり、それが労働過程論のすべてになっていた。
しかし、目的意識だけでは労働過程の中身が空虚であり、労働概念をそれだけではなく拡張すべき、と提起されている。
「労働」のコア概念から基本相への変容
「労働」のコア定義と、拡張された3つの基本相の関係は以下のようになっている。
かつてブレイヴァマンが述べた、有名な「構想と実行の分離」説では、賃金労働者は、資本家による構想が与えられ、それに基づいて実行する。しかしよく考えれば正しくないことがわかる。なぜなら、実行の中にも 構想の要素が含まれて いるからだ。
まず、与えられた指示の内容そのものを自分が理解するは目的設定である。そこに構想の要素が含まれる。同一人物でなければ他人の構想を自分の構想に取り入れるにも労働が必要である。これは目的設定になる。
次にその指示が どうやったら実現できるのかという方法について手段の組合せや順序を構想することが必要である。最も単純に考えても、労働者がどういう動きをすればよいか、逐一、指示されるわけではない。身体の動かし方、道具の使い方、さらに道具のそろえ方などを労働者が構想する労働が必要になる。これが手段設計になる。
さらにそれを実行するときには自然過程の逐次的なコントロールを行うが、その際に自然過程が意図した方向に進むように、状況を理解し、それに応じて必要なコントロールを構想しなければならない。
このように考えると「構想と実行の分離」説は、労働概念を狭く誤らせていることがわかる。
こうして、労働はコア定義として「目的意識的に欲求を充足する活動」とされ、次に「目的設定」「手段設計」「逐次制御」の3つの相として現れる。
20世紀の機械化の発展は、たしかにブレイヴァマンの「構想と実行の分離」説が説得力を持つように見えるかもしれない。「目的設定」「手段設計」が相対的に小さくなり、逆に「逐次制御」が相対的に大きくなった。これが操縦型の労働と言われるものである。しかし3つの相いずれにおいても労働者に構想がなくなった方言えばそうではない。
21世紀の現代においてはAIによる自動化が進むと、「逐次制御」における労働が減少する。つまりクリック操作でその先は機械が行う、という場面が増える。「構想と実行の分離」説に過剰に寄りかかって、20世紀に大きく発展した機械操縦型の「逐次制御」の相の労働こそが労働だと思い込んでいると、まるで労働がこの世から消えたように見える。しかし実際に起きているのは、「逐次制御」が相対的に小さくなったが、逆に「目的設定」「手段設計」が相対的に大きくなっている。
AIの自動化による労働の消滅化のように見える事態は、じつは、労働における3つの相の強弱の違いの変化ということになりそうだ。変化というとこれが「労働の変容」のように思えるが、「変容論的アプローチ」では「変容」という語を独特の意味で使う。
「変容」の意味
「変容」というと、歴史的な変化や、業種や地理的条件、あるいは社会文化によって異なる違いなどが思い浮かぶが、ここではそういう意味ではない。ここで前提にされている「変容論的アプローチ」では、変容とは、抽象度の高い概念がより抽象度が低く具体的な概念になるときに複数の形に分かれることである。貨幣についての変容は以前の記事で紹介した。それに合わせると次のようになりそうに思える。
そして歴史的な変化は、「発展」historical developmentと呼ばれる。
多態化の枠はいろいろ書けそうだが、とりあえず???としておく。
「発展」(歴史的変化)は3つの基本層それぞれの強弱によって考えることができそうだ。この強弱による変化を以前、泉正樹氏は「分流」と表現していた(泉[2021]「資本主義の歴史的発展と経済原論:『変容論的アプローチ』からの展開」)が、今回の学術フォーラムの報告資料では「分流」という方法は使っていないようだ。
理論的にはまず、「変容」としてコア概念が分岐することを明確にする必要があるが、分流はその分岐をあいまいにする危険があるのかもしれない。いずれにしても、まずは3つの基本相の中身を論じることが必要だろう。
「オブジェクト」
労働は「目的設定」「手段設計」「逐次制御」という三つの基本相をもったオブジェクトになると説明されている。オブジェクトを「対象」と考えると訳が分からなくなる。そういう意味ではなく、ここで「オブジェクト」とはプログラミング言語でいうところの「オブジェクト指向」のオブジェクトである。(小幡「熟練内包的労働の一般概念:オブジェクトとしての労働」32頁)
複数の属性(プロパティ)を振舞い方(メソッド)で関連づけたセットをオブジェクトという(らしい)。
この先は、報告資料をしっかり読んで学習してください。
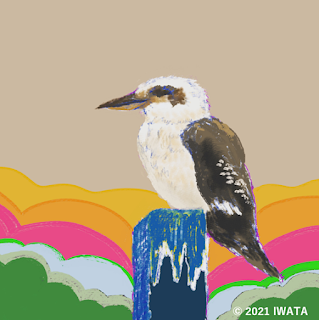



コメント
コメントを投稿