注目
商業資本における変容論的アプローチ
商業資本の分化・発生の概観
原初的な産業資本は確定的な生産過程と不確定な流通過程を持つが、確定的な生産過程を維持しながら不確定な流通過程に対処することには困難があり、不確定な流通過程を専門的に担う商業資本が分化する。図解すると次のようになる。
![]()
ここで産業資本の利潤の一部が商業資本に移譲される。その仕組みは次のようになる。
産業資本は商業資本に対して通常の販売価格よりも低い価格で売渡し、商業資本は通常の販売価格で販売するのでその差額が商業資本にとっての粗利潤となる。
こうして産業資本は純利潤率を高める可能性がある。といっても厳密に考えれば、不確定な流通過程への対処の費用は不確定なので、その額は事前にはわからない、事後でもその額には客観的根拠はないのだから、分化と分化後について淳利潤率の大小を比較することができない。そのため産業資本にとっての目的は純利潤率を高めるというよりも不確定な要素を排除して、確定的な生産過程の継続性を維持すること自体に目的があると考えるべきであろう。
商業資本がいつでも商品を買い取ってくれるとわかっていれば産業資本は流通過程への負担つまり流通資本と流通費用を削減することができる。
商業資本の矛盾
しかしここには「押し戻し」と言われてきた問題がある。商業資本の特性は①多数の産業資本から買い取ることで流通資本と流通費用を節約できるとともに、②「変わり身のはやさ」として、取り扱う商品の種類や量を頻繁に変更するという特性がある。この変わり身のはやさあれば、産業資本にとっては買い取ってもらえるという保証は存在しないので、産業資本は流通過程の負担を解除することができない。
「組織化」論
ここから「組織化」の議論が発展した。つまり、商業資本は産業資本から継続的あるいは大量に買い取るという将来にわたる約束をすることで初めて、産業資本は流通過程の負担を解除できるというものである。このように産業資本と密着に組織的関係を持つ商業資本の他に、変わり身のはやさを全面的に生かして機会主義的なスポット買取をしたり、過剰な在庫で窮迫した産業資本から大幅値引きで買い取りをしたりする商業資本も想定される。これで商業資本の2類型が現れる。
しかし、しかしここで疑問が残るのは
ⓐ産業資本に流通資本が残るという中途半端さがある。(産業資本に在庫があることが想定されている)
ⓑ現実の商業機構の変化として、大規模産業資本を起点とした中小商業資本に対する流通系列化と、大規模商業資本を起点とした製版統合を分析できない。
もちろんこの矛盾はもともと原初産業資本の内的な矛盾が根拠になっている。商業資本が分化した後では産業資本と商業資本との間の外的な矛盾となって現れる。
こうした商業資本の組織化論を原理論体系にまとめた「さくら『原論』」では、継続的大量買取の契約とともに契約打ち切りのオプションを含む形にして、組織化と変わり身のはやさを両立させようとしている(186-187)。しかしこれは現実に存在するものはすべて中間、としてグレーに塗りつぶす発想と似ている。
現実を中間とする前に、2つ(複数)のタイプを明確に切り出すことを考えてみよう。
変容論的アプローチ
生産過程と流通過程を共に担う原初的な産業資本が分化するとすれば、いったん、流通資本を全く持たない産業資本を想定する必要がある。
そして、一方の極に永久に継続的で、生産物を買い取る大量買取という商業資本がある。この商業資本は実は、原初的な産業資本の流通資本と同じものになる。但し多数の産業資本から買い取るという意味で多数の産業資本の共同の流通資本の役割を成す。
これと完全に対極の商業資本は単品のスポット買取になる。ただそれは最終的な買い手の買取代行になる。不確定な流通過程における在庫保有のリスクを引き受けるということが商業資本の利潤の源泉であるとすれば、単品スポット買取というのは極限的な姿でしかなく、ある程度の量を買い取るということになろう。「組織化」では、継続的大量買取の契約がなければ産業資本は流通過程を解除できないと言うが、必ずしもそうではない。商業資本は在庫商品を買い取らなければ事業活動ができないわけだから、多数の商業資本が存在していれば産業資本から買い取ろうという動きが多数発生する。継続的大量買取がなくても次々と売れていくということはありうる。そうすると産業資本にとっては生産した商品が常に売れるという想定になり、流通過程の不確定性がなくなったかのように見えるが、それは商業資本がすべて引き受けているわけであって全体としては流通過程の不確定性は存在している。言ってみれば、原初的な産業資本にとっては生産過程から出てきた商品はすべて自身の流通資本に納品されるので生産過程だけから見れば、流通過程の不確定性は存在しない、ということと同じ現象になる。この二つの極を図解すると以下のようになる。
これまでの「組織化」論は「多態化」のレベルで③と④の分類をしていた、あるいは③と④の性質が1つの商業資本の中でどのようにあらわれるか、ということを契約打切のオプションを含む継続・大量買取契約という形で論じていたように見える。多態化の形で現象する商業資本の規定には、変容のレベルで抽象的に「変容」として論じる必要がある。
念のために変容論的アプローチとは、①から②に変化する、という意味ではなく、①や②についてさらに抽象度を高めた「展開」のレベルにある「流通資本の自立化」という抽象的な概念が、①あるいは②のようにもっと具体的な形に変容して現れるという意味である。
「組織化」論への疑問についてⓐは変容論アプローチで解決できる。もう一つのⓑについては以下のように考えられる。まず前提として「流通系列化」は19世紀末から始まる大規模な産業資本を基軸にした組織化の時代の特徴であり、製版統合は1980年代を画期とする新自由主義の時代の特徴である。
流通系列化は③だとすぐにわかる。しかし製版統合は④かといえばそうではなく、これも③である。コンビニ本部が独自の商品を企画する場合には産業資本(工場)に大量・継続買取を保障しなければならない。SPA(製造小売)も同じである。
両者の違いはまず起点が異なる。流通系列化は大規模産業資本が起点であり、製版統合は大規模小売商業資本が起点である。しかし起点の違いだけでは充分な説明にはならない。たとえば、かつてのアメリカの通販販売大手シアーズは独自に生産過程を編成し、家電を含む独自のブランドを多数展開した。19世紀末から始まり組織化の時代に大いに繁栄したが、新自由主義の時代に凋落する。日本では総合量販店(総合スーパー:GMS)のダイエーが1960年代からプライベートブランドで生産過程を編成したが、バブル崩壊後の90年代不況の中で凋落する。これらの凋落の理由にはいろいろあるだろうが、新自由主義の時代の製版統合との違いでは、大規模商業資本が商品の単品管理と大量販売を前提にして、生産過程の関与の増加である。しかも単に工場から買い取るだけではなく、生産する商品の種類と量を最終販売の論理に合わせて変更させるということである。これは生産過程を不断に変更させる技術的な条件が必要となる。
つまり、流通系列化と製販統合はともに③でありながら何が違うのかといえば、生産過程の安定的な継続性を、流通過程は前提として受け止めるに対して、製版統合は生産過程の継続性を自身の都合のいい形で変更させるということである。これまでの原理論体系では現代宇野理論も含めて、生産過程の安定的な継続性から商業資本を論じる。そのため③では流通系列化しか思いうかばない。しかしここではもう1歩踏み込んで商業資本による生産過程の変更を論じる必要がある。つまりもう一つ別の「変容」を説く必要がある。以下は形式的だが、作業仮説として変容の図式を挙げる。
いったんこのように仮説を作っておく。
継続・大量買取を前提としたうえで、⑤と⑥がある。原理論では⑤の理解は容易だが、⑥はありうるのか、検討が必要だ。
これらの問題は以前、「経済学原理論における「市場機構」と「市場組織」 : 流通過程の不確定性と利潤率均等化の観点から」と「商業機構における多型的展開 : 原理論と段階論からの検討」(いずれもこのWebページを参照)で取り扱って扱っていたのだが、変容論的アプローチを意識していなかった。そのため、今回の記事ではそのアプローチで整理してみた。
変容論的アプローチの再考
今回の記事で使った変容論的アプローチは、その提唱者の小幡氏の方法とは異なるところがある。山口重克の「ブラックボックス論」あるいは「本質規定と分析基準」の方法に近いところもある。この問題は今後の記事で取り上げる。
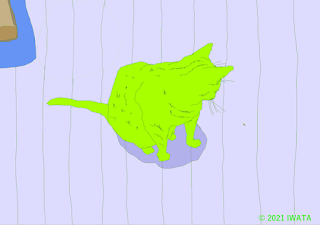





コメント
コメントを投稿