注目
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
「マルクス経済学の現代的スタンダードを語る」の「労働概念の拡張」報告の文字起こし
昨年10月23日の「マルクス経済学の現代的スタンダードを語る」(東京経済大学術フォーラム)の企画の全内容は、ワーキングペーパーとして出版される予定で、現在作業中。
文字起こしは業者(コエラボ)で「整文」で依頼した。一見、きれいに文章になっているようだが、よく読むと、やはりそれだけではわからない。
今回は第3報告の報告部分を掲載する。この報告については、報告者ご本人が手入れをしそうにないので、代わりに私(岩田)がかなり手を入れた。さらに変更する可能性もある。私(岩田)が手を入れた結果、報告者の意図とは異なるものになる危惧もあるかもしれないが、幸いなことに報告のための事前資料がウェブにあるので、それと参照すれば、問題があったとしても解決可能だろう。なお、以下の文字起こしに間違いや不明な点があればお知らせいただきたい。今回は報告部分だけで、討論は今後、掲載する。
報告者:小幡道昭(東京大学名誉教授・東京理科大学非常勤講師)
小幡です。本日の報告は「労働概念の拡張」という話をしようと思います。
ここをクリックすると、これから話をするところのページに入ります。何段階かあります。1ページ戻ってもらうと、このページの下のほうに岩田さんのブログの記事があったので、先ほど少し見ました。そうすると、ここに丁寧に労働概念の拡張を読むための若干の整理と前提があります。岩田さんが随分と丁寧に解説されているのを見て、こういうものがあると便利だと思いました。みなさんもご覧になるといいと思います。といっても、本人はそれほど難しい話をする気は全くありません。このページは私のブログですが、大体はそこに書いてある内容を話していきます。
目次を開くと、本日の話の概要のようなものが書いてあります。最初にこれまでの労働概念ということで1、2とあります。労働のコア概念を3で話をするということで、できるだけここでいうと3のコア概念の話と拡張の話、3、4の話をしていきたいと思っています。時間も限られているので、できるだけ手短にしたいと思います。少し恥ずかしいですが、このブログのページは、みなさんに話すことを想定して、わざわざですます調で書いているので、そのまま読んでもらえるといいという感じです。こちらを書くときはみなさんに話すことを前提にして書いてみました。
初めに、突然ですが、人工知能の発達でいよいよ労働が要らなくなる、こういうセンセーショナルな報道はよく目にすると思います。私も本当にそうなるのかと、よく尋ねられます。労働の姿が仮に変わらないとすれば、変わらない労働は姿を消すのは当然です。しかし、労働はその姿を変えます。そうすると、姿が変わるものがなくなるかどうかということは途端に難しい問題になります。姿が変わるものがなくなるかどうかです。変わるということは結構、考えてみても難しい概念です。
そういう中で目につく現象を追いかけ回す、新しいもの好きの人たちは、右から見てはなくなると言い、左から見てはなくならないと言い、右往左往するばかりです。こうした混乱は、労働はどう変わり得るのかということです。逆に理論的に言えることは、どう変わり得ないかという否定形のほうだと思います。そのようなことが書かれるような、新しい経済原論を組み立てることで、初めて学問的に解決できる問題だと思っています。
こう言うと、そのような理論は本当にできるのかという声があちらこちらから聞こえてきそうです。理論は変わらない法則を対象にするものだと信じているのでしょう。とはいえ、こういう信じている方々と、信念の次元でいくら議論をしても抽象的な方法論、一般の問題のようになって時間の無駄ということで、ここではとにかくできるかできないか、実際に試してみたいと思います。
第2節です。これまでの労働概念です。格好をつけて労働価値説から始めています。初めに断っておきますが、ここで今は変わることが難しいと言った「変わる」というのは、もちろん価格が変わるような個々の様子、要因の変化ではありません。価格の変化を支える基盤となっている、市場の構造が変わるという意味での「変わる」です。こういう構造変化を個々の要素、要因の変化と区別して「変容」と呼んでいます。
さて、この構造が変わるという変容の問題を考えようとするとき、マルクス経済学は強力なパワーを発揮します。とはいえ、この力は潜在的なパワーの話で、進化を引き出すには何層にも降り積もった固定観念を打ち破る覚悟、『資本論』に書いてあることでも正面からもう一度疑ってかかる気概が必要です。これから考えようとしている、労働の場合は特にそうです。
マルクス経済学では、伝統的に労働は常に労働価値説に縛り付けられてきました。ただ、労働価値説に関しては、解かれるべき問題は既に解かれたと私は考えています。こう言うとたちまち異論百出で、収拾がつかなくなりますが、本日はこの話はしません。しませんと言うことに迷い気味です。詳しくは「マルクス経済学を組み立てる」をご覧ください。これは2016年の春に、元の大学を辞めるときに最後の置き土産的に書いた論文です。ここに組み立てるという話で取り組んでいました。長い間いた大学でしたが、近代経済学の人たちと自分の立場をはっきりとさせるようなつもりで書いた論文があります。基本問題は解決されたという意味の話はそこに書いておきました。簡単にそこの内容を振り返ってもいいですが、ここを話していると時間がかかるので、ここを飛ばして本題に入りたいと思います。
ただ、少しだけ言っておくと、例えば労働価値説に縛り付けられたということに、私は労働価値説について、商品を生産するのに必要な労働時間が計算できるという話と、その労働時間が価値を規定するという話は分けるべきです。私は前半の労働時間を考えていくことの意味は重要だと思います。しかし、そのことを言うためには、実は労働に対してとても強い制約をかけておかないと、もともと無理なところがあります。そのような制約をかけて初めて投下労働時間(スモールt )をしめすことができます。つまり1商品を直接、間接に生産するのに必要な労働時間の決定はできるのかということで、そのためには明示的にいくつか条件をはっきりとさせる必要があります。
その条件とは例えば技能の問題についていえば、「技能なき労働」、技能の熟練を同じ意味で使うとすると、そういう労働を想定しておくことが必要です。次に「手段なき労働」についてです。手段があっても、それによって異質にならないような労働という意味です。そういうものを想定していくことが必要です。これは考えると、結構、いろいろと根が深い問題です。2番目はそういう条件です。
3番目は「結合なき労働」です。簡単に言うと、協業や分業をしても変わるところがありません。n人であればn倍をすればいいと想定しておかないと、労働時間の集計はもともとできません。n人であれば1人のn倍の労働が可能になる、そういう想定をしっかりと置いておかなければいけないというようなことがあります。挙げていくと、まだ技能なき労働や手段なき労働や結合なき労働、こういうものをしっかりと想定しておかなければいけないと思います。
こういういくつかの想定をしておいて、次に2.2の理論空間の話です。この部分は報告資料(ウェブサイト)を読んでおきます。次の2点がここまでの結論です。①『資本論』第1部の骨格をなす剰余価値論と蓄積論において、その量的分析に投下労働時間を用いることは有効である。ただ、このことは商品が投下労働時間に比例した価格で売買されるという命題、本来の労働価値説、あるいは労働力商品が他の商品と同じく、その生産に直接間接に必要な労働時間によって売買されることです。労働力の価値規定と言われているものですが、そのような命題、本来の搾取論を必要とするものではないと思います。それが第1の結論です。
②2番目の結論は、『資本論』における労働の変容を捉えるには、労働概念をこの前提の枠に無理に押し込めず、より一般的な内容に拡張する必要があります。その話は報告資料の上のほうにそれをたくさん、省いた形で書いておきました。
この2番目が本日の話の出発点です。無理に労働価値説のための労働概念に押し込めずに、より一般的な内容に拡張することです。ただし、労働が変わるという問題に興味がない人にとっては全く意味がないでしょうが、しかし理論的な問題であれ、現実理論の外の問題としてでも関心があれば、チャレンジしてみる意味があるでしょう。
ここで理論の構成の仕方についてです。よく方法と言いますが、理論の方法といっても、その理論を現実にどう適用するかについて、例えば段階論でします、とか、直接適用します、といったようなさまざまな言い方で、出てきた理論を現実に適用する方法です。大体は宇野弘蔵の経済学方法論というときの方法論は適用方法ですが、それとは別に理論にはもちろん展開方法があって、これをどのようにするかです。例えば分化発生論を軸でするように、そういう多様な展開方法についての問題を考えるときに、どのような方法を使えばいいのかについてです。
少しだけコメントしておくと、ポイントは2で概念を拡張したからといって、現実と変わる労働に関心があって、それを明らかにする理論をつくろうと思って、2番目のところで概念を拡張したからといって、直ちに単純化された①の前提を変更する必要はないという点です。
両者は異なる課題を解明する相対的に独立した理論空間を構成し、おのおのの理論空間に属する前提や基本概念は、それに応じてそれぞれ固有の特性を付与されます。ここの理論空間というのは、一定の基本課題を解明するために、一群の諸前提を基礎に構成された演繹体系のことで、個々の理論空間は相互の関連を明確にすることで、上位の理論空間のサブ空間として位置付けられます。少し難しく言ってしまいましたが、理論空間の種明かしをすると、最近のコンピュータのプログラムを書くときに、ネームスペースという名前空間をよく使います。その考え方そのものですが、そういう空間をそれぞれに設定して、その関係を考えていく形です。複雑な大きなプログラムを書くときは、そういう整理をする方法を使います。
考えてみると、経済原論のテキストは昔から編、章、節等の編別構成に基づく形になっていますが、あえて理論空間と言う狙いは、編、章、節ごとにもう少し隠された諸前提を示して、その関係を明らかにしていこうという点にあります。同じ物理学といっても、ニュートン力学と相対性理論、あるいは地球物理学と宇宙物理学では、それぞれ異なる理論空間を構成しています。例えばそのように考えてみます。
地球という同名の個別要素であっても、それぞれの理論空間に属する要素として、その形で比較検討されると、地球一般として同じ物理学の中に置くのではなくて、地球物理学というネームスペースの中で、地球物理学の地球と普通は言います。そういうスペースをつくっていくことが大事です。これは実は経済原論の編別構成でつくっている場合に当てはまると思います。
①において、投下労働時間を計算可能にするのに単純労働の仮定をするのであれば、②の労働の変容では単純労働化の深化を説くべきで、②において熟練技能を考察するのであれば、①では熟練労働の単純労働への還元を説く必要があるといった、ナイーブな思考からはそろそろ卒業するときと私は思っています。そういうことを前提にして、2.3の労働の変容に入ります。以上のように、方法論を整理することで、例えば熟練、技能は同じ意味です。次に技術です。あとは組織、労働の結合です。協業や分業等を取り込む形で労働概念を拡張し、歴史的な環境の中で、労働の姿がどのように変わっていくのかという問題に、理論のサイドから光を当てることができます。
もう一度、断っておきますが、これは経済原論で不可逆的な歴史的変化、すなわち発展が全て説明できるという意味では決してありません。原理論を現実に適用しようとすると、すぐこれを理論による決定論と解釈して、そういう理論というか昔の唯物史観のドクトリンで、歴史を無理に解釈したということは、よほどアレルギーが強いだろうと思いますが、必ず理論を現実に適用するというとお決まりの反論がきます。しかし、ここでいっているのは、歴史的発展の基礎にある分岐の可能性や構造変化の契機を示すことが、原理論でも、できるということです。
こうしたアレルギーの事情は、理論的に説明可能な貨幣は金貨幣だけである、それ以外は段階論で語るべきという主張に通じています。こう信じている人から見れば、同じく19世紀には機械制大工業が普及したのであり、こうした傾向を延長した先に想定される純粋資本主義では、単純労働以外の労働は考える必要なしということになるでしょう。この種の紋切り型の純粋資本主義と手を切り、貨幣にしても労働にしてもより抽象レベルを上げて、理論的に構造変化を考えることができる原理論を開発しようというのが変容論の狙いです。
ホームページ上でより抽象レベルを上げる、のところにカーソルを当てると、ツールチップが大量にあります。このような小細工をしてあり、ホームページを作るときはこのように結構、遊んでしまいます。
これが変容論的アプローチのポイントで抽象レベルを上げるということです。変わる現実に近づくために、変容論の「現実から遠ざかる」という逆説で、抽象レベルを上げるという形です。要するに、鳥瞰できるように距離を取って抽象レベルを上げていくこと、これが現実に適用するときの方法です。眼前の現実を説明しようとして抽象レベルを落として、生の現実を理論の言葉で語るだけの類似品に注意、ということです。
類似品は何を言っているかというと、ここだけのオフレコで言ってしまいます。昔から、私はよく純粋資本主義に対して、こういう疑問を投げかけると、世界資本主義というレッテルを貼られました。古い人は知っています。私は世界資本主義が逆に抽象レベルを下げてしまったと思います。生の現実について、19世紀のイギリスをそのまま書いてしまうと理論にはならないので、理論の言葉に翻訳して話していると勘ぐります。今、話しているのはこの辺りです。
今、話したところについてです。前項で話した理論空間の狙いは、このような狙いに応える試みでした。労働価値説あるいは客観価値説で、社会的再生産の構造や純生産物の分配を説明するには、それに応じた理論空間が必要です。理論空間は芝居でいうと、書き割り、backdropのようなもので、どの幕にもそれにふさわしい背景があります。剰余価値論という第1幕では適切な書き割りで、解くべき問題をしっかりと解くべきです。
しかし、それが労働に関して考えるべき問題の全てではありません。働くとはそもそもどういうことなのか、それがどのような姿をしているのか、そして今はどのような姿に変えようとしているのかについてです。このような問題を考えるには新しい書き割りを設定することが、これからは必要になってきます。演じる役者は同じ労働でも、舞台が変われば役割も変わり、演じ方も変わってきます。
これぐらいの柔軟さを原論体系全般に埋め込んでいかないと、とても窮屈な原論になってしまうと思います。理論は同じ平面の上で一部の隙間もない理論なのだから演繹的に少しでも前提が動いてはいけない、というような平板な理論を演出する必要は、今はないだろうと思います。この辺りはかなり用心して書かなければいけません。信用貨幣型の貨幣を説いているうちに、いつの間にか信用論までもっていってしまうことや、丸ごと信用論を先取りするようなことに、どうしてもなってしまいかねません。方法論は結構、大事というか、用心する必要があると思います。
次に2.4「「労働過程」の盲点」です。これは先ほど話したことです。このような観点から振り返ってみると、『資本論』第1部の労働過程は確かに独特な意味をもっていると思います。読んでいることを前提に話をしてしまいます。『資本論』第1部、第5章第1節、労働過程です。人間の労働はどのような姿をしているかという話を、非常に一般的に抽象的に話している節があります。
この節は、労働価値説に基づく搾取論に対して、冒頭からずっと商品の価値規定を労働に基づいてするとしてきた中で、一風違う趣を確かに帯びています。そこでは価値を形成する労働、商品に対象化された労働という一連の議論からいったん離れて、人間の活動を特徴付けるものとして労働なるもの一般の性質が論じられています。
宇野弘蔵がここを非常に拡張しました。先ほど『資本論』を正面から疑ってかかる覚悟が必要であると言いましたが、それはここからです。新たな労働が変わるという話をするときに、この労働過程は確かによくできていて新しい視点ですが、しかしこれで良いのかというとそうはいきません。よくみなさんがご存じのように、ミツバチの活動と人間の労働を比べて印象深く読むことができるところです。他は難しくてもここは読みやすいと言う人も多いです。この書き割りの下で労働概念を書きつぶしていけばよさそうに見えますが、これには落とし穴があります。
研究者相手に何かをするときは、この辺りについてこのように言うときは、相当にしっかりとした解釈をして、どこに盲点があるということを示さなければいけません。それは部分的にですが、今日の他の報告でもみなさんがよく挙げていた経済理論学会の雑誌『季刊経済理論』に以前、書いたことがあります(「熟練内包的労働の一般概念:オブジェクトとしての労働」)。これをクリックすると現れます。熟練内包的労働の一般概念、オブジェクトとしての労働という難しめのタイトルを付けてしまいましたが、これが載っているのでのぞいてみてもらうといいと思います。これは以前に書いた話を、ブログのここに書いてみました。
少し難しいタイトルですが、中身がごく単純な話です。労働過程のところに戻って、熟練とは何かを考えてみようということです。当たり前のことですが、これがなかなかできない仕掛けになっています。考えればいいでしょうとなりますが、そうすると他のところとの関係が一気にさまざまな問題を起こしてしまうような形になっています。『資本論』のテキストを批判しながら話しました。結論だけ少し言います。この辺りから三つほどウェブの報告資料を読んでみます。
まず「意志と身体の未分離」です。それから、「手段の欠落」、「他者の不在」です。2番目、3番目が先ほど上のほうで述べた三つの話と大体は重なります。そのような構造になっています。これも時間がかかるので今はカットします。読んでもらえると、なぜこれが盲点なのかと思うかもしれません。私はみなさんが良いと言われれば言われるほど疑いたくなります。人間の労働とミツバチの活動を比較した、あの有名な労働過程論で本当にいいのか? とても疑問になってきて、この論文を書きました。そこには先に挙げたような欠落があるのではないか、ということです。マルクスの中で労働価値説に縛られていない労働を書くには、そこしかないでしょう、と言ってそのまま受け止めると、他者の不在、など、この辺りがそのまま盲点になってしまうと書いてみました。
そういうことを踏まえて、ようやく本題です。では、労働概念はどのように拡張できるものに変えますかという話です。あとはここからです。
労働の概念です。これもいろいろと書いています。初めに労働という用語の定義として、ここでは欲求・必要を目的意識的に実現する活動と言葉を定義します。これはあくまでも用語の定義であって、考察対象に外側からラベルを貼ったにすぎません。ラベルを貼って終わりにしてしまう人も多いです。見てみると、AIというラベルを貼って中を分析しないことがあります。それは言葉の言い換え、定義を与えただけで、それから中身を詰めて概念をつくっていかなければいけません。欲求とは何なのか、目的意識的は何なのか、実現するとはどういうことか、そのような中身を分析していかないと概念にはなりませんが、なかなか概念をつくらずに定義で終わらせてしまう人も多いです。
少しだけ余計なことですが、書いたので話します。概念とはどういうものかについて話してみます。マルクス経済学では、『資本論』のBegriffの日本語訳として、概念という用語は多用されています。これの影響でみなさんもよく概念と言います。それは多分に17、18世紀のドイツ哲学をバックグラウンドにしたものになっています。経済原論では、例えば一つ一つの商品の特徴ではなく、どの商品にも当てはまる一般的な性格が対象となるので、当然、後者を意味する商品概念が中心問題になってきます。
ただ、このような概念的把握は、オブジェクトという考え方をベースにした最近のプログラム言語で、より明示的に行うことができます。ここでオブジェクトと言っているのは、属性、性格とその働き・振る舞い方、そういうものをセットにした一種の構造体です。データをどのように捉えるかというと、前はさまざまな属性だけを並べて、せいぜい配列に置くような形でしかなかったものが、その属性固有のものを捉えます。
例えばこういうオブジェクトだと、これに位置や名前や色が身体Aに付いています。属性というのは身体Aの文字です。それからこのように枠があって、位置があります。このようなものが属性で、それに応じて矢印が出ていますが、こういうファンクションが付いてきます。これがオブジェクトで中身にいくつかの属性とファンクションとメソッドが組みになっているように、最近はプログラムを書きます。概念という言葉を使ってもいいですが、こういうスタイルで中身を明示的に書くことが難しいので、私は結構、オブジェクトは使えると思っていて、実は隠れてさまざまなところで使ってきました。本日は種明かしです。
こういうオブジェクトという捉え方は、商品や貨幣をするときにそのまま当てはまると思いましたが、労働に関しても内部構造をもたない従来型の労働力という一枚岩について、中身を持たない労働力の限界を打破できるので、とても有効な方法だと思っています。
次に3.1「労働の定義」、労働の定義にどのように中身を与えていくかについてです。つづいて3.2「二つの世界」です。こういうことをするときもbackdropをいかに置くかが重要です。知覚、perceptionということは昔からよく使う言葉です。私はこれをあるときからよく使うようになりました。これもいろいろと種明かしがあります。知覚できる世界、できない世界という二分法をよく使うようになりました。なんのことですかと思うかもしれません。英語で言うとcountable、uncountableで名詞を二分します。身近なところでは、あのようなものを思い浮かべてみれば、われわれが考えているものの世界、われわれを取り巻いている世界がcountableな知覚可能なものと、uncountableな知覚できないものという構造でできていると思います。
哲学の人たちにとっては、知覚できないものはどのようにして分かりますか、ということが昔からのテーマです。知覚できないものを超越論と言うようですが、昔は興味があっていろいろとそのようなものを読みました。今は経済学をするときに、このような二分しています。一番はっきりとした分類は、客観的に計量できる対象と、それを超える超越論的対象の区別だろうと思います。
知覚できるほうの対象、つまり客観的に計量可能な対象を片仮名のモノと表記するとします。この片仮名のモノをよく使って議論を進めていきます。backdropはどのようになっているかというと、世界の下のほうの知覚できるcountableなモノの世界と、欲求や意志のようなモノが属する知覚できない世界です。このような大きなbackdropがあると考えて、その上で労働、オブジェクトを展開していこうというわけです。
二つの世界ということで3.3「身体の二元性」です。このように考えると、二分法がなぜ必要なのか、あるいは有効なのか、それは労働者という人間、労働する主体の特徴を捉えるための工夫です。意志の「しよう」、欲求の「したい」についてです。こちらのほうで考えるといいと思いますが、難しいことは置いておきます。「しよう」、「したい」という属性は知覚できないと思います。確かに労働者の人間にこのような属性が何かしらあるとしても知覚できませんが、両者は知覚できる世界に半分は属する身体に結び付いています。五感を備えた身体を介して欲求は生まれるわけであり、手足を自由に動かせることで、初めて「したい」という意志も働くことができるという構造です。
「したい」と考えてみたときに、身体が両義性をもっていることがポイントです。このような世界に存在している、このようなモノの位置をはっきりとさせることができると思います。知覚できる世界だけでもありません、知覚できない世界だけでもありません、ここです。両義性をもった身体です。
それに対して下のほうの知覚できる世界では、3.4「モノとモノの反応過程」です。これもなかなか分からない人が多いです。モノとモノの反応過程はこちらにモノの世界があります。後でもう少し説明しますが、手段になる金槌でくぎを打つという世界は、モノとモノの反応なので、どれだけの力がかかると、どういうことが起こるのかについて、客観的に自然法則が働いているので、どれだけ意志の力で念力をかけてみても、できないことはできません。ここはモノとモノの反応過程です。客観的な結果が出てくるような、拘束性があるような世界が下のほうの世界にあると考えるといいと思います。
ここは分からないかもしれません。「反応」の部分は取ってしまってもいいですが、要するにモノの世界ということで、そこではいくら意志があっても、意志の力では何も動きません。なぜ動くのかというと、両義性をもった身体と意志が結び付くからです。
次に3.5「目的意識的」です。知覚できる世界の諸現象に対して、目的物を設定するのは主体です。主体の意図は、この目的が実現するようにしようとするわけです。労働のコアになるのは、この「しよう」、「させよう」という意図的な活動です。この行動の仕方を目的意識的と呼びます。もちろんいくら「しよう」、「させよう」と念じても、自然法則に反することはできません。何が実現可能なのかは、主体が知るべきことです。
労働の概念は駆け足で言ってしまいました。「したい」の中に当然、あるもやもやとした体からの結び付きがなければ、直接、間接にあり得ないような、何らかのもやもやとした欲求があります。意志がもう一つあります。意思のほうもやもやしては駄目です。はっきりと何かを「したい」、「しよう」という意志がある必要があります。普通はこの欲求と意思の二つが重なって、欲求や意志を動かしながら、となります。ただしそれだけでは駄目で、両義性を持った身体を操作して、身体の外にある金槌をたたくと、くぎがめり込むという形で、知覚できる世界に働き掛けます。図のように2段構造になっていると言えば分かると思います。
これは1人で考えたときには簡単です。しかし、人間の労働はそれで終わりではありません。今はコア概念だけを三つ挙げました。人間の労働とは目的意識的、ということでコア概念ということで定義を出しました。定義はこれで結構ですが、どのようにするのかという内容を分析すると、二つの世界、バックグラウンドを置いて、身体の二元性を明らかにします。その上でモノとモノの実現の問題、モノとモノの反応過程は目的意識やこういう定義を、しっかりと内容を詰めていけばコア概念はできると思います。
ここが定義のようなもので、これで終わるものではないことは何となく分かってもらえましたか。労働の定義、労働のコア概念をつくってみました。さて、時間が押してきたので、これで終わりとするのがいいと思います。
実はここからが本日の本題の、労働概念の拡張です。あらすじだけを、あと5分ほど話します。せっかくなので岩田さんのものを見てからにします。このように整理してくれたので、この整理を使わせてもらいます。このように書いてあります。ここから話をすればよかったでしょうか。岩田さんは上のほうを全て外してしまったかもしれません。
コア概念からの基本相への変容は、実は拡張の考え方です。コア概念はここが定義ですが、それに概念のバックグラウンドを付けて、どのようにオブジェクトとしてつくるか、概念の定義をするのかについて話をしました。そうすると、拡張の方向性が三つほど出てきます。
人間の労働はどのようにできているかについてです。これは岩田さんの説明です。ブレイヴァマンが構想と実行の分離を強調したことはよく知られていますが、実はこれはとてもシフトした(一部に偏った)労働の定義になっていると思います。しかし、人間の労働について先ほどの図で拡張の可能性を考えてみると、目的物の設定があります。
一つ目は、人間は他人の欲求を明確な働き、機能に変える部分について、こちらのAさんがBの欲求の形を作るところに働き掛けます。こうなると自分の欲求ではないので、もやもやとした空腹感をどういう働きを持ったもので満たすことができるのかというと、もやもやとしたものをどういうものにすればいいのかについて、Aの再度の働き掛けで作り上げます。これが結構、大事なファクターになってくると思います。
これは、どのようにこの2人がコミュニケーションをしながら、相手の欲求を明確な形にするかということです。この活動が自分のときも本当は必要です。無意識にできるものについて、これができることは他人のもやもやとした欲求を明確な形に仕上げることです。抽象的に言うと、そうなります。
例えば商業労働をするのであればまずは、他人のもやもやとした欲求を明確な形に仕上げるところを、人間の労働のコアなところの中の第1フェーズ(相)として置くべきだと思います。商業労働の中身はこのようなことですが、しかし具体的な労働を直接、突然に入れるのはやぼです。入れません。十分に抽象化してから、こういうレベルでの理論をすることが必要です。
次に2番目の相です。それはどうすれば実現できるのか、ということが次の問題です。『資本論』や普通の労働論を見ると、目的設定をすると、あとは、ヨーイドン、で目的物に向かって働き掛けます。実はそのようにする前に、逆向きに目的物のほうから見えない働きがあります。これは見えないイメージですが、それを目玉焼きというはっきりとした目的物に変えます。これはモノの世界、こちらは見えない世界の機能ですが、それをさらに具体的な実現可能なものに変えます。ここまでが必要となります。
そのためには、次に目的からさかのぼって、どういう手段でできるのかです。これは1個ではなくて、さまざまなものを組み合わせて手段を体系化していくプロセスが2番目に必要です。それが2番目にあれば、第2の拡張です。相としてはイメージ、目的物を作り上げるという第1相のこの部分と、今度は目的物からさかのぼって手段の体系を作り上げるという第2の相があります。この2つの相を踏まえた上で、3つ目の最後の相です。これがうまくできていれば自動的にこのようにいきますが、外的要因でかく乱されるのに対して、身体を使って、絶えずコントロールする手段を作ります。自動車を運転するようなイメージです。これは、どれだけ機械が出てきても労働として行われてきました。自動機械といっても、今はここで本当に目的と手段の間を、逆にこちらのほうから完璧に戻していくことができれば、今までの20世紀に広く存在した操縦型の労働に置き換えることができるかどうかが、恐らく問題になってくると思います。そういう構造になっています。
早足になってしまいましたが、そういう岩田さんがまとめてくれた意味です。元の定義に飛んでしまっていますが、先ほどの岩田さんのところに三つの表でうまい具合に描いてありました。それを見てもらうといいと思います。
このような感じです。図でいうと第1、第2、第3の三つぐらいの性質を持ったものとして、人間の労働概念については、まずは拡張して考える必要があるだろうということが本日の話です。それをするとどういう効用があるかという話も当然、していかなければいけません。だいぶ長丁場の話になりましたが、ここまでです。こういう拡張をコア概念の上に考えていきます。みなさんがよく話している営業という問題を、労働についても理論的に考えてみることができるし、それをベースにすれば、今の変わりゆく労働のようなものも、右往左往して新しいものを見つけていろいろなことを言うレベルよりは、もう少し客観的、学問的な議論ができるお題ができるだろうという話でした。以上です。
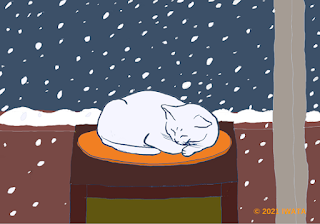

コメント
コメントを投稿