信用貨幣①の定義:外生的貨幣説
「信用貨幣」とはもともとの意味は、金のような物品貨幣を「ほんらいの貨幣」とし、その「ほんらいの貨幣」を引き渡す支払い約束が貨幣の機能を果たす場合、その支払い約束が信用貨幣ということだった。これが信用貨幣①の定義である。
図1

しかし、歴史的医は1930年代以降の金兌換停止によって「ほんらいの貨幣」が なくなってしまった。
兌換停止後は、強制通用力を持つ法貨である中央銀行の銀行券と硬貨を「ほんらいの貨幣」とし、その「ほんらいの貨幣」を支払う約束を信用貨幣と考える人もいる。ここでの「ほんらいの貨幣」は「政府紙幣」と呼ばれることも多いが、紙が金属か、データかは問題ではないので命令貨幣fiat moneyとよぶ方が適切である。
もっと粗雑な考えには、政府と中央銀行を混同して、信用貨幣の「信用」を政府に対する信用と思っている人もいる。これもfiat money の一種である。
ここまでで「ほんらいの貨幣」の理解には、それ自体に価値を持つ物品、特に金属と考える立場はを金属主義メタリズムmetallism、他方、貨幣の素材それ自体には価値がないが、政府による法貨規定や強制通用力付与で無価値のものが価値を持ち貨幣となると考える立場を表券主義または名目主義ノミナリズムnominalismという。
表券主義に対してはすぐに次のような反論がある。つまり、法貨規定や強制通用力付与だけでは貨幣が流通するとは限らない。ソ連崩壊時やラテンアメリカで見られたように、自国の法貨ではなくドルが流通することがある。また、中央銀行の銀行券や、様々なレベルの預金通貨は、一方的に交付されるわけではなく、与信や債券獲得の見返りに創出されるもので、銀行券や様々なレベルの預金通貨は発行者の負債であり、その裏付けとして発行者の資産勘定に元利払いの健全な資産がある。
これは信用貨幣が銀行の仕組みで発行されること、そして「ほんらいの貨幣」が存在しないことを思えば、有効な反論である。
このような反論としてたとえば吉田暁[2002]『決済システムと銀行・中央銀行』の説明は以下の通り。「兌換銀行券の流通根拠は兌換にあったのであろうか。流通根拠が兌換であったという点を強調すれば、不換銀行のそれは、法貨制にしか求められないことになる。しかし法貨であると強制しても激しいインフレに悩まさられれば、現実には流通し得なくなったり、ドラリゼーションでさえ起こりうる。不換化しても運営よろしきを得れば支障なく流通するということから逆に考えれば、兌換銀行券の時代でも、兌換は銀行券の信認を高めるために必要だったことは確かだが、真の流通根拠は銀行券の発行の態様にあった … つまり、経済取引のなかの信用関係がまずあって、銀行券にしろ預金通貨にしろ、その信用関係を代位するという形で信用貨幣が発行される。いい方を変えれば、再生産過程に根差した貨幣の発行還流こそが、真の流通根拠」(吉田[2002]78)
したがって、商品経済の中で流通する貨幣には、商品経済における根拠を持たなければならない。その考えには次の信用貨幣②と、信用貨幣③がある。
なお、現在のfiat money命令貨幣は硬貨である。
信用貨幣②の定義:内生的貨幣説
信用貨幣の信用の意味を①とは明確に異なるものとして打ち出したのが吉田暁である。
「現代にあっては,貨幣(中央銀行券,預金通貨)はすべて信用貨幣である(中略)。(ここでの信用はcreditであってtrustと解してはならない。信用貨幣は信用関係の中で発生・消滅するという意である。)吉田暁[2008]「内生的貨幣供給論と信用創造」『季刊経済理論』45(2), 15頁。つまり「ほんらいの貨幣」の支払い約束はtrustで、与信・返済という信用関係はcreditである。 与信によって発行される貨幣が信用貨幣だとした。これが信用貨幣②の定義である。つまり信用創造で生じるのが信用貨幣である。再び吉田の説明を挙げると、
「政府紙幣は国家権力により政府の購買手段として流通に投じられる(その典型が軍票)。これに対して中央銀行券を含む銀行券は金融取引を通じてしか、流通に投じられることはない。この点が両者を区別する重要な特色である金融取引を通じてしか、ということは誰かが負債を負うことによってしか、の意味であるから、銀行券の発行者はそのような負債を債権として、自らの負債(銀行券)と交換に取得し、リスクを負うのである。これは相手方の預金口座に記帳することによって貸出しを行う預金銀行の信用創造と本質的には同様である。政府紙幣の場合にはその弁済可能性は徴税権によっているが、銀行券の場合は発行の原因となった債権の返済可能性に依存する」(吉田[2002]142)
「ほんらいの貨幣」が全く存在しないので、信用貨幣①では想定されていた「ほんらいの貨幣」の支払いはなく、与信と返済の自己完結となる。図解すると次のようになる。
図2
①②の2つの定義の関係
2つの信用貨幣の定義は吉田が注意したように「信用」の意味が異なる。信用貨幣①は、貨幣の保有者が、その貨幣の発行者を信用する。吉田の言葉ではこちらはtrustである。他方、信用貨幣②は、信用貨幣の発行者が債務者の将来の支払いを信用する。こちらはcreditである。発行者を中心にみると信用の向きが正反対になる。
信用貨幣①と信用貨幣②をつなぐのが、1950年代の銀行券論争において、不換銀行券も信用貨幣だと考えた論者である。つまり岡橋保や川合一郎である。この人たちの主張は現代でも有力な考えで、簡単に言うと次のようになる。まず、信用貨幣の生成と還流について、信用貨幣①と信用貨幣②の形がある。次に、信用システムの発展で信用貨幣②が拡大し、金兌換の必要が少なくなり、最終的に金兌換停止で信用貨幣①がなくなっても信用貨幣②だけで成立する、というものだ。
これは信用貨幣①が「本来の貨幣」という基礎から離脱し、与信・返済の自己運動となって信用貨幣②になったということである。信用貨幣①でいうところの「ほんらいの貨幣」の支払いを無期限に延期することでもある。縮めていうと「兌換の無期化」となる。図解すると次のようになる。
「信用」という語について再論すると、図2の㋐の信用関係creditを基に信用貨幣が発生し、信用貨幣の保有者がその貨幣を信用trustするとすれば㋐のcreditが確実だから、ということになる。しかし信用貨幣②でも、銀行への債務者の債務のさらに裏付けの「ⓐ」の部分については積極的な言及はない。「ⓐ」の部分は次の信用貨幣③のテーマとなる。
岡橋や川合は信用貨幣①を基礎にしつつ、その発展として信用貨幣②の自立化を説いたが、吉田では「ほんらいの貨幣」がないので信用貨幣①もなく、初めから信用貨幣②がある。
なお世代を比べるために生年を並べると、岡橋保1905年、川合一郎・西川元彦1918年、吉田暁1933年である。
信用貨幣③の定義:商品貨幣説
小幡『経済原論』では「商品価値は金銭債権の形で外化し自立することもある。商品価値が債権の形で自立化した貨幣を信用貨幣とよぶ。」(小幡『経済原論』47頁)
商品価値を根拠にした貨幣となる。その商品はどこにあるのか図解すると
図3

信用貨幣の発行者の資産にある「商品の価値」は抽象的な説明であって、原理論におけるこの後の展開で現象に引き寄せて(小幡『経済原論』47頁)。後の展開とは信用機構、階層的な銀行間組織のことだろう。
また、上の定義では金銭債権が自立化したものが信用貨幣、となっているが、「金銭」が「ほんらいの貨幣」のことならば、「ほんらいの貨幣」を受け取る債権が信用貨幣となって信用貨幣①に戻る。あるいは「金銭」が信用貨幣成立で初めて成立する概念であれば、信用貨幣の定義の中に貨幣を含む循環参照になる。しかし、小幡『経済原論』の貨幣の「変容論的アプローチ」ではそうはならない。価値形態論で諸商品によって価値表現の対象となる貨幣が、商品価値に基礎を持つという意味で「商品貨幣」として導出されるが、その商品貨幣には商品の素材そのものが貨幣となる「物品貨幣」と、商品の価値だけが自立化する「信用貨幣」の二つにわかれる。俗な議論では、商品貨幣={物品貨幣}、とされているが、変容論的アプローチの原理論ではそうではなく、商品={物品貨幣、信用貨幣}である。
ただし、わかりづらいのは図3の「商品の価値」が、信用貨幣の資産として倉庫の中に大量の商品が集積しているというわけではなく、商品市場に多数存在する商品、商品を売買する主体、信用を取り扱う様々な主体が詰め込まれて抽象化されていることだ。
この記事のこの後の話は、図3の赤の楕円にある抽象化された「商品の価値」をいかにして、ある程度の具体性を入れて説くか、ということがテーマである。
さくら原論研究会『これからの経済原論』では、図3の「商品の価値」をもう少し具体化して、(鉄0.5kg, 砂糖15kg)のように複数の種類の商品の組み合せが示されている。しかしここでは価値量を重視しているが、貨幣は価値量だけではなく、すべての他の商品との交換性も必要になる。この点では西川の議論が次のステップになる。
信用貨幣の裏付けとなる「商品の価値」の抽象的な説明に対して、具体的な実務レベルでの説明のようになっているのが、西川元彦[1984]『中央銀行:セントラル・バンキングの歴史と理論』である。西川は次のように説明している。
「ここでは,預金通貨が銀行券により現実に弁済(引出)されうるのに対し,弁済されることのない不換銀行券がなぜ負債であり,流通しうるのかということについて一言しよう。」
「仮に不換銀行券を実際に弁済すると空想してみよう。その場合は,再割引した手形(保証物件)の弁済を求めざるをえず,商業銀行から問屋やメーカーに弁済請求が順次及んでいく。最終的な姿は,…(中略)…最初の買い手から商品を取り戻し,それで銀行券所持者に弁済することとなる。実際には,そんな不便な回り道はせず,銀行券所持者は市場で商品を買うことによって,銀行券という債権の弁済を受けたのと同じ結果を得る。市場でその商品を売った人の手に渡った代金は最終的には当初の借入れ(手形割引)の返済に充てられ,中央銀行勘定のうえでも,実際に,割引債権と銀行券という債務の双方が消滅する。空想上の弁済と同じことが間接的には市場取引で実現するわけである。これが『信用通貨による交換経済』の機構であり,銀行券発行の全経済的な『仕組み』なのである。金キンによる弁済を行わなくなった不換紙幣にも一種の弁済性があるといってよいだろう。これは手品か詭弁のようにみえるかもしれないが,現に動いている市場的事実といえる」(西川[1984]47-48)
図解すると、銀行券が流通しているときには次のような債権債務関係になる。
図4
西川の説では、銀行券は債権債務関係をたどっていけば最終的に市中銀行への債務者のⓐ商品に行き着く。銀行券は中央銀行の債務だが、中央銀行は債務の弁済を求められれば、債権債務関係を辿って行って市中銀行の債務者の商品を引き渡すことで債務の弁済ができる、と西川は言う。これは銀行券の裏付けには商品があることを示す。そのこと自体は正しい。しかし西川は、商品は特定の使用価値によって価値が制限されることへの考慮が不明確だ。銀行券保有者が価値の引き渡しを要求する金銭債務に対しては、銀行券発行者は価値が制限される商品では引き渡しができず、債務も弁済できない。同じ価値の大きさであっても、商品では特定の使用価値によって交換可能性としての価値が制約されているに対し、貨幣としてはあらゆる商品に対して直接的交換可能性を持つ。そのため、銀行券が貨幣であるならば図4の㋐商品に限らずどの商品に対しても交換可能性を銀行券は保証しなければならない。
つまり図4では中央銀行が支配できる商品は、ⓐ商品に限られる。そこで、西川は大量の商品のある商品市場に着目するように言う。つまり銀行券保有者は市場でどんな商品でも買えるので、特定の使用価値に制限されずに、債務の弁済を受けることができる、と言う。
もちろん西川は図4で、すでに貨幣の存在を前提にしている。しかし貨幣の発生を説く価値形態論では貨幣の不存在を前提にするので、「債権」「債務」とは商品の受取・引渡である。この引き渡し対象の商品の種類が増えれば、特定の使用価値への制約がなくなる。図解すると以下のようになる。
図5
ここで「複数の商品の引渡債務」「複数の商品の受取債権」とは、複数の商品から債権者がどれかを選ぶということだ。なお、私の論文の題の「or」は意味がわからないと査読でクレームがついたが、もともとは小幡『経済原論』39頁問題18の「andの関係」「orの関係」からきている。
この商品引渡債務発行者が保有する商品には限りがある。これを増やすには、商品引き渡し債権・債務を拡大することだ。そこで、別の商品所有者が自分の保有商品を引き渡す債務の見返りに、複数の商品引渡債務者から「複数の商品の引渡債務」を受け取る。この「別の商品所有者」がたくさん増えれば、「複数の商品引渡債務者」のもとに多数の種類の商品が集積し、「複数の商品の受取再建」は多数の商品からいずれかを受け取ることができる。Bのもとには現物商品の他に多数の商品受け取り債権が並ぶ。
図6

多数の商品と交換可能という点でこの債権は特定の使用価値の制約を解除し貨幣となる。ここで西川説の債務者の保有商品という制約から、商品市場へと転回した。
A1~nの経済主体はもともと自分が称している商品は特定の使用価値によって価値が制限されており、流通過程の不確定を帯びている。しかしBと債権・債務関係を結び、B多数のもとにある多数の商品のどれかを受け取る債権を持てばそれは使用価値の制約を解除された貨幣となる。つまりBは特定の使用価値に制約された商品を、制約されない貨幣に変換する機能を果たす。そのためにはBはA1~nがもともと保有する商品が、他の主体から交換に求められやすいかどうかを審査する必要がある。
銀行は非流動的資産を流動的資産に転換する、長期の債権を短期に転換するといった転換機能を持つといわれる。その転換機能を思い出せば、図6のBの役割は容易に理解できるだろう。
なお、さくら原論研究会『これからの経済原論』では、図3の「商品の価値」を安定化するために複数の商品が組み合わされる、としている。つまり、小幡『経済原論』の信用貨幣の定義について価値の安定性を重視して延長している。しかしこれは商品の使用価値の制約の問題を回避している。私(岩田)は、価値形態論での貨幣の形成における使用価値の制約の解除を重視して、西川説の商品市場への転回の方法を用いた。
詳しくは「商品集積体と債権化から信用貨幣を導出する新しい価値形態論:orの関係で結びついた商品集積体を基礎として」 さらにはブログの「現代資本主義論講義」「第5回:信用貨幣の構造と展開」のC.2を参照。
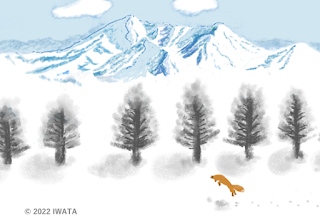







コメント
コメントを投稿