注目
「変容論的アプローチの適用」の段階論と現代資本主義論への適用-5:利潤の測定
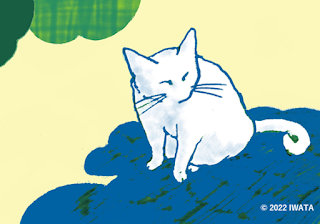 |
機構論
「本質規定としての原理論」は流通論と生産論が多く、機構論には「分析基準としての原理論」として変容する要素が多い。
利潤の測定
利潤の測定方法は、小幡『経済原論』では 開口部や変容のポイントではないが、問題59の解説(306)には利潤の測定方法は複数あることが示されている。
展開
利潤の概念は原理論の展開では流通論と機構論の2か所に現われる。 流通論では資本の基礎概念とともに論じられる。機構論では、利潤率をもとに、複数の資本間の競争で利潤率の均等化と生産価格体系の同時決定が説明される。
いずれにしても投下資本の価値額よりも価値が増えた部分が利潤となるが、ここが開口部となるのは価値尺度を受けていない、生産要素や在庫商品その他の資産の価値の測定方法が複数あるからである。姿態変換の図式で書くと、 G-W・・・P・・・W’-G’ あるいはG-W・・・W’-G’ において、「・・・」の前のWは以前に買われたので価値尺度を受けている、つまり価値実現による価値の測定がされているが、「・・・」の後G’はまだ価値尺度を受けていない。この部分の評価として簡単に理論の歴史を踏まえておく。
マルクスは『資本論』第1巻では剰余労働と姿態変換による剰余価値の価値増殖の概念を用いるが、『資本論』第3巻6章2節「資本の価値増加および価値減少、資本の遊離及び拘束」には「価値増加」と「価値減少」の概念がある。ここでは実物資本維持の観点から、保有原材料の価格騰貴による「価値増加」や、固定資本の「社会的摩滅」(陳腐化)による「価値減少」などが利潤率に与える影響を考察している。また、『資本論』第3巻29章でも、収益や利子率の変化による証券の価値減少・価値増加に言及している。
山口は「・・・」の前後では、「W」の価値と「W’」の価値は直接にはつながらず、「価値の切れ目」があり、その切れ目を資本家の活動がつなぐ、とした(山口『経済原論講義』67頁)。そう考えると「・・・」の過程では価値は不定となろう。
小幡『経済原論』では、流通論における「内在的価値」の想定が特徴である。以前、宇野はマルクスを批判して投下労働量による価値規定を流通論から外し生産論に移した。そうすると流通論では実際に買われることで価値尺度を受けるが、その際の価値の基準はなく、価格はばらつく。したがってまだ買われていない価値の大きさを測定することができない。これに対して小幡は、同種の商品が多数、売買されている中でその商品の価値の基準が浮かび上がってくるとした。これが内在的価値、あるいは相場の価格である。そうするとまだ売れてなくても、W’-G’の「W’」の段階で、販売された場合と同量の価値を持つことになる。そうすると、まだ売れてない商品もその同種商品に共通して存在する内在的価値で評価する方法が可能になる。この内在的価値はばらつく束であるが、同種商品にかかわる多数の経済主体間の相互の牽制作用によって基準が生じる(小幡『経済原論』問題43解説297-298)。
変容
理論的な展開としては資本に保有される資産の価値が増えたらそれが利潤になるが、その利潤の測定の方法には複数の可能性がある。実際に売れた価値量で測定されるのか、それともまだ買われていなくとも同種の他の商品の売買から浮かび上がる内在的価値(相場の価格)で評価するのか、という2つである。ここでは、前者の姿態変換を伴う方法を「価値増殖」とよび、姿態変換を必要とはしない評価の方法を「価値増加」とよんでおく。
表 利潤の認識と測定の変容
|
多態化 |
利益の計算 |
収益費用アプローチ |
資産負債アプローチ |
|
価値量の測定 |
取得原価主義 |
公正価値(時価)主義 |
|
|
利潤の性格 |
当期純利益 |
包括利益 |
|
|
変容 |
利潤概念 |
価値増殖 |
価値増加 |
|
資本概念 |
姿態変換 |
姿態変換しない部分を含む |
|
|
市場 |
分散的な市場 |
集中的な取引所のある市場 |
|
|
価値尺度 |
価値実現 |
内在的価値の未実現の評価 |
|
|
展開 |
〔流通論〕 |
(資本投下→)増殖(→資本の多態化) |
|
|
〔機構論〕 |
(費用価格→)利潤(→利潤率均等化と生産価格) |
||
価値増殖は姿態変換運動によって価値量を測定することであり、山口のいう「価値の切れ目」にある資産(または要素)は、かつての売買であるG-Wの価格で測定する。この測定方法が想定する市場は、原理論で一般に想定される分散的な市場である(小幡『経済原論』54)。つまり同種の商品が大量に多数の売り手と買い手によって分散的に売買されており、商品の売り手にとって自分の商品がいつどれだけいくらの価格で売れるかは不確定である。そのため、実際にその商品が買われて価値実現することが利潤の測定の起点となる。利潤はフローの実現利潤となる。
他方、価値増加は、まだ売れていない商品について、分散的な市場でも内在的価値として評価は可能であるが不確かである。しかしそうした商品の評価額の変化が損益と計算されるほどに確かな評価になるとすれば、それは、取引所のような市場で集中的に売買される場合である。その場合、市場で付いた価格であればいつでも売れると評価できる。その評価額の変化分は未実現のストックに含まれる利潤となる。話を簡単にするために負債がないものとする。評価額の変化を損益と考えるという方法を徹底すれば、t期の価値量の総額{Gt,Pt,W’t}とt+1期の価値量の総額{Gt,Pt,W’t}を比較することで利潤が測定できることになる。この価値総額の中には商品売買による貨幣量の変動や保有商品の変動も含まれるので、価値増加の概念は価値増殖を包含する。
多態化
姿態変換に基づく価値増殖は具体的には、利潤率計算上の期間における収益から、その収益に対応する費用をマイナスして当期の純利益として計算できる。これは収益費用アプローチであり、保有資産の評価額を取得原価で固定することで評価額の変化を利潤計算から隔離する。
他方、姿態変換しない部分も含む価値増加は具体的には、利潤率計算上の期間における期首について資産から負債を引いた純資産から、同様に算出した期末の純資産を引いた額として計算できる。これは資産負債アプローチであり、保有資産の評価額も含むという点で包括利益となる。ここでの資産や負債の評価は実際の売買ではなく、公正価値としての評価に基づく。
しかし、包括利益は一般には、二時点間の完全な純資産から計算するのではなく、純利益を基に、販売されていない資産の価値変動を加えて以下のように計算される。
包括利益 = 純利益 + その他包括利益(OCI: Other Comprehensive Income)
純利益は主に収益費用アプローチで計算され、OCIはすぐに売却されない資産の評価額の変動から計算される。そのため、現在の包括利益は収益費用アプローチと資産負債アプローチのハイブリッドになっている。また、現在では純利益の中にも収益費用アプローチで計算された利益の他に、売買目的で保有されている資産の公正価値価の変動が純利益として計算されるため、厳密にいえば純利益自身も収益費用アプローチと資産負債アプローチのハイブリッドになっている。
ハイブリッドだから全ては2つのアプローチの中間形態、というわけではなく、どちらかのアプローチヘの偏りをみることで資本主義の変容を分析することができる。。
売買目的の資産の評価は、取引所のような市場で集中的な売買が行われる金融資産の場合に整合的である。そのため資産負債アプローチは1980年代以降の「金融化」と合わせて論じられることが多い。さらに金融資産だけではなく、その他の資産や負債も含めて、分析基準として2つのアプローチを設定しその2つアプローチの揺れとして分析することによって段階論と現状分析を考えることができる。段階論は世界資本主義の歴史的な変化なので1980年代を前後にして収益費用アプローチから資産負債アプローチへの移行としてとらえることができる。そうした段階論の大きな枠組みを基にして、各国における2つのアプローチのシフトの状態が現状分析となる。
参考 岩田[2019]「現代資本主義における利潤の認識と測定:原理論と段階論からの検討」

コメント
コメントを投稿