注目
「変容論的アプローチの適用」の段階論と現代資本主義論への適用-6:本源的自然力(地代論、土地と知識)
本源的自然力
展開
地代論はもともと、制限された生産条件である土地を主要な生産手段とする農業を中心に論じられてきた。しかし現代の資本主義では知識が重要になり、知的所有権で利用が制限される知識について地代論を応用した議論が始まっている。
小幡『経済原論』では、「土地」を一般化して、「本源的自然力」という概念にする。その定義は「生産に用いられるが、再生産されない生産条件」のことである。その特徴は
(1)何回も用いられても劣化しない。劣化しない部分が本源的自然力である。
(2)再生産されず、「発見」される。再生産可能な生産条件は模倣されて優等のものにそろっていくが、再生産不可能ならば均質化せず較差が残る。(小幡『経済原論』201-202頁)
生産条件に利用制限がない場合には、平均利潤と生産価格体系が成立する。しかし利用に制限がある場合には超過利潤が生じ、その生産条件の所有者がその超過利潤を得る。これが地代である。
変容
地代論での開口部は、小幡『経済原論』では「絶対地代」と「恒久的土地改良」にある。
「絶対地代」の概念は伝統的な原理論では、農業は資本の有機的構成が低いので農業生産物では投下労働量による価値量よりも生産価格の方が低くなる。土地の利用制限のため、農業で生じた投下労働による価値が他の部門に移動しないため、農業生産物では、生産価格を上回って超過利潤を得ることができる。これが絶対地代の源泉になる。しかし近年の原理論では、投下労働量は総資本と総労働の分配関係を示し、生産価格が個別の商品の価値の基準を示し、この2つは切り離される。そのために資本の有機的構成に基づく絶対地代の説明は使われてはいない。
その代わりに小幡『経済原論』での絶対地代の説明は、利用されている土地の中で最劣等の土地の所有者たちが結託してタダでは貸さないと地代を要求することによって絶対地代が成立する。結託がなければ、土地の貸出競争が最劣等の土地の地代をゼロにまで引き下げる。結託の有無は外的条件による開口部になる。
「恒久的土地改良」は土地の豊度それ自身を変更させるものである。産業資本は資本投下と利潤という枠で再生産の活動をするが、恒久的土地改良は不均質な外的自然に一回限りで働きかける。そのため、恒久的土地改良は再生産を基礎とする資本の枠組みに入らず、産業資本とは異なる活動である。そ戸で恒久的土地改良の主体は、資本家でも労働者でもない第3の主体となる。原理論は資本の活動を中心に論じるため、誰がこの主体となるかは原理論では開口部となる。ここで、小幡『経済原論』は、恒久的土地改良は土地所有者の役割、と断定しているわけでなく、資本がおこなわない、と断定しているわけでもない。恒久的土地改良とはシンボリックな意味であり、土地ではなく知識の場合には新しい知識の発見となる。
しかし、上記の説明は土地を本源的自然力としてして抽象化するのがまだ弱い。もっと抽象化してみると以下のように考えられる。
まず、絶対地代については本源的自然力の所有者間で結託ができるのか、ということである。土地で考えると、たしかに土地は生産されず、その量には制限があるものの、同じランクの土地が多数、分散して存在する場合に、同じランクの土地の所有者同士で結託するのは難しい。もちろん結託は外的条件が必要としてあるが、結託が外的条件次第で可能だとして原理論の中に取り込むなら、資本家の間や労働者の間においても多様な結託が可能になり、カルテルや、労働者の団結権を基礎とした賃金交渉も原理論の対象になるが、これは外的条件の濫用だろう。しかし、小幡『経済原論』には絶対地代が容易に理解できるところがある。それは問題132でガソリンエンジンにパテント(特許権)が設定されて絶対地代を得る設例だ。同種の本源的自然力が一人の経済主体のみ所有されていれば結託して絶対地代を得るのは容易だ。こうした絶対地代の可能性の考察から、本源的自然力の変容を組み立ててみると次のようになる。
表 本源的自然力の変容
|
多態化 |
土地など |
知識など |
|
変容 |
タイプ1 |
タイプ2 |
|
特定の有体物と分離不能 |
特定の有体物と分離可能 |
|
|
本質的に不均質 |
同じモノが無限に広がる。他のモノとは不均質 |
|
|
物理的に利用制限可能 |
法的に利用制限可能 |
|
|
絶対地代は困難 |
絶対地代は容易 |
|
|
展開 |
(生産過程における競争→)競争の制限(→流通過程における競争) |
|
土地と地代という言葉が抽象化を制約していたので、本源的自然力の変容として「土地」や「知識」などの具体的な形を付けることは適切ではない。そのため変容の名前として先入観がなくなるようにここでは仮に「タイプ1」、「タイプ2」としておく。
本源的自然力自身は再生産されない生産条件の意味であり、利用制限とは直接には関係ない。利用制限されると、超過利潤を得る可能性がある。利用制限について、「タイプ1」は特定の有体物と分離不能なので制限は容易だが、「タイプ2」は特定の有体物と分離可能で多数の有体物や経済主体に同時に利用可能である。知的所有権の法制度のような外的条件があれば制限が可能となる。このように考えれば絶対地代はタイプ2で容易に発生することはわかる。
ここは新しい領域なので、試みにいろいろと考えてみることができる。まず、タイプ1とタイプ2は互換になる場合もあろう。たとえば、優等な農地の生物・化学的分析を徹底してタイプ2の知識に変えて野菜工場にする、という場合がある。逆に、知識は本来的にタイプ2だが、特定の人にのみ習得可能な知識はタイプ1と同じことになる。小幡『経済原論』でいえば名人芸のような個人の熟練の「属人的熟練」(156)である。複雑労働として習得可能な範囲であればタイプ2であり、知的所有権の対象となればタイプ2のままで利用制限される。
本源的自然力を「タイプ1」「タイプ2」に区分すれば、恒久的土地改良の開口部は、特別利潤の問題に吸収される。ここで「特別利潤」とは従来の原理論で「特別剰余価値」としてきたものである。新たな知識や新たな資源で生産方法の利用を改善した場合、改善の源泉はタイプ1とタイプ2に分かれる。タイプ2であれば外的条件として知的所有権の有無に分かれる。新たな知識や新たな資源の利用の発見が、何らかの理由で他の主体には利用が制限されると「恒久的土地改良」になる。ここでは「土地」を抽象化するために「本源的自然力の恒久的改善」とよんでおく。まもなく他の主体に模倣される場合と恒久的な場合を含めると「本源的自然力の改善」となる。「本源的自然力の改善」の発見は本質的に一度限りの行為であり、産業資本の再生産に依拠した活動とは異なる。発見に要する費用はあらかじめ見通すことはできず、また結果として要した費用には客観的合理性はない。そのため発見に要した費用は費用価格に入らず、特別利潤も一般的利潤率の計算に入らない。特別利潤は改善された本源的自然力の所有者が得る。その意味で本源的自然力の改善の主体とその所有者は資本であっても非資本であってもよい。その意味で源的自然力の改善の主体は開口部になる。変容と含めて図式化すると以下のようになろう。
表 本源的自然力の所有と改善の主体の変容
|
多態化 |
土地所有者、発明家など |
技術革新を内部に取り込む企業 |
|
変容 |
本源的自然力の所有者と利用者が異なる |
同じ |
|
改善の主体と利用の主体が異なる |
同じ |
|
|
展開 |
(本源的自然力による制限→)本源的自然力の改善 |
|
従来の地代論は、農業のように本源的自然力の所有者と利用者が異なる場合のみが論じられ、農業における生産性向上の遅れとそれに伴う資本蓄積の遅れが説明されてきた。しかし、本源的自然力の所有者と利用者が同じ場合には逆に特別利潤の獲得を目指して本源的自然力の改善が促進される。さらに外的条件として知的所有権のようなものがあればさらに促進される。この開口部と本源的自然力のタイプ1、タイプ2は連動して考えるべきだが、本稿ではここまでにする。
こうして土地や知識を本源的自然力の変容した形として抽象化すれば、理論に新しい領域が開ける。
しかし、現実の世界にある知識や知的所有権を、原理論体系の地代論に取り込もうとすると別の問題が生じる。たしかに特許権や実用新案権によくあるように生産技術に係るもので確定的な製造原価のレベルで生産性を高めるものであれば、地代論で論じるのは適切である。しかし知識の中には商標権や意匠権、著作権など生産技術にかかわらない知識がある。これらは不確定な流通過程に関与するものが多い。そうであれば商業地代論の中に取り込むことができる。商業地代はマルクス『資本論』第3巻第18章「商人資本の回転、価格」の最後に出てくるが、これまであまり議論が進んでいない。
商業地代
排他的に制限された条件を利用することで、販売量の増加や流通費用の節減が可能であれば超過利潤が生じる。販売価格Ps、買取価格Pw、流通費用総額k、商業資本Cz、販売数量Qとし、その条件を用いた場合の変化分Δで示すと商業地代は以下のようになる。
商業地代には2つの方法がある。1つは売買を集中することで販売が有利になる特殊な場であり、具体的にはアマゾンなどのプラットフォーム、ショッピングセンターなどがある。もう1つは商品の本質的な使用価値が同じでありながら、副次的な使用価値を変化させることによって販売促進させる競争的使用価値を付加することである。大きく言えば「場」はタイプ1で、競争的使用価値はタイプ2になる。競争的使用価値とは、本質的な使用価値は同じだが、個別的販売の偶然性に対して自分の商品の販売を促進するために副次的な使用価値を変化させることである。小幡『経済原論』でいえば同種と異種の境目にあるものであり、大きくは同種に取り込まれるが、異種に分立化しうるものである。競争的使用価値について簡単には、加藤司[2006]「石原理論の革新性について」参照。
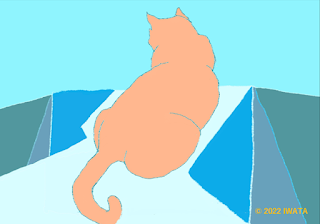

コメント
コメントを投稿