(3月11日少し修正)
原理論では最近、地代論の研究は少ないが、逆に言えばこの領域は今後、大いに発展できる余地がある。
もともと古典派やマルクスの時代には経済的に農業が一定の比率を占め、政治的にも土地所有者がかなりの程度の権力を持っており、農業を基礎とした地代論は重要な意味があった。しかし、農業や土地所有者の影響力の低下とともに地代論は減少してきたといえる。もちろん、土地以外の制限された自然力として、利用制限される知識や生産技術も地代論の範囲だと以前から指摘されており、近年のIT化による知識経済を地代論から考察する試みもある。ただし、これらの試みの多くはマルクスの記述のあてはめにとどまっている感が否めない。原理論体系では小幡『経済原論』の地代論が土地と知識・技術の共通性を指摘して、原理論における位置づけの見通しが良くなった。しかしそれでも土地と知識・技術の類似と相違が検討されているわけではない。
土地と知識が同じ、というのはかなりインパクトのあるテーゼである。これは地代論だけでなく、原理論における市場観や、現代資本主義の新自由主義としての特徴など、さまざまな面で発展していく可能性がある。
今回は可能な発展の方向をいくつか示しておく。詳細は今後、論じていく。
知識と土地の類似と相違について。土地よりも知識の方が地代論に適合する
すでに
以前の記事で示したが、土地と知識は再生産されない生産条件という点で共通である。相違は、土地は有体物に固着し、基本的に不均質であるのに対して、知識は無体の要素として、多数の有体物に普遍的に広がっていくものである。知識は知的所有権などで制限されたときに土地を同じ性質を持つことができる。ここは有体物と無体の要素との区別と関連を理解しておく必要がある(
別の記事(B.有体物と無体の要素(知識)との関係)参照)。
現代の宇野理論における地代論は日高普の地代論が基礎になっているが、そこでは、①同一レベルの生産条件は生産量を弾力的に伸縮できることと、②異なるレベルの生産条件の間には非連続的な較差があることの2点を前提にしている。
しかし、この2点を否定して絶対地代を否定する議論も多い。たしかに本質的に不均質な外的自然としての土地ではこの2点は成立しない可能性も高そうだ。しかし、利用制限された知識の場合、同じ生産技術の知識の利用は弾力的に伸縮可能で、かつ、異なる生産技術の知識は非連続的だと容易に考えられるので、この2点は成立するだろう。こうして、現在の原理論の地代論は、土地よりも知識と生産技術の方がうまく適合する。
再生産過程に土地と地代を導入し、生産価格と絶対地代を両立させることは可能
マルクス以降の原理論の大きな発展は、投下労働量や生産価格の議論に再生産の概念を導入したことだ。では土地と地代はどうなるのか。土地は労働生産物ではなく、地代は剰余価値の一部の分配
なので、投下労働量の計測ではなく、生産価格で地代を含めて説くことができる。まず絶対地代がなければ地代のない最劣等の生産条件だけが生産価格の計算に入るので、通常の生産価格と同じことになる。優等地で生じる差額地代はその部門だけの問題である。問題は絶対地代の場合だが、ここで、地代が生じる生産物が他の生産物の投入物にならない「非基礎財」の場合と、投入物になる「基礎財」で異なる。非基礎財ならその部門の原価に地代を加えればいいので容易だ。「基礎財」の場合は絶対地代が外生的に与えられれば計算可能だ。実際、現在の原理論では外生的に与えられる。ただし、固有値と固有ベクトルの方法は使えない。たとえば小幡『経済原論』193頁の式に、小麦20トン当たりの絶対地代を小麦の価格p2でa×p2として外生的に与えられるとすれば、以下のように下線部が追加される。
(6p1 + 4p2 + 6w)(1 + R) = 20p1
(8p1 + 4p2 + 4w)(1 + R) + ap2 = 20p2
5p1 + 5p2 = 10w
これらの式においてaは定数なので、p1とp2の比と、Rの値が計算できる。
三大階級の見直し:知識と生産技術を、超過利潤を生む「土地」に相当する「無形資産」と認識する。
農業に基づく地代論では、土地は土地所有が所有し、農業における資本蓄積の阻害となる想定がふつうである。もし制限された知識や生産技術を地代論で論じると、資本が特別利潤(特別剰余価値)を追求する中で得た新たな知識や生産技術が長期にわたって、他の資本に対しては制限され続ける、という構図になる。この場合には農業における土地とは異なり、知識や生産技術の所有者はまずは資本であり、知識や生産技術の所有は資本蓄積を促進する面もみられる。もちろん過度な知的所有権の保護が資本蓄積を阻害する可能性もある。この場合は三大階級ではなく、土地所有者のいない二大階級となる。しかし知識や生産技術についても三大階級を想定することが可能である。新たな知識や生産技術を発見し所有する主体を資本の外側の発明家やベンチャービジネスとすれば三大階級になる。しかしそうではなく、一般の産業資本が知識や生産技術を新たに発見する場合は、一時的にのみ存在する特別利潤であれば、これまでの原理論の想定通りである。しかしその知識や生産技術がもたらす特別利潤が持続化し、地代論として論じるためには、産業資本の主たる資産とは別の特別な資産として認識される必要がある。それは、会計上の「無形資産」の一部に相当する。
通常、自己創設の知識や生産技術は、資産認識されるにはかなり制限があるが、M&Aによる獲得では被買収企業の知識や生産技術は特別な「無形資産」の一部として認識可能な場合も多い。その際の評価はPPA(Purchase Price Allocation:取得価額配分)の際に、獲得した資産の超過収益力をインカムアプローチで評価すれば、土地が地代を生むのと同様に、獲得された「無形資産」が超過利潤を生む、として計算される。こうして、産業資本は自身の中に通常の産業資本の資産の他に、「土地」に相当し、地代を生む「資産」を保有することになる。この場合、三大階級ではなく、土地や知識の所有は様々な階級に分有される。なお、「無形資産」とはかなり曖昧な概念なのでさしあたり「」をつけておく。その説明は
別の記事にある。
ここで行動論的アプローチの徹底を考えてみる。資本の活動が土地所有を発生させる、というのは日高や大内力の特徴的な論理である。その論理の骨子は利潤率の均等化の妨げになる土地は資本とは別の、土地所有者に押し出されるというもので、「行く先論アプローチ」そのものである。しかし資本が新たな知識と生産技術を発見し、それが会計上、資本の主たる資産とは区別される「無形資産」として認識されるようになれば、その「無形資産」の発生は個別資本の利潤追求活動が生み出す「行動論的アプローチ」によって説くことができる。この意味で、知識や生産技術の方が土地よりも原理論に適合的である。
市場観:在庫に満ちた市場、価格の下方放散
原理論体系では地代は「機構論」の前半の「価格機構」の最後にある。その次は、不確定な流通機構への対処に特化した資本が分化発生する市場機構論である。価格機構の中心をなす生産価格は需要の契機を持たない。需要の変動の影響は商品在庫を中心とする流通資本によって吸収されることを前提とし、価格は生産過程のみを考慮した利潤率の均等化によって決まる。しかし、地代論では社会的需要の変動に対して、変動する生産の限界部分が論じられる。なお、宇野『原論』の場合は地代論の少し前の「市場価値」から社会的需要が導入される。
いずれにしても、マルクス経済学の中でも、ここからミクロ経済学の需要曲線と供給曲線と同じ理解をしている場合もある。しかし、小幡『経済原論』の「在庫に満ちた市場」や「価格の下方放散」といった概念は、需要曲線と供給曲線の交差、需給の一致とは根本的に異なる市場観を示している。この市場観では、社会的需要の変動の影響は在庫の変動によって吸収されるとともに、価格の下方放散の幅の伸縮によっても吸収され、生産量の変化に直結しない。これは、商業資本が存在する「市場機構」論の前のことであり、地代論における複数の生産条件の存在の前提にはこうした、重い媒体の中で動く粘着的な市場があることを前提にしておく必要がある。
新自由主義との関係
19世紀末からの固定資本の巨大化や、労働の組織化の進展によって経済の内側からの組織化が進み、さらに二つの世界大戦や経済危機を契機にした経済過程への政治的な介入による組織化が進んだ。こうした動きは1980年代を契機に変化し始める。組織化を市場に置き換え、資本の利潤追求活動の場とすることで、組織化が果たしてきた社会運営を市場と資本による運営へと委ねようとする動きが進んだ。これが新自由主義である。その場合、従来は非市場的な組織で運営されていた領域に所有権を設定し、市場の売買の対象とする方向が進む。例えば環境に負荷を与える排出物は排出権として財産権に模した権利が創出され、市場で売買される。排出権への支払いは生産活動をおこなうための地代の支払いと同一であり、これは「土地」の利用と同じ扱いになる。太陽光発電や風力発電は従来、地代を生まなかった土地に用途転換によって地代を生じるようになる。その際には新たな所有権、または広く財産権が設定され、超過利潤を受け取る権利となる。
このあたりのことは「資産化assetization」として様々な現象が取り上げられていることは
以前の記事で紹介した。ここでの「資産」とは、商品のように売却ではなく、保有を続けることで剰余価値の一部を受け取ることができるモノである。
金融資産としての土地。しかしこの概念はよくない
有名なところではD. ハーヴェイなどのマルクス経済学な経済地理学では、土地を金融資産とする議論が多い。こうした議論では金融化financializationの発展形と合わせて論じられたり、生産から遊離して資産保有からレントを得ることを表現するために「レント資本主義」と言ったりする。しかしこれは金融資産の利子と土地の地代との区別を抹消するものであり、あまりよくない。つまり、土地を金融資産としてみる観点は金融化の拡大として一定の意味があるだろうが、剰余価値あるいは利潤が発生する根拠を【保有資産額 × 利子率】に解消するのはよくないということだ。
たしかにマルクス経済学でも、地代論の最後で「諸階級」として、土地の価格が地代を利子率で割ることで算出されるという概念から、資本家が土地を買って利子と同様の地代を得ることで、資本家階級と土地所有者階級の融合をいう場合もある(例えば日高[1983]『経済原論』215-216)。ここで問題になるのは、土地の豊度を変化させる恒久的土地改良に要した費用の扱い方だ。日高の場合、【土地価格 = 地代 ÷ 利子率】の関係から、【恒久的土地改良費 × 利子率 = 地代増加分】となるべきと論じている(日高[1974]『地代論研究:再版』185-186。これには犬塚、磯前、柘植らの議論があり、そのうち触れる)。
たしかに損得勘定ではそうかもしれないが、これは将来の期待収益に基づく資産評価としての「インカムアプローチ」と、資産を作るために要した「コストアプローチ」を同一している点で問題だ。知識と生産技術の発見は再生産過程の外側にあり、発見に要した費用と成果との間には客観的に合理的な関係がなく、この二つのアプローチによる算出額は根本的に異なる。農業と土地の場合の実務はよく知らないが、土地が本質的に不均質であればやはり同様に異なる異なるとみるべきだろう(二つのアプローチのギャップはインカムアプローチの場合の利子率と利潤率との違いから生じる、ヒルファディンクの「創業者利得」の面もあるがここでは考察しないでおく)。そのため土地の恒久的改良や知識の発見には資本の活動とは別の計算のフレームワークが必要となる根拠がある。この点でも地代論を土地や農業に限定するのではなく、知識や生産技術に拡張することで、より一般化し、抽象化して原理論で地代論を論じる可能性が広がることがわかる。
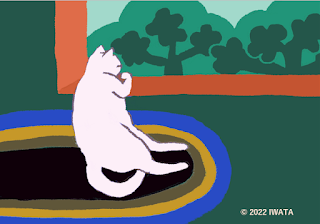


コメント
コメントを投稿