注目
東経大学術フォーラム:方法の報告での質問・感想について
報告者からの回答はそのうち公表されると思いますが、私(岩田)の(勝手な)意見を書いておきます。以下の回答は泉氏の見解とは関係ありません。
学術フォーラムの質疑応答のページはこちら。
全体について
◆「「資本主義の諸タイプを構成する必要がある」とのことですが、諸タイプとはどのようなイメージになるのでしょうか?」
←今回の報告は方法論に徹したようです。いろんな具体的な事象を並べ立てて煙に巻くのではなく、中身に入ることなく方法論をそれとして論じるということでしょう。
◆「今回は方法論中心ですが、イメージしやすくするために、開口部、外的与件の変化の具体例はを挙げてもらえませんか? 20世紀中葉、今の現代、これらの違いなど。それとも、意図的に具体例を論じないほうが良い、ということでしょうか?」
←私(岩田)は泉氏とは異なる立場です。例えば、次のように抜本的に段階を組み替えて、19世紀の規制撤廃型の自由主義イデオロギー、20世紀の市場の組織化・市場をコントロールしようとするイデオロギー、それまでの組織の中に市場をつくり経済主体を資本として規律付ける新自由主義のイデオロギー、と仮説的に区分し、外的与件と開口部での作用を論じるのが最短コースだと思われます。
この図の説明は現代資本主義論Ⅰの授業資料の第3回にある。
例えば有名な例ではレーニンの帝国主義論は、現実に存在する帝国主義のイデオロギーや政策体系に対して経済学としての根拠を与えようとしたという流れになっています。
◆「「開口部」の活動は活発になったり不活発になったりするのでしょうか。だとすると、その「開口部」の活動の活発・不活発の程度を規定する基本的な要因というものは何(資本主義社会におけるどのような状態)なのでしょうか」
←私(岩田)の理解は泉氏とは異なるようですが、さらに質問は一般的な開口部の理解とは異なるようです。開口部はいつも存在し、そこにどういう外的な条件が作用するによって資本主義のモードが変わるということになります。具体的な開口部については、今回の報告では方法論に限定すると言うことでストイックに言及を控えられたようです。私のような理論にいい加減な者にとっては、具体例を挙げてもらった方がわかりやすいですね。私のブログ「資本主義の変化と原理論の「開口部」」に一覧表があります。開口部に何が作用するかによって具体的な資本主義があります。例えば商品貨幣が具体的な姿として物品関係時と時代と、不換の信用貨幣の時代に分かれます。これを変容論的アプローチといいます。貨幣を例にして次の記事に表にしてあります。「「変容論的アプローチ」における用語」
非商品経済
◆「「非商品経済的要因」についてその中身としてどのようなものをお考えなのでしょうか?」
←泉氏の「非商品経済的要因」はもっと深く考えたほうがいいと思います。村上氏のコメントにもありました。下の質問への回答も参照。
◆「資本主義が発展していくとその内部に非商品経済的要因が広がっていくことはありませんか? 巨大企業内の「官僚化」や、大きな労組と大企業の関係とか。」
←私のブログの記事「資本主義経済の中に生じる非商品経済」にあります。
◆「 現代資本主義を分析するために、政府と市場が共に拡大しているとすると、政府の「経済的」活動を理論的にとらえるのか。資本家的活動とは異質な「経済的」活動が肥大化するとき、政府の行う「非商品経済的な」分析が必要なのではないか。{参考ハイルブローナーを公共部門を「一つの経済部門」として捉えている。}現代資本主義を分析するためには、公共部門と私的部門の両方の理論が経済原論として必要となるのではないか? 」
←原理論は私的な商品経済的利得の追求で成立するので、公的部門は経済原論にならないのが普通の考えでしょう。伝統的な宇野理論では公的部門は段階論で論じられてきました。しかし最近の「開口部」論を発展させれば「労働者の生活過程」に公的部門の一部を組み込むことが可能です。
◆「グレーバーが言うような基盤的コミュニズムとしての相互扶助関係というようなものを非商品経済的要因として考えたりしていますか。 」
←コメンテーターの村上さん回答がウェブサイトにあります。
その他
◆「1)報告者は両大戦間期のロシア革命や大恐慌の資本主義に与えた影響を過小評価していないか? ソ連型社会主義が崩壊したからと行って、それが資本主義に与えた影響は無視できないのではないか?」
← ロシア革命の前後で資本主義が 変化したとすれば、その前後の異なる資本主義が、 それぞれ開口部での変容を通じて、資本主義が変化すというのが今回の方法論のスタイルです。その点、質問者には原理の開口部の操作による資本主義の変容、という今回の方法には全く理解してもらえていないように思います。議論が難しい。
ただ泉氏の報告では方法論に徹するということで、資本主義の諸タイプの中身についてはストイックに避けられています。その中身を論じないことが、広く共感を得るには限界となっていると思います。
感想
◆「 とても野心的な報告でワクワクしました。ありがとうございました。開口部は不変という前提は賛成です。外的条件に関する小幡先生のイメージを是非お聞きしたいです。私自身は、非商品経済については、ヒントを頂きました。(おそらく宗教だとか環境ですね、これと経済に関わるテーマがいくつか思い浮かびました。またどこかでお話する機会があれば、宜しくお願い致します)。 」
←「開口部は不変」とは? 開口部そのものは原理論で明らかにされるので資本主義である以上、そこに開口部があるということは確かに不変です。開口部に外的条件が作用することで資本主義が変容するということでしょう。
宗教はイデオロギーとして、各種の開口部に作用する各種の外的条件の同質性を貫くものといえるでしょう。環境は、小幡氏の「開口部」論にヒントを与えた山口氏「ブラックボックス」論に整合的なものです。
今回はここまで。続きは次回。
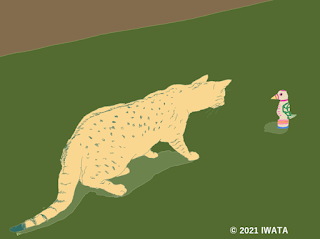


コメント
コメントを投稿