注目
【新しい地代論4】本源的自然力タイプ2(知識など)の地代には絶対地代しかない
(3月12日修正)
本源的自然力のタイプ1とタイプ2(まとめ)
本源的自然力のタイプ1は、特定の有体物に不可分に結びついており、本質的に不均質で無限に多様であるのに対して、タイプ2は特定の有体物から分離可能で、同じモノが無限に多数の有体物に同時に含まれることができる。同じ種類の生産物の生産に用いられる生産条件として、タイプ1では生産性の異なる無数の種類がある。他方、タイプ2でも種類は無限に多数であるともいえるが、1種類が広がりうる有体物の数が無限に多数であることを踏まえると、実際に用いられるタイプ2の生産条件の種類は比較的、少ない有限の数といえる。
タイプ2における地代の特徴
タイプ2の本源的自然力が生産条件となる場合は、最も優等なもののみが用いられるため、その生産物は同じ生産条件で任意に増加可能であり、調整的な生産条件となる。しかし、知的所有権などで優等な生産条件の利用を制限できる場合は、他のより劣等な生産条件との格差を根拠に地代が発生しうる。以下、利用制限が可能なタイプ2の本源的自然力として特許を例に説明する。この場合、従来の地代論との対比でいえば、土地所有者は特許権者、借地資本家は特許実施権者の産業資本家に当たる。地代は特許実施料(royalty・ライセンス料)に相当するが、同じ知識は無限数の有体物に拡張可能なので、土地のように1区画当たりの地代を想定することが難しく、生産物1単位あたりに支払われるとする
タイプ2での地代論は、タイプ1での地代論とは異なり、日高の想定した前提、つまり①同一ランク(等級)の生産条件は生産量を弾力的に伸縮できることと、②異なるランクの生産条件の間には非連続的な格差がある、という前提が成立する。
タイプ2での地代の性質について原理論での説明の例は、小幡『経済原論』205頁の問題132にある。まず、ガソリンエンジンの製造方法が特許によって所有されており、蒸気機関の製造方法は所有されていないとする。ガソリンエンジンによる生産が調整的な生産条件となると生産価格は100円、利用制限のない蒸気機関による生産が調整的な生産条件となると生産価格は110円となるとき、ガソリンエンジンの特許所有者に生じる地代の性質は何か、という問題である。
同書での解答の解説は、「ガソリン・エンジンという条件には量的制限がないから、発生するのはすべて絶対地代」(AR)となっている。
もともと『資本論』の落流と蒸気機関の例では落流を用いた生産で生じる地代はDRだから、小幡『経済原論』のこの箇所ですでに実質的に本源的自然力タイプ1とタイプ2との区別がされている。これを変容として明確にすべきだ。
この関係を図解すると次のようになる。
図1
ここではガソリンエンジンの利用の量は伸縮可能であり、ガソリンエンジンが調整的な生産条件になる。他方で蒸気機関は利用されない。
タイプ2にDRがありうるか?
ARしかないという考えに異論があるとすれば、ガソリンエンジンの特許権者が付与する特許実施権の生産量を制限すると、蒸気機関が調整的な生産条件となることがあり、その場合はガソリンエンジンの特許権者にDRが生じる、ということだろう。つまり次の図のようになる。
図2
このときのDRがDR1かDR2かを考えてみる。タイプ2では同じモノが無限に広がるため、タイプ1のDR2で想定される追加資本投下による収穫逓減はない。そのため資本のすべての追加資本投下が1次の投下と同じ生産性を持つので、DR1となる、ということになるだろう。
しかし実は、通常の原理論のように、本源的自然力所有者と産業資本が別の階級として分立している場合には、そもそもタイプ2にはDRが存在しない。なぜなら特許権者が得る特許実施料(地代)は【生産物1単位あたりの特許実施料(地代)×生産物量】なので、意図的に自分の特許による生産量を制限して、特許ではない方法での生産を放置することは考えにくい。特許実施権者の産業資本は特許実施料(地代)を払えば、だれでも自分の判断で投下資本額と生産量を決めることができる。特許となった生産条件を利用(特許実施)できるかどうかを決める権利は特許権者にあるが、生産においてどれだけの資本投下をし、どれだけの量を生産するかはその生産条件を借りた産業資本家たちによる自由競争による。つまり、ここで生産条件の利用の「制限」とは特許権者が生産量全体をコントロールする、という意味ではなく、ARとしての利用料を払わなければその生産条件は使わせない、という意味での「制限」である。タイプ1に例えるなら無限に多数の区画数のある土地を1区画ずつARをとって賃貸しするようなものである。
タイプ1では土地のような個々の生産条件の利用の数と生産量との間に緩いリンクがあったが、知識のようなタイプ2には同じ知識が無限に広がるので、所有の対象となる知識の種類数と生産量には何のリンクもない。そのため利用できるかどうかの「制限」と生産量の「制限」は異なるものになるので注意が必要だ。ここは本源的自然力タイプ1とタイプ2の区別の必要の理由でもある。
ここでの現実感覚を持ち出して、特許権者も市場規模を考慮して特許実施者に対して生産量を指示する、と主張する人がいるかもしれない。それは、本源的自然力所有者が産業資本と半ば結合していることを半ば無前提に前提化する誤りである。土地所有者が自分の土地に工場を建てたり、商業資本が自身の商品の仕入れ商品について産業資本に指示したりすることをもって、土地所有者や商業資本の産業資本的性格を主張するようなものだ。本源的自然力と産業資本の結合と分離の問題は次回の記事に論じる。
複数のARが存在する可能性
以上のように、本源的自然力タイプ2が地代を得る場合はARしかない。そのうえで次に、生産性の高い生産条件をもたらすには代替的な複数の特許がある場合を考える。上記の小幡『経済原論』の例を拡張して、生産性の高い特許付き原動機①、それほど高くない特許付き原動機②、特許無し原動機の三つに分ける。知的所有権は一般に、既存の知識とは大きく異なることが求められるので、生産性において最優等の特許付き原動機①と特許無し原動機の間に、生産性が互いに異なる特許付き原動機②③…が無数にあるとは考えられない。比較的、有限の少数であると考えるべきなので、タイプ1のように曲線ではなく、非連続的な有限の数として表示されるべきである。
図1と同様に、特許なしの生産条件がARの上限とし、それに近いARが要求されると想定すると、ARは次の図のようになる。
図3
原動機①の特許権者の特許実施料(地代)総額は【AR①×原動機①による生産物量】、原動機①の特許権者の特許実施料総額は【AR②×原動機②による生産物量】となる。ここではARはAR①とAR②の二つの量が存在する。これら2つの原動機の技術という生産条件は、特許を実施しようとする産業資本家にとってはどちらでも一般的利潤率を得られるのだからどちらでよい。そのため、原動機①も②もともに調整的生産条件になる。
しかしここで原動機①の特許権者が特許実施権者に要求する特許使用料を【AR①-AR②】以下に下げれば次の図のようになる。
図4
原動機②の技術を用いた産業資本では投下資本額の回収と平均利潤の獲得ができず、原動機②の技術は生産条件として用いられなくなり、調整的な生産条件は原動機①による生産のみになる。
ここで原動機①の特許権者が得る特許実施料総額は【(AR①-AR②)×この生産物の生産量】になる。そうすると生産物1単位あたりのARは減るが、他方で自分が受け取るARの対象となる生産物の量は増える。
原動機①の特許権者が要求する特許使用料の額としてAR①の大きさを選ぶか、【AR①-AR②】の大きさを選ぶかは、AR①とAR②の大きさの比較によるだろう。つまりAR②がAR①に近ければ、要求する特許使用料はAR①の大きさとなり、市場を原動機②による生産と分け合うことになる。AR②≪AR①であれば要求する特許使用料を【AR①-AR②】へと少し下げて、原動機②の技術による生産を排除して、自分が受け取る特許使用料の対象となる生産物量を増やすことで特許実施料(地代)総額を増やすことができる。
生産価格体系との関係(本源的自然力タイプ2)
本源的自然力タイプ2では調整的な生産条件にARが上乗せされるので、生産価格の式は以下のようになる。
(a1nPA1 + a2nPA2 + a3nPA3 + … + annPAn ) (1 + R ) + AR =
なお、投入要素A1, A2, A3 … An から地代を必要とする生産物Anを生産する。各投入要素の単位当たりの価格がPA1, PA", PA3 … PAn、生産物Anを生産するための各投入要素の係数がa1n, a2n, a3n, …ann だとする。
この生産価格体系については以前の記事の「再生産過程に土地と地代を導入し、生産価格と絶対地代を両立させることは可能」で説明した。
図3のように生産条件が2種類あり、ARが2種類ある場合も、どちらかの生産条件を式に用いればもう一つも決まる。
タイプ1での生産価格と地代との関係は以前の記事参照。
まとめ
以上のように、本源的自然力タイプ2で地代が生じる場合はARのみであり、同一の生産物で複数の種類の制限しうる生産条件があれば、異なるARの額が生じる場合があることがわかる。
こうして、タイプ1との地代の違いが明瞭になる。つまり、タイプ1ではDR2が基本であり、補足的に、その生産条件の利用を排除するARが存在する。他方、タイプ2ではARが基本であり、利用しうる異なる生産条件ごとにARの異なる額が生じる場合がある。
従来の原理論での地代論はタイプ1に該当するものとタイプ2に該当するものを不鮮明に混ぜ合わせていたので、さまざまな地代の性質が不鮮明だった。本源的自然力をタイプ1とタイプ2に概念的に分けることでさまざまな地代の性質も明確になる。最近、特に言われるようになった、地代論の知識の領域への拡張も、変容論として2つのタイプの違いを明確にすることが必要となる。本源的自然力そのものとしての違いだけでなく、地代の種類の違い、本源的自然力の個々の違いが連続的な曲線で示されるか、非連続的な有限数で示されるか、といった違いを明確にする必要がある。また、本記事ではタイプ2の特許の地代(特許使用料)は生産物1単位あたりに支払われる額としたが、以前の記事のタイプ1の土地の地代は土地1区画あたりで考えてある。いずれにしても投下資本の超過利潤が地代となることは同じだが、産業資本が借りる本源的自然力が有体物として限定されるか、限定されないかによって地代の支払いの基準が異なる可能性もある。
もちろん現実にはタイプ1の性質とタイプ2の性質を併せ持つものもあれば、本源的自然力の所有者とそれを借りる産業資本を兼ねる存在もあるだろう。しかし原理論の方法として、本源的自然力の変容として、一定程度の抽象度を維持したまま、2つの異なるタイプを明確化することが必要である。
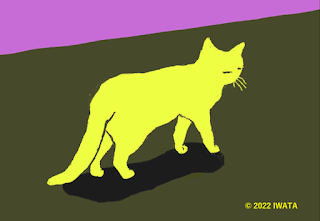





コメント
コメントを投稿