注目
変容論的アプローチによる段階論:利潤の測定と会計基準
変容論的アプローチによる段階論の再構成をこのブログではいくつかの項目で説明してきた(商業資本、地代と知識、労働過程など)。
今回は利潤の測定について。
「金融化と資産負債アプローチ」と称して研究会で報告をする。
利潤の測定は原理論では流通論と機構論で現れる。変容論的アプローチで図解すると次の通り。
三段階論と利潤の測定・会計規則との関係
資本とは自己増殖する価値の運動体で、 資本主義経済は利潤を追求する資本の活動が中心となって編成される経済体制である。
しかし、ここでの問題は、利潤(利益)の測り方には規則があり、その規則は歴史的に変化することだ。規則の変化は資本主義経済自体の歴史的変化を反映している。ここで段階論が生じるとともに、唯物史観も示される。つまり経済の在り方という下部構造に密着して法や社会制度といった上部構造の中でも一番下に位置するのが会計規則となる。その時代の経済の仕組みと、それにそくした利潤の測定方法とその変化が唯物史観に対応している。
更に遡れば原理論のレベルでも会計規則の起点がある。つまりまだ売れていない商品の価値の評価には複数の方法があり、利潤の測定にも複数の分岐の可能性がある。原理論におけるこうした分岐の可能性は一般に「変容論的アプローチ」とよばれる。こうして原理論ベースにして段階論を説くことができる。
会計の規則についての最近の変化を見るには、19世紀末から第二次世界大戦後直後までの「収益費用アプローチ」の確立、その後1970年代から徐々に始まる「「資産負債アプローチ」への変化が特徴となる 。ただし、ここにはややこしい問題がある。それはまず、現実には2つのアプローチのハイブリッドであること、また、日本基準では国際基準(IFRSなど)に比べて収益費用アプローチの余地が大きいこと、さらに、会計規則を学習するとそれ自体が固定的な体系と思ってしまうこと、などなど。こうした事情のため段階的変化が見えづらくなっている。そのため現実の制度をそのまま見るのではなく、現在の制度の背景にある複数の理念や制度の変化の方向性を、あえて言えば強調また延長して捉える必要がある。これは理論に必ず伴う抽象化である。
このように理念としての2つのアプローチを強調した上で、ある特定の時代や地域について、その2つのアプローチの相互関係やバランスの変化の分析が可能になる。これが現状分析になる。焦点としてはIFRSにおけるFVTPLやFVOCIの扱い、IFRSと日本基準と違いの検討などになろう
こうして会計規則の分析は原理論、段階論、現状分析、さらに唯物史観をトータルに把握する非常によい材料である。
さらに現状分析の一環として「金融化」を理解するのに重要だ。資産負債アプローチは、金融商品だけでなく、実物資産も含めてあらゆるものを金融資産のように処理する特徴がある。つまり将来の収益を現在価値に換算して評価するという方法である。他方、伝統的な収益費用アプローチにでは過去の支出額を現在と将来にわたって配分することが中心であり、両者は逆向きになる。
こうすることで実物資産も金融資産のように市場で売買することが可能となる。こうした動きを一部の会計学者は「産業資本主義から金融資本主義への変化」と説く。この点に「金融化」をめぐる重要なポイントがあることがわかる。金融化に特にかかわる会計上の概念としては、公正価値(時価)、包括利益などがある。
また、金融化を金融資産総額とGDPとの関係などでいうことがあるが、しかし今回、報告するように、金融資産も保有目的が異なる。産業資本主義としての金融資産もあれば、金融化にふさわしい金融化もある。このあたり、もう少し踏み込んで分析する必要がある。
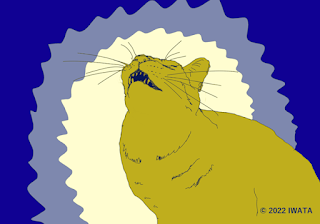


コメント
コメントを投稿